※今回の記事は難易度がかなり高めです。後日、ライト版を書く予定です。
会計情報に隠された超過リターンの源泉
投資の世界において、株価は常に利用可能な全ての情報を織り込んでいるという「効率的市場仮説」は、現代ファイナンス理論の根幹をなす考え方です。しかし、学術研究の進展は、この強力な仮説では説明が難しい、市場に存在する数々のアノマリー(経験則)を明らかにしてきました。その中でも、企業の会計情報に根差し、投資家の行動心理と深く関わることで特に重要視されているのが「アクルーアル(発生主義会計)・アノマリー」です。
多くの投資家が企業の業績を判断する際に最も注目する指標は、おそらく「純利益」でしょう。しかし、この公式な業績指標は必ずしもその企業の真の価値創造能力や将来の収益性を正確に反映しているとは限りません。なぜなら、会計上の利益には、実際の現金の裏付けがある部分と、会計上の見積もりや将来への期待に基づく調整に過ぎない部分が混在しているからです。この「利益の質」の違いを市場参加者の多くが見過ごすことで、将来のリターンを予測しうるシステマティックな価格の歪みが生まれます。
今回は、このアクルーアル・アノマリーのメカニズムを、その発見のきっかけとなった1996年の独創的な研究から、2020年以降の最新の国際的な実証研究まで、査読付き学術論文のみを厳密な根拠として徹底的に解剖します。単なる現象の解説に留まらず、当メディア「Asymmetry Signal」の思想に基づき、超過リターンを生み出す「非対称性」の源泉と、アノマリーが完全には消滅せずに存続する理由である市場の「摩擦」の正体を明らかにします。これにより、読者の皆さんが会計情報の深層を読み解くための一助となることを目指します。
アクルーアル・アノマリーの概論 ― 利益の質とは何か
アクルーアル・アノマリーを理解するためには、まず会計の基本的な考え方、特に利益がどのように計算されるのかを知る必要があります。企業の利益とキャッシュ・フローの間に存在する「差」こそが、このアノマリーの核心だからです。
現金主義 vs. 発生主義:会計の二つの顔
企業の経済活動を記録する会計には、大きく分けて二つの考え方が存在します。「現金主義会計」と「発生主義会計」です[1][2][3][4][5]。
- 現金主義会計 (Cash Basis Accounting): 現金の入金があった時点で「収益」を、現金の出金があった時点で「費用」を認識する、非常にシンプルで直感的な方法です。個人の家計簿に近い考え方であり、手元の現金残高を正確に把握できる利点があります[1][3]。
- 発生主義会計 (Accrual Basis Accounting): 一方、現在の上場企業の財務諸表で標準的に採用されているのが発生主義会計です。これは、現金のやり取りのタイミングに関わらず、経済的な価値が発生・消費された事実に基づいて収益や費用を認識します[2][5]。 例えば、商品を顧客に納品し、代金は翌月末に受け取る「掛け売り」の場合、発生主義では商品を納品した時点で売上(収益)を計上します。このとき、まだ受け取っていない代金は「売掛金」として資産に計上されます。
発生主義は、企業の特定の期間における経営成績をより正確に反映できるという大きな利点があります。しかし、そのプロセスには将来の入金額の見積もり(貸倒引当金など)や資産の評価といった、経営者の判断や予測が介在します。この会計上の見積もりや調整項目のことを総称して「アクルーアル(Accruals)」と呼びます。そして、このアクルーアルの存在こそが、会計上の「利益」と実際の「キャッシュ・フロー」の間に乖離を生じさせる根源となるのです[7][8]。
スローン(1996)の画期的な発見:「利益固執仮説」とアノマリーの誕生
アクルーアル・アノマリーの存在を学術的に初めて明らかにしたのは、ミシガン大学のRichard Sloan教授が1996年に発表した画期的な論文「Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?」です[9]。この研究は、会計情報と株価形成の関係に新たな光を当て、その後のアノマリー研究に絶大な影響を与えました[10][11][13]。
Sloan教授の発見の核心は、以下の二点に集約されます。
- 利益の構成要素と持続性の非対称性: 彼は、企業の利益を「キャッシュ・フロー要素(営業キャッシュ・フロー)」と「アクルーアル要素」に分解し、それぞれの要素が将来の利益にどれだけ持続するかを分析しました。その結果、キャッシュ・フローを源泉とする利益は持続性が高い一方で、アクルーアルを源泉とする利益は翌期以降に反転する傾向が強く、持続性が低いという明確な非対称性があることを実証しました 。これは、アクルーアルが多くを占める利益は「質が低い」ことを意味します。
- 利益固執仮説 (Earnings Fixation Hypothesis): 上記のような性質の違いがあるにもかかわらず、市場の投資家は利益の総額という表面的な数字にのみ注目し(固執し)、その内訳であるキャッシュ・フローとアクルーアルの質的な違いを株価に十分に織り込んでいない、とSloan教授は主張しました。このため、高アクルーアル(低品質な利益)の企業は市場に過大評価され、逆に低アクルーアル(高品質な利益)の企業は過小評価される傾向が生まれます[14]。
この投資家の認知バイアスによって生じたミスプライシングが、将来的に修正される過程で、予測可能なリターン・パターンが生まれます。すなわち、過小評価されていた低アクルーアル企業群は市場平均を上回るリターンを記録し、過大評価されていた高アクルーアル企業群は市場平均を下回るリターンに甘んじることになります。これが「アクルーアル・アノマリー」の正体です。
アクルーアルの計算方法:貸借対照表アプローチ
では、投資家はどのようにしてアクルーアルを測定すればよいのでしょうか。最も一般的で、歴史的なデータにも適用しやすいのが、貸借対照表(バランスシート)の変動から計算する方法です。これはキャッシュ・フロー計算書が一般化する以前のデータも利用できるため、長期的な分析において非常に有用です 。Sloan (1996) が用いた計算式は以下の通りです。
Accruals=(ΔCA−ΔCash)−(ΔCL−ΔSTD−ΔITP)−Dep
ここで、各項目は以下の通りです。
- ΔCA: 流動資産の期末・期首差額
- ΔCash: 現金及び現金同等物の期末・期首差額
- ΔCL: 流動負債の期末・期首差額
- ΔSTD: 短期有利子負債の期末・期首差額
- ΔITP: 未払法人税等の期末・期首差額
- Dep: 減価償却費
この式は、本質的に「(運転資本の増加額) – (減価償却費)」を計算しており、非現金費用である減価償却費と、運転資本への投資(売掛金や棚卸資産の増加など)を捉えています。
なお、算出されたアクルーアル額は企業の規模に依存するため、異なる企業間で比較可能にするために、期首と期末の総資産の平均値で割って標準化するのが一般的です[15] 。
アノマリーの長所と短所、そして収益機会の実例
アクルーアル・アノマリーは、学術的に非常に興味深い現象であるだけでなく、投資戦略としても多くの示唆を与えます。ここでは、その長所と短所を両論併記の形で掘り下げ、近年の研究に基づいた収益機会の実例を紹介します。
長所と強み:ファンダメンタルズ分析の深化
アクルーアル戦略が持つ最大の強みは、その根拠が企業のファンダメンタルズに深く結びついている点にあります。
- 利益の質の可視化: この戦略は、単に利益が伸びているかどうかだけでなく、その成長が持続可能なキャッシュ創出能力に裏打ちされているか、それとも会計上の見積もりによって一時的にかさ上げされているだけなのかを評価する枠組みを提供します。例えば、売上を急拡大させるために与信基準を緩めれば、売掛金(アクルーアルの一種)が急増し、利益は増加しますが、その質は低下します。これは将来の貸倒れリスクや業績悪化の予兆となり得ます[7][8] 。
- 会計操作の早期発見: 経営者が短期的な利益目標を達成するために利益操作を行う際、裁量的なアクルーアル項目(引当金の調整や売上計上時期の変更など)を利用することがあります。アクルーアルの水準を監視することは、こうした会計操作の兆候を早期に捉え、潜在的なリスクを回避するための一助となります[7] 。
- 論理的で透明性の高いシグナル: 株価の過去の値動き(モメンタムなど)に依存する戦略とは異なり、アクルーアル戦略は公開されている財務諸表データに基づいています。そのため、なぜ特定の銘柄が選好されるのか(あるいは敬遠されるのか)についての論理的根拠が明確であり、投資家は戦略の背景を深く理解することができます。
収益機会の実例:2020年以降の国際的な学術研究から
多くのアノマリーは、その存在が広く知られるようになると、裁定取引によって超過リターンが減衰、あるいは消滅する傾向があります。アクルーアル・アノマリーも例外ではなく、その発見後、特に米国市場では収益性が低下したとの報告もあります。しかし、近年の研究は、特に国際市場において、このアノマリーが依然として有効であることを示唆しています。
- 欧州市場での実証研究: Alberto Sandoval氏らが2022年に発表した論文では、欧州の主要株価指数であるSTOXX Europe 600の構成銘柄を対象に、2000年から2021年までの期間でアクルーアル戦略の有効性が検証されました。その結果、低アクルーアル企業群を買い、高アクルーアル企業群を空売りするロング・ショート戦略は、統計的に有意なプラスのリターンを生み出すことが確認されました。特に、長期的な営業活動に関連するアクルーアル(非流動営業資産・負債の変動)に着目した戦略では、年率2%から6%の範囲で超過リターンが観測されており、アノマリーが現代の欧州市場でも機能していることを示しています[17] 。
- 日本市場での実証研究: Hiroaki Isoyama氏が2024年に発表した論文は、日本市場におけるアクルーアル・アノマリーを、情報の非対称性という観点から分析しました。この研究は、アクルーアル情報が投資家間で均等に解釈・評価されていないために生じる「逆選択リスク」が、アノマリーの背景にあることを示唆しています。つまり、情報の非対称性が存在する限り、アクルーアル・アノマリーは存続しうるという理論的根拠を提供しており、日本市場におけるアノマリーの有効性を補強するものです[18]。
これらの近年の研究成果をまとめたのが以下の表です。
表:アクルーアル戦略の近年のパフォーマンス(2020年以降に発表された研究)
| 著者, 年 | 対象市場 | 分析期間 | 戦略概要 | 超過リターン年率(報告値) | 統計的有意性 |
| Sandoval, A.ら(2022) | 欧州 (STOXX 600) | 2000-2021 | 長期営業アクルーアルのロング・ショート | 2%~6% | 有意 |
| Isoyama (2024) | 日本 | 1996-2020 | アクルーアル・ファクター | 有意なリスクプレミアムを報告 | 有意 |
この表が示すように、アクルーアル・アノマリーは過去の遺物ではなく、現代の国際市場においても観測され、超過リターンの源泉となりうる現象であることが、最新の学術研究によって裏付けられています。
短所とリスク:手放しでは称賛できない現実
一方で、アクルーアル戦略の実践には無視できない短所やリスクも存在します。
- アノマリーの減衰 (Anomaly Decay): Sloan (1996) の論文が広く知られるようになった後、特に2002年以降、米国市場におけるアクルーアル・アノマリーの収益性は著しく低下したことが複数の研究で報告されています。これは、ヘッジファンドをはじめとする洗練された投資家がこのアノマリーを認識し、積極的に裁定取引を行った結果、市場がより効率的になったためと考えられています[19][20] 。
- 取引コストと流動性の問題: アノマリーによるリターンの多くは、高アクルーアル企業群(ショートサイド)の株価下落によってもたらされることが知られています 。しかし、これらの企業はしばしば小型株であったり、流動性が低かったり、あるいは投資家の間で人気が高く株価が割高であったりするため、空売りが物理的に困難であったり、高い貸株料や売買コストが発生したりします。これらの取引コストを考慮すると、理論上の超過リターンが相殺されてしまう可能性があります[21][22][23]。
- クオリティ・トラップの可能性: 低アクルーアルであることが、必ずしも将来の好業績を保証するわけではありません。会計基準の変更や、特定の経済環境下では、低アクルーアル企業が必ずしも優良企業であるとは限らず、投資家を誤った判断に導く「クオリティ・トラップ」となる可能性も指摘されています。
Asymmetry Signalの視点 ― 非対称性と摩擦
アクルーアル・アノマリーは、当メディア「Asymmetry Signal」が探求する「非対称性」と「摩擦」という二つの概念を体現する、まさに格好の事例と言えます。ここでは、独自の視点からこのアノマリーの本質を深掘りします。
非対称性(Asymmetry):利益の質の歪みが生むリターンの源泉
アクルーアル・アノマリーから得られる超過リターンは、市場に存在する様々な「非対称性」に根差しています。
- 情報の非対称性(持続性の歪み): このアノマリーの根源にあるのは、利益を構成するキャッシュ・フローとアクルーアルの将来利益に対する「持続性の非対称性」です。キャッシュ・フローは企業の恒常的な収益力を反映し持続性が高いのに対し、アクルーアルは一時的な会計上の調整であることが多く、持続性が低いという本質的な違いがあります[9][11]。市場参加者の多くがこの非対称性を十分に認識せず、利益という一つの指標を均質的なものとして評価してしまうことが、最初の価格の歪みを生み出します。
- リターンの非対称性(ショートサイドの寄与): アノマリー戦略のパフォーマンスを分解すると、その超過リターンの多くが、ロングサイド(低アクルーアル企業の買い)の良好なパフォーマンスよりも、ショートサイド(高アクルーアル企業の売り)の著しいパフォーマンス不振によってもたらされていることが、多くの研究で示唆されています[21][22] 。これは、市場による過大評価の修正が、過小評価の修正よりも大きなリターンを生むという「リターンの非対称性」を示しています。つまり、良い企業がさらに良く評価されることよりも、悪い企業の実態が暴かれることの方が、株価へのインパクトが大きいのです。
- リスクの非対称性(裁定コストの歪み): ロングサイドとショートサイドでは、取引に伴うリスクとコストが非対称です。ショートサイドの対象となる高アクルーアル企業は、しばしば小型株であったり、流動性が低かったり、ボラティリティが高かったりする特性を持ちます。これにより、空売りに伴う貸株料や取引コストが非対称的に高くなり、裁定取引のリスクが増大します[15][23][25] 。このリスク構造の非対称性が、ミスプライシングの完全な是正を妨げ、アノマリーが存続する土壌を提供しています。
摩擦(Friction):なぜアノマリーは完全には消滅しないのか
もし市場が完全に効率的で、取引に何らの障害もなければ、アクルーアル・アノマリーのような予測可能なリターンは即座に裁定取引によって消滅するはずです。しかし、現実の市場には様々な「摩擦(Friction)」が存在し、アノマリーの存続を許しています。
- 裁定取引の限界 (Limits to Arbitrage):
- 理論的背景: Shleifer and Vishny (1997) らの研究が示すように、教科書的なリスクフリーの裁定取引は現実には稀です。実際の裁定取引には資本が必要であり、リスクを伴います。特に、プロの裁定取引者が他者の資金を運用する場合、短期的な損失が資金の引き揚げを招き、最も裁定機会が大きい局面で取引を停止せざるを得なくなる可能性があります [26][27]。
- 空売り制約という摩擦: アクルーアル・アノマリーのショートサイドを取引するには空売りが不可欠ですが、これが最大の摩擦の一つとなります。特に高アクルーアルの小型株は、貸株市場での調達が困難であったり、法規制によって空売りが制限されたりすることがあります[28][29] 。
- 因果関係の証明: この摩擦の重要性は、Chu, Hirshleifer, and Ma (2020) による研究で強力に裏付けられています。彼らは、米国証券取引委員会(SEC)が2005年から2007年にかけて実施した「Regulation SHO」という規制変更を自然実験として利用しました。この規制緩和により、ランダムに選ばれた一部の銘柄(パイロット銘柄)で空売り制約が一時的に緩和されました。分析の結果、このパイロット銘柄群では、アクルーアル・アノマリーを含む11の主要なアノマリーのリターンが、対照群に比べて統計的に有意に低下したことが確認されました。特に、その効果はショートサイドのパフォーマンス改善(つまり、空売り戦略の利益減少)によってもたらされており、空売り制約という「摩擦」がアノマリー存続の直接的な原因であることを因果的に示しています [26][27]。
- 制限された注意力 (Limited Investor Attention):
- 認知バイアスという摩擦: 裁定取引の限界が「制度的・構造的」な摩擦であるとすれば、投資家の「限定された注意力」は「認知的」な摩擦です。人間は利用可能な全ての情報を完璧に処理できるわけではなく、認知的なリソースには限りがあります[30][31][32][33][34] 。特に個人投資家は、企業の財務諸表の脚注に記載されるようなアクルーアルの詳細な内訳まで分析する時間や専門知識を持たないことが多く、結果として利益の質を見過ごしてしまいます 。
- 情報の顕著性(Salience): 利益という単一の数字は、メディアでも大きく報じられ、非常に顕著(salient)で投資家の注意を引きやすい情報です。一方で、その内訳であるアクルーアルやキャッシュ・フローは専門的な分析を要し、顕著性が低い情報です。この情報の顕著性の違いが、投資家の注意を利益総額に偏らせ、アクルーアル情報を軽視させる一因となります。
- DisFrictionへの示唆: これらの「摩擦」は、市場の非効率性を示すと同時に、洗練された投資家にとってはエッジ(優位性)の源泉となります。例えば、空売りコストが比較的低く、流動性も確保されているにもかかわらず、依然としてアクルーアル・アノマリーが観測される銘柄群を特定すること。あるいは、多数の企業の決算発表が集中し、市場参加者の注意が散漫になりがちな時期を狙って取引を行うこと。これらは、市場に存在する「摩擦」を特定し、それを乗り越える(DisFriction)ことで、持続可能な超過リターンを追求する具体的なアプローチとなりうるのです。
用語集
本記事をより深く理解するために、重要な専門用語を解説します。
- 発生主義会計 (Accrual Accounting) 現金の収支に関わらず、経済的価値の発生・消費の事実に基づいて収益や費用を認識する会計手法。企業の期間業績をより正確に表すために、現代の企業会計で標準的に用いられています[1][2] 。
- キャッシュ・フロー (Cash Flow) 企業活動によって実際に生み出された現金の流れのこと。特に、本業の儲けを示す「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、企業の真の稼ぐ力を示す指標として重視されます[6][9] 。
- アクルーアル (Accruals) 発生主義会計上の利益と、現金主義に基づいたキャッシュ・フローとの差額を生み出す会計上の見積もりや調整項目の総称。売掛金や棚卸資産の増減、減価償却費などが含まれます[8][15] 。
- アノマリー (Anomaly) 「変則性」を意味し、効率的市場仮説などの現代ファイナンス理論ではうまく説明できないが、市場で経験的に観測される株価の規則的なパターンのことです。サイズ効果やバリュー効果などが知られています[36][37] 。
- 利益固執仮説 (Earnings Fixation Hypothesis) 投資家が利益の総額という分かりやすい指標に注目しすぎるあまり、その構成要素であるキャッシュ・フローとアクルーアルの質的な違い(将来への持続性の違い)を無視してしまうという、投資家の認知バイアスに関する仮説です[9][15] 。
- ロング・ショート戦略 (Long-Short Strategy) 割安と判断した資産を買い持ち(ロング)し、同時に割高と判断した資産を空売り(ショート)する投資戦略。市場全体の値動きの影響を低減させつつ、銘柄間の相対的な価格差からリターンを狙います[17]。
- 裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つはずの資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を確定させる取引。市場の価格発見機能を担い、非効率性を是正する力となります[26][27] 。
- 裁定取引の限界 (Limits to Arbitrage) 取引コスト、空売り制約、情報コスト、資金調達の制約といった現実世界の様々な「摩擦」により、裁定取引が理論通りに機能せず、ミスプライシングが市場に存続してしまう状況を指します [25][26][27]。
- 限定された注意力 (Limited Attention) 人間の認知能力には限界があり、利用可能な全ての情報を同時に処理することはできないとする行動経済学の概念。投資家がどの情報に注目し、どの情報を見過ごすかが、投資判断に影響を与えます[30][31] 。
- シャープレシオ (Sharpe Ratio) リスク(リターンの標準偏差)1単位あたりで、どれだけリスクフリーレートを上回るリターンを得られたかを示す指標。投資の効率性を測るために広く用いられます。数値が高いほど、効率的な運用であったことを意味します。
参考文献一覧
1. Cash vs. Accrual Business Accounting – Paychex2. Accrual Accounting vs. Cash Basis Accounting: What’s the Difference? – Investopedia
3. Cash vs. Accrual Accounting: The Fundamental Differences – McCracken Alliance
4. Cash vs. Accrual Accounting: Differences & Which Is Best | Rippling
5. Accrual Accounting vs. Cash Basis Accounting | Differences – Wall Street Prep
6. Oh, H. I., & Penman, S. (2020). The Accruals-Cash Flow Relation and the Evaluation of Accrual Accounting. Columbia Business School Research Paper.
7. Cecchi, M. (2018). The accrual anomaly: The dampening effect of adjusting entries. *Corporate Ownership and Control*, *16*(1), 94-106.
8. Dechow, P. M., Khimich, N. V., & Sloan, R. G. (2011). *The Accrual Anomaly*. SSRN Electronic Journal.
9. Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, *71*(3), 289–315.
10. Bae, G. S. (1999). *Do Stock Prices Fully Reflect Information in Current Earnings, Cash Flows Accruals?: Evidence From Quarterly Data*.
11. Heyns, P. J., Hamman, W. D., & Smit, E. V. D. M. (1999). Do share prices fully reflect the information about future earnings in accruals and cash flow? *South African Journal of Business Management*, *30*(4).
13. Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J. T., & Nikolaev, V. (2016). Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross section of stock returns. *Journal of Financial Economics*, *121*(1), 28-45.
14. Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289–315.
15. Accrual Anomaly – Quantpedia
16. Sawhney, G. (2018). Accrual Anomaly. QuantConnect.
17. Sandoval, A., Márquez, J., & Cervera, I. (2022). The countercyclical long-term operating accrual-based trading strategy in the Stoxx Europe 600 index: The importance of asset and liability components. *PLoS ONE*, *17*(5), e0266045.
18. Isoyama, H. (2024). Accruals anomalies could be explained by the adverse selection risk induced by the information structure: the case of the Japanese securities market. *Cogent Economics & Finance*, *12*(1).
19. Green, J., Hand, J. R. M., & Soliman, M. T. (2011). Going, Going, Gone? The Apparent Demise of the Accruals Anomaly. *Management Science*, *57*(5), 797-816.
20. Mohanram, P. (2011). *The Role of Analysts’ Cash Flow Forecasts in the Decline of the Accruals Anomaly*. NYU Stern School of Business.
21. Koerniadi, H., & Tourani-Rad, A. (2007). Accrual or cash flow anomaly? Evidence from New Zealand. *Accounting Research Journal*, *20*(1), 21-36.
22. Kothari, S. P., Loutskina, E., & Nikolaev, V. (2006). *Agency Theory of Overvalued Equity as an Explanation for the Accrual Anomaly*. CentER Discussion Paper.
23. Bekjarovski, F. (2017). *How do short selling costs and restrictions affect the profitability of stock anomalies?*.
25. Li, X., & Sullivan, R. N. (2011). The Limits to Arbitrage Revisited: The Accrual and Asset Growth Anomalies. *Financial Analysts Journal*, *67*(4), 53-69.
26. Chu, Y., Hirshleifer, D., & Ma, L. (2017). *The Causal Effect of Limits to Arbitrage on Asset Pricing Anomalies* (NBER Working Paper No. 24144). National Bureau of Economic Research.
27. Chu, Y., Hirshleifer, D., & Ma, L. (2020). The Causal Effect of Limits to Arbitrage on Asset Pricing Anomalies. *The Journal of Finance*, *75*(3), 1487-1527.
28. Lev, B., & Nissim, D. (2006). The Persistence of the Accruals Anomaly. *Contemporary Accounting Research*, *23*(1), 193-226.
29. Hirshleifer, D., Teoh, S. H., & Yu, J. J. (2011). Short Arbitrage, Return Asymmetry, and the Accrual Anomaly. *The Review of Financial Studies*, *24*(7), 2429–2461.
30. Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2005). *Limited Investor Attention and Earnings-Related Under- and Over-Reactions*. SSRN Electronic Journal.
31. Nekrasov, A., Teoh, S. H., & Wu, S. (2022). *Limited Attention*.
32. Wang, Y., Zhai, Y. A., & Lin, Y. (2024). Signal or pressure? Retail investor attention and MD&A quality. *Journal of Accounting Literature*, *47*(5), 388-413.
33. Wang, Y., Zhai, Y. A., & Lin, Y. (2022). Investor Limited Attention, Opinion Divergence, and Post-earnings-announcement Drift: Evidence from China. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, *86*, 348-363.
34. Feng, Q., Ning, D., Zhang, W., & Zhou, R. (2022). Investor’s Inattention and Earnings Announcement Effects on Tomb-Sweeping Day in China. *Credit and Capital arkets*, *55*(2), 291-320.
36. Toluwa, O., & Otakefe, J. P. (2023). Accrual Anomaly: A Review of Literature. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 7(4), 1135-1145.
37.McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? The Journal of Finance, 71(1), 5-32.

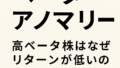
コメント