概論
テクニカル分析の世界において、相対力指数(RSI)ほど広く知られ、利用されているオシレーター系指標は数少ないでしょう。「70以上は買われすぎ」「30以下は売られすぎ」というシンプルなルールは、多くのトレーダーにとって、市場の反転を捉えるための魅力的なシグナルとして機能してきました。
RSIは、1978年にJ・ウエルズ・ワイルダーJr.がその著書「New Concepts in Technical Trading Systems」で発表した、市場の勢いを測定するための指標です [1]。その計算式は、一定期間(通常は14期間)における値上がり幅と値下がり幅の平均を基に、価格変動の強弱を0から100の範囲で数値化するものです。ワイルダー自身が提唱した、70と30を「買われすぎ」「売られすぎ」の境界線とする逆張りの考え方は、今日に至るまでテクニカル分析の教科書的な戦略として語り継がれています。
しかし、この直感的に分かりやすいルールは、果たして学術的な検証に耐えうるものなのでしょうか。市場の非効率性を捉え、統計的に有意な利益を生み出すことができる「エッジ」となり得るのか。あるいは、単なる経験則や、特定の市場環境下でのみ機能する限定的な現象なのでしょうか。本稿では、この古典的な問いに対し、感情や逸話を排し、複数の査読付き学術論文の知見を基に、RSIの逆張り戦略が持つ有効性と、その深刻な限界について、多角的に検証していきます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
RSIの70/30ルールは、その単純さの裏に、市場の特定の局面を捉える「強み」と、致命的となり得る「弱み」を併せ持っています。学術研究は、この二面性を客観的なデータで浮き彫りにしています。
長所、強み、有用な点について
RSIの逆張り戦略が持つ最大の強みは、市場が一定の範囲内で上下動を繰り返す「レンジ相場」や、価格が平均に回帰する傾向を持つ局面において、有効なシグナルを生成する可能性がある点です。
収益事例として、ロンドン証券取引所のFT30指数を60年間にわたって分析した研究が挙げられます。この研究では、RSIのルールを用いた取引が、多くの場合においてバイ・アンド・ホールド戦略を上回るリターンを生成できたことが示されています [3]。
また、テクニカル分析の有効性をより科学的に検証しようとした別の研究では、客観的なアルゴリズムを用いてチャートパターンを検出した結果、いくつかのテクニカル指標が、単なる偶然を超えた「増分的な情報を提供し、いくらかの実践的価値を持つ可能性がある」と結論付けられています [6]。これらの研究は、RSIのような指標が、特定の条件下で市場の非効率性を捉えるツールとなり得ることを示唆しています。
短所、弱み、リスクについて
一方で、RSIの逆張り戦略が直面する現実は、決して甘いものではありません。その有効性は市場の状況に大きく左右され、多くの学術研究がその収益性に厳しい目を向けています。
最大の損失事例は、強力なトレンドが発生した場合です。強気相場では、RSIは「買われすぎ」とされる70のレベルを遥かに超え、長期間にわたって高止まりすることが頻繁にあります。この状況で教科書通りに売り向かえば、その後の大きな上昇トレンドを逃し、深刻な機会損失、あるいは空売りの場合は壊滅的な損失を被る可能性があります。
この弱点は、複数の実証研究によって裏付けられています。例えば、S&P 500指数を対象とした59年間の分析では、RSIを含む個別のテクニカル指標の多くは、取引コストを考慮すると、バイ・アンド・ホールド戦略をアウトパフォームできなかったことが報告されています [4]。
さらに、テクニカル分析の有効性を検証した95の学術論文を包括的にレビューしたある研究によれば、報告されている利益の多くは、リスクおよび取引コストの見積もりの難しさといった問題を抱えており、その収益性は確固たるものではないと結論付けられています [2]。
そして、より根源的な問題として、テクニカル分析の研究そのものが抱える「データスヌーピング」のバイアスが指摘されています。これは、研究者が膨大な過去のデータの中から、偶然最も成績の良かったルールを見つけ出してしまう統計的な罠です。ある研究では、このデータスヌーピングのバイアスを考慮に入れると、最良のテクニカルルールのリターンでさえ、その優位性が統計的に説明できてしまう可能性が示されています [5]。
非対称性と摩擦の視点から
RSIの逆張り戦略は、なぜある時は機能し、ある時は破綻するのでしょうか。その本質は、「非対称性」と「摩擦」という当メディアの根幹をなす視点から解き明かすことができます。
Asymmetry:市場レジームによる有効性の非対称性
RSIが示すシグナルの価値は、市場が置かれている状況、すなわち「市場レジーム」によって、極端に非対称となります。
RSIの逆張り戦略が機能するのは、価格が平均回帰的な性質を示す、すなわち「行き過ぎ」がやがて修正されるという前提がある市場です。このようなレンジ相場や調整局面において、「買われすぎ」「売られすぎ」のシグナルは、価格の短期的な反転を捉える収益機会となり得ます [3, 6]。
しかし、ひとたび市場が強いトレンドを形成したり、あるいは外部からの大きな介入を受けたりすると、この前提は崩壊します。テクニカルルールの有効性が常に一定ではないことは、学術的にも示されています。例えば為替市場を対象としたある研究では、テクニカルルールの収益性が時間と共に変化し、特に中央銀行の市場介入があった期間と強く関連していることが発見されました。介入期間を除くと、ルールの予測能力は劇的に減少したのです [7]。これは、RSIのような指標の有効性が、市場の内部的なダイナミクスだけでなく、外部環境という明確な「レジーム」に強く依存することを示す強力な証拠です。この「特定のレジーム下でのみ有効」という非対称性を認識することが、RSIを使いこなす上での鍵となります。
Friction:データスヌーピングとトレンドという二重の摩擦
もしRSIが示す「行き過ぎ」が常に確実に修正されるのであれば、この戦略は安定した利益を生み出すはずです。しかし、現実にはその収益性を蝕む、複数の強力な「摩擦」が存在します。
一つは、統計的な摩擦である「データスヌーピング」です [5]。テクニカル分析の有効性を示す研究の多くは、無数のパラメータやルールの中から、過去のデータで最も成績が良かったものを後付けで選んでしまっている可能性があります。この「未来のデータを見て答え合わせをする」ような行為が、見せかけの優位性を生み出してしまうのです。この統計的な幻想こそが、バックテストでは機能するように見えたルールが、現実の市場では機能しない最大の原因の一つです。
もう一つは、より物理的な摩擦である「トレンド」そのものです。一度発生した強力なトレンドは、市場参加者の集団心理や資金の流れによって、自己増殖的な力を持つようになります。この大きな流れの前では、RSIが示す短期的な「買われすぎ」のシグナルは、何度も押し流されてしまいます。このトレンドという抗いがたい力が、逆張りトレーダーに連続的な損失をもたらす、最大の収益阻害要因(摩擦)として機能するのです。
総括
- RSIは、J・ウエルズ・ワイルダーJr.によって開発された、市場の勢いを測る古典的なオシレーター系指標です [1]。
- 「70以上で売り、30以下で買い」という逆張り戦略は、特定の市場(例:ロンドン株式市場)や条件下では、バイ・アンド・ホールド戦略を上回るリターンを生む可能性が示されています [3]。
- しかし、多くの実証研究は、取引コストやリスクを考慮すると、RSIを含むテクニカル分析の優位性が統計的に有意でなくなる可能性を指摘しています [2, 4]。
- テクニカル分析の研究そのものが「データスヌーピング」という統計的なバイアスに陥っている可能性があり、報告されているリターンが見せかけのものである危険性も指摘されています [5]。
- RSIの有効性は普遍的ではなく、市場のレジーム(例:中央銀行の介入の有無など)に強く依存するという非対称な性質を持っています [7]。
用語集
相対力指数(RSI) ある期間の価格変動における「値上がり幅」と「値下がり幅」を比較し、相場の勢いや過熱感を0から100の数値で示すオシレーター系のテクニカル指標。
オシレーター系指標 価格の「買われすぎ」や「売られすぎ」といった過熱感を判断するために用いられるテクニカル指標の総称。「振り子」のように一定の範囲で数値が変動する特徴を持つ。
逆張り 相場のトレンドとは反対の方向にポジションを取る投資戦略。価格が下落している時に買い、上昇している時に売る手法を指す。
順張り 相場のトレンドと同じ方向にポジションを取る投資戦略。価格が上昇している時に買い、下落している時に売る手法を指す。
平均回帰 市場価格が、その長期的な平均値から乖離した場合に、将来的に平均値の方向へ戻っていく傾向があるという性質。
レンジ相場 価格が特定の上限(レジスタンス)と下限(サポート)の間を行き来し、明確なトレンドが発生していない市場状態。
トレンド相場 価格が一定の方向に継続して上昇(上昇トレンド)または下落(下降トレンド)している市場状態。
データスヌーピング 研究者が多数の仮説を同じデータセットで検証する(データを覗き見る)ことで、本来は無関係であるにも関わらず、偶然によって統計的に有意な結果を見つけ出してしまう統計的なバイアス。データマイニングとも呼ばれる。
バイ・アンド・ホールド戦略 一度購入した資産を、市場の短期的な価格変動に関わらず、長期間保有し続ける投資戦略。
取引コスト 金融商品を売買する際に発生する費用の総称。売買手数料、スプレッド(売値と買値の差)、スリッページなどが含まれる。
参考文献一覧
[1] Wilder Jr, J. W. (1978). New concepts in technical trading systems. Trend Research.
※書籍です
[2] Park, C. H., & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis?. Journal of Economic Surveys, 21(4), 786-826.
https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x
[3] Chong, T. T. L., & Ng, W. K. (2008). Technical analysis and the London stock exchange: testing the MACD and RSI rules using the FT30. Applied Economics Letters, 15(14), 1111-1114.
https://doi.org/10.1080/13504850600993598
[4] Lento, C. (2008). A combined signal approach to technical analysis on the S&P 500. Financial Services Review, 17(1), 39-55.
https://doi.org/10.19030/jber.v6i8.2460
[5] Sullivan, R., Timmermann, A., & White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. The Journal of Finance, 54(5), 1647-1691.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00163
[6] Lo, A. W., Mamaysky, H., & Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation. The Journal of Finance, 55(4), 1705-1765.
https://ssrn.com/abstract=228099
[7] LeBaron, B. (1999). Technical trading rule profitability and foreign exchange intervention. Journal of International Economics, 49(1), 125-143.
https://doi.org/10.1016/S0022-1996(98)00061-0
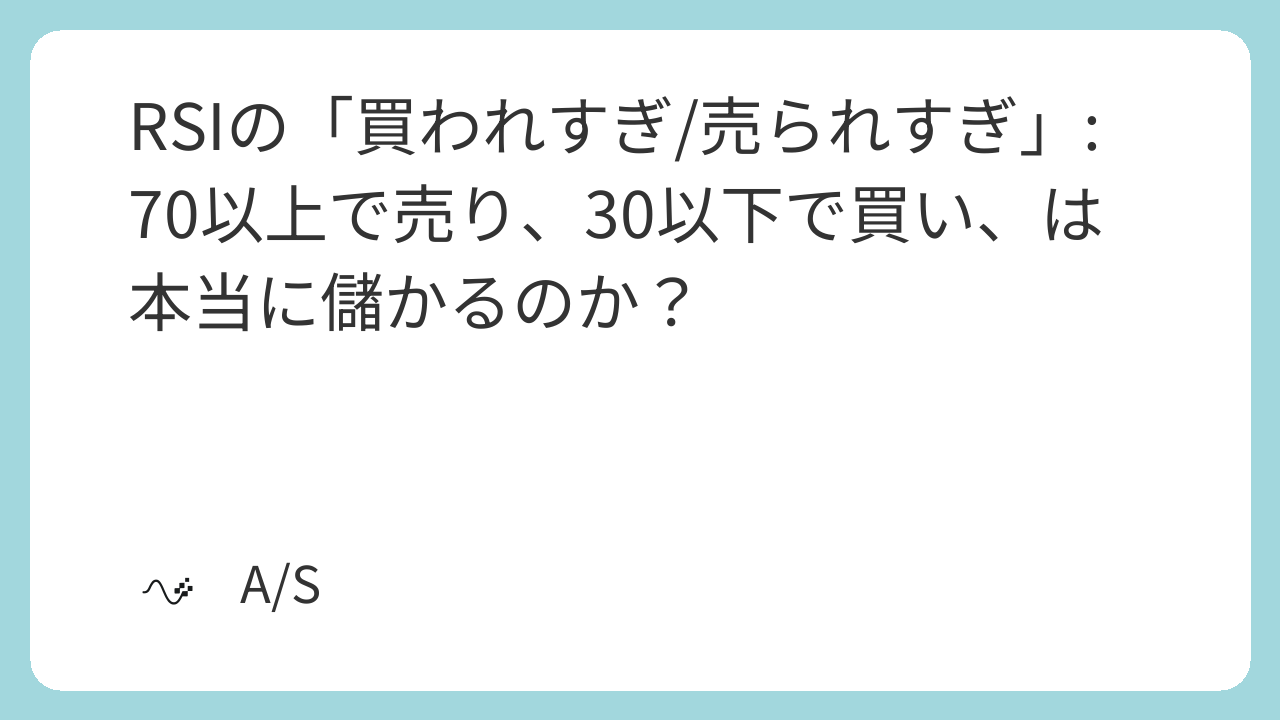
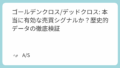
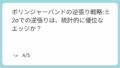
コメント