概論
前回の記事では、多くの金融時系列データ(特に価格)が、予測不可能な「ランダムウォーク」に近い非定常な性質を持つことを解説しました。そして、このような非定常なデータ同士を安易に分析すると、本来は何の関係もないはずなのに、見かけ上は強い相関があるように見えてしまう「見せかけの回帰」という深刻な罠に陥る危険性も指摘しました [1]。
では、予測不可能なランダムウォークに従う資産価格を、統計的に分析することは全く無意味なのでしょうか。――いいえ、そこに驚くべき例外が存在します。それが共和分(Cointegration)です。
共和分とは、複数の非定常な時系列データが、それぞれ単独ではランダムウォークのように予測不可能に動くにもかかわらず、それらの間に長期的に安定した「均衡関係」が存在するという、特別な統計的性質を指します。
これはしばしば、「酔っ払いと、その飼い犬」の比喩で説明されます。飼い主である酔っ払いの歩く道筋(株価A)は、千鳥足で予測不可能です。リードに繋がれた犬の歩く道筋(株価B)もまた、予測不可能です。しかし、犬はリードの長さの範囲内でしか飼い主から離れることができません。二者の間の距離(価格差、スプレッド)は、大きく開くことはあっても、いずれまた近づいていく、という安定した関係性が期待できます。この「価格差」が、予測可能な定常性を持つ場合、この二つの株価は「共和分の関係にある」と言えるのです。
この共和分の概念を数学的に定式化し、その検定手法を確立したのが、クライヴ・グレンジャーとロバート・エングルによる1987年の研究です [2]。この業績は、計量経済学に革命をもたらし、グレンジャーは後にノーベル経済学賞を受賞しました。
共和分の発見がもたらした最大のインパクトは、「個々の価格の動きは予測不可能でも、価格間の『関係性』は予測可能かもしれない」という、新たなエッジの可能性を示したことにあります。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:統計的裁定取引の基盤
ペアトレード戦略の理論的支柱(収益事例)
共和分の概念は、ペアトレードとして知られる、市場中立(マーケット・ニュートラル)な統計的裁定取引戦略の、強力な理論的支柱となります。
二つの銘柄が共和分の関係にあることが確認できれば、その価格差(スプレッド)は、長期的な平均値の周りを変動する定常的な時系列となります。トレーダーは、このスプレッドが何らかの理由で一時的に平均から大きく乖離した際に、将来的に平均へと回帰することに賭けることができます。具体的には、スプレッドが拡大した際には、割高になった銘柄を売り、割安になった銘柄を買い、スプレッドが縮小した際にポジションを解消して利益を得るのです。
ゲイトフ、ゲッツマン、ルーウェンホルストによる2006年の研究は、このようなペアトレード戦略の有効性を米国株式市場で実証した、最も有名な学術論文の一つです [3]。彼らの分析によれば、1962年から2002年までの期間において、シンプルなペアトレード戦略は、取引コストを考慮した上でも、年率11%程度の有意な超過リターンを生み出したと報告されています。
より高度な検定手法への発展
共和分を検定する手法は、エングルとグレンジャーによる2段階法だけでなく、その後も発展を続けています。例えば、セーレン・ヨハンセンが1991年に開発したヨハンセン検定は、3つ以上の変数が共和分の関係にあるかどうかを、より頑健に検定するための手法です [4]。これらの高度な統計ツールは、より複雑な資産間の均衡関係を発見し、より洗練された取引戦略を構築するための道を開いています。
短所、弱み、リスクについて:理論と現実のギャップ
アノマリーの減衰(損失事例)
ペアトレードは、理論的には魅力的な戦略ですが、その有効性が広く知られるにつれて、超過リターンは減衰していく傾向にあります。
ドゥとファフによる2010年の研究は、ゲイトフらの研究[3]を追試し、その後の期間(2003年〜2009年)のパフォーマンスを分析しました [5]。その結果、オリジナルの研究で報告されたほどの超過リターンは、この新しい期間ではほとんど消滅してしまっていたことが明らかになりました。彼らは、その原因として、市場の効率化、すなわち多くの投資家が同様の戦略を実行するようになったことによる競争の激化や、取引コストの上昇などを挙げています。
共和分関係の不安定性
過去のデータで確認された共和分の関係が、将来も永続する保証はどこにもありません。企業の合併・買収、新技術の登場による競争環境の激変、あるいは規制の変更といった構造的な変化が起これば、これまで安定していたペアの関係性は、あっけなく崩壊してしまいます。スプレッドが平均に回帰することを前提として構築されたポジションは、関係性が崩壊した場合には、無限大の損失をもたらす危険性さえはらんでいます。
最適な手法に関する議論
共和分は、ペアトレードのペアを選定するための唯一の手法ではありません。ハックとアファウボによる2015年の研究は、共和分に基づくペア選定と、より単純な、過去の価格差(距離)に基づくペア選定のパフォーマンスを比較しました [6]。その結果、取引コストを考慮すると、統計的に洗練された共和分アプローチが、必ずしも単純なアプローチよりも優れているとは限らないことを示唆しています。理論的な正しさが、必ずしも現実の取引における優位性に直結するわけではないのです。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、予測不可能なランダムウォークの中に、共和分という予測可能な「聖域」が存在し続けるのでしょうか。そして、その利用にはどのような非対称なリスクと摩擦が伴うのでしょうか。
Asymmetry:リターンの非対称性と平均回帰の非対称性
ペアトレード戦略は、そのリターンプロファイルが本質的に「非対称」であるという特徴を持っています。
この戦略は、スプレッドが平均から乖離した際に、その平均への回帰を狙うものです。多くの場合、スプレッドは比較的小さな範囲で変動するため、この戦略は「コツコツと小さな利益を積み上げる」という、安定したリターンを生み出す傾向があります。
しかし、その裏には、稀に起こる壊滅的な損失のリスクが潜んでいます。それは、二つの銘柄間の共和分関係そのものが、何らかの構造的変化によって恒久的に崩壊してしまうリスクです。この場合、開いたスプレッドは二度と平均に回帰せず、無限に拡大し続ける可能性があります。この「頻繁な小さな利益」と「稀な巨大な損失」というペイオフの非対称性は、ショート・プット戦略などにも見られる典型的なものです。
また、スプレッドが平均に回帰する「速度」も非対称である可能性があります。スプレッドが上方に乖離した場合と、下方に乖離した場合とで、平均に戻るまでの時間が異なるかもしれません。この平均回帰プロセスの非対称性を理解し、モデル化することが、より洗練されたペアトレード戦略の鍵となります。
Friction:「関係性の崩壊」という究極のリスクと摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、共和分に基づく戦略には、そのモデルの根幹に関わる、より深刻な「摩擦」が存在します。
モデルリスクという情報の摩擦
共和分の関係性は、神から与えられた法則ではなく、あくまで過去のデータから統計的に「推定」された仮説に過ぎません。この推定プロセスには、必ず誤差が伴います。また、過去に安定していた関係性が、未来も続くと保証するものは何もありません。
この「モデルは現実そのものではない」という情報の摩擦は、ペアトレードにおける最大のリスク源です。トレーダーは、共和分関係が崩壊するリスク、すなわちモデルリスクを常に負わなければなりません。ドゥとファフの研究が示したように、ペアトレードの超過リターンが時間と共に減衰していった背景には、市場の効率化だけでなく、このようなモデルの不安定性も影響している可能性があります [5]。
取引コストという物理的摩擦
ペアトレードは、二つの銘柄を同時に売買する必要があるため、取引コストに対して非常に敏感です。特に、スプレッドが開いた際に「空売り」する側の銘柄が、流動性の低い小型株であったり、品薄で貸株料が高騰していたりする場合、その取引コストは極めて高くなります。
ゲイトフらの研究では、取引コストを考慮してもなお利益が残ったとされていますが [3]、その後の研究では、この取引コストという物理的な摩擦が、ペアトレードの利益を大きく蝕む主要な要因であることが指摘されています [5]。理論上は魅力的なスプレッドの乖離が見られても、この摩擦によって、現実には利益の出ない取引となってしまうのです。
総括
・共和分とは、それぞれ単独では予測不可能な非定常な時系列データ(ランダムウォーク)間に存在する、長期的に安定した「均衡関係」のことです [2]。
・この概念は、二つの資産間の価格差(スプレッド)の平均回帰性を利用するペアトレード戦略の、強力な理論的支柱となります。
・歴史的には、シンプルなペアトレード戦略が、取引コストを考慮した上でも、有意な超過リターンを生み出していたことが報告されています [3]。
・しかし、その超過リターンは、市場の効率化や取引コストの増大により、近年では減衰する傾向にあります [5]。
・また、過去に観測された共和分関係が将来も継続するとは限らず、関係性が崩壊するモデルリスクという、非対称なリスクを常に内包しています。
用語集
共和分 (Cointegration) 複数の非定常な時系列データ間に存在する、長期的に安定した関係性。これらのデータを組み合わせる(線形結合する)と、定常的な時系列になる。
定常性 (Stationarity) 時系列データの統計的な性質(平均、分散など)が、時間をずらしても変化しない性質。平均回帰性を持つ。
非定常性 (Non-stationarity) 時系列データの統計的な性質が、時間と共に変化する性質。ランダムウォークが代表例。
単位根 (Unit Root) 非定常な時系列データが持つ統計的な特徴。過去のショックの影響が永続する。
見せかけの回帰 (Spurious Regression) 本来は無関係な二つの非定常な時系列データ間に、あたかも統計的に有意な相関関係が存在するかのように見えてしまう現象。
ペアトレード (Pairs Trading) 共和分の関係にある二つの銘柄の価格差(スプレッド)が、その平均値から乖離した際に、将来的に平均値へ回帰することに賭ける統計的裁定取引。
スプレッド (Spread) この文脈では、ペアトレードの対象となる二つの資産の価格差のこと。
平均回帰 (Mean Reversion) ある変数が、その長期的な平均値から乖離した場合に、将来的に平均値の方向へ戻っていく傾向があるという性質。
統計的裁定取引 資産間の統計的な関係性(共和分など)の歪みを利用して、市場の方向性には賭けずに、収益を狙う取引手法。
市場中立 (Market Neutral) 株式市場全体の上下の動き(ベータ)に対するエクスポージャーがゼロになるように構築されたポートフォリオ。ペアトレードは代表的な市場中立戦略。
参考文献一覧
[1] Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7
[2] Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
https://doi.org/10.2307/1913236
[3] Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs trading: Performance of a relative value arbitrage rule. The Review of Financial Studies, 19(3), 797-827.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhj020
[4] Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580.
https://doi.org/10.2307/2938278
[5] Do, B., & Faff, R. (2010). Does simple pairs trading still work?. Financial Analysts Journal, 66(4), 83-95.
https://doi.org/10.2469/faj.v66.n4.1
[6] Huck, N., & Afawubo, K. (2015). Pairs trading and selection methods: is cointegration superior?. Applied Economics, 47(6), 599-613.
https://doi.org/10.1080/00036846.2014.975417

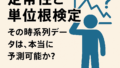

コメント