概論
「このトレードは、儲かる見込みがあるのか?」――全ての取引は、この素朴な問いから始まります。この「儲けの見込み」を、確率論を用いて客観的な数値として表現したものが期待値(Expected Value)です。期待値は、ギャンブル理論から現代ファイナンスまで、あらゆる不確実な状況下での合理的な意思決定の根幹をなす、極めて重要な概念です。
期待値の計算は、起こりうる全ての結果について、「その結果が得られる確率」と「その結果によって得られる価値(損益)」を掛け合わせ、それらを全て足し合わせることで求められます。
例えば、サイコロを1回振り、出た目×100円がもらえるゲーム(参加費400円)があったとします。各目が出る確率は6分の1、得られる価値は100円から600円です。このゲームの期待値は、(1/6)×100 + (1/6)×200 + … + (1/6)×600 = 350円となります。参加費400円を支払うと、期待値はマイナス50円(350円 – 400円)です。したがって、合理的な判断としては、このゲームに参加すべきではない、ということになります。
この単純明快な概念は、しかし、人間の意思決定や複雑な金融市場を分析する上で、数々の洗練と挑戦を経てきました。まず、フォン・ノイマンとモルゲンシュテルンによるゲーム理論の基礎研究は、人々が最大化しようとするのは金額そのものではなく、その金額から得られる「効用(満足度)」であるとする期待効用理論を提唱しました [1]。
さらに、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによるプロスペクト理論は、人々が期待効用理論の前提さえも満たさない、体系的に非合理な意思決定を行うことを明らかにしました [2]。彼らは、人間が確率を主観的に歪めて認識し(低い確率を過大評価する)、利益よりも損失を重く感じる(損失回避)といった、複雑な心理を持つことを示したのです。
このように、期待値という概念は、その単純な計算式の裏に、人間の合理性と非合理性が交錯する、深い問いを投げかけています。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について:全ての合理的な意思決定の羅針盤
利益例:体系的な戦略の理論的支柱
期待値の概念は、全ての体系的な投資戦略の根幹をなす「羅針盤」として機能します。例えば、これまで解説してきたバリューファクターやモメンタムファクターといった戦略は、本質的に「バリュー株の期待リターンはグロース株の期待リターンを上回る」「過去の勝者株の期待リターンは敗者株の期待リターンを上回る」という仮説に基づいています。期待値という共通の言語があるからこそ、異なる戦略の優劣を比較し、ポートフォリオを構築することが可能になるのです。
また、期待値は、市場全体の大きな謎を解き明かすための分析ツールでもあります。メーラとプレスコットによる1985年の研究は、株式市場の歴史的なリターン(期待値)が、伝統的な経済モデルで合理的に説明できる範囲を遥かに超えて高いことを示し、「エクイティ・プレミアム・パズル」として知られる一大論争を巻き起こしました [3]。
短所、弱み、リスクについて:計算できない「儲けの見込み」
期待値は理論的には強力ですが、現実の金融市場でそれを利用しようとすると、深刻な、時には乗り越えられない困難に直面します。
損失事例1:期待値の「推定誤差」という罠
サイコロの出る確率が6分の1であることは誰もが知っていますが、来月の特定の株式のリターンとその確率を、神ならぬ人間が正確に知ることは不可能です。我々にできるのは、過去のデータからそれを「推定」することだけです。
ロバート・マートンによる1980年の古典的な研究は、この期待リターンの推定がいかに困難であるかを統計的に示しました [4]。株式のリターンはノイズが非常に大きいため、たとえ100年分のデータを使ったとしても、その期待リターンの推定値には、極めて大きな誤差(標準誤差)が含まれてしまうのです。もし、計算の基礎となる期待値の推定が間違っていれば、プラスだと信じていた戦略が、実際にはマイナスだったという悲劇的な結果を招きます。
損失事例2:「最適ポートフォリオ」の失敗
この期待値の推定誤差の問題は、現代ポートフォリオ理論に基づいた「最適ポートフォリオ」運用が、しばしば現実に機能しない原因となります。
デミゲル、ガーラッピ、ウパルによる2009年の影響力の大きい研究は、この問題を実証的に明らかにしました [5]。彼らは、期待リターンや共分散を推定して構築される14種類の洗練された最適ポートフォリオと、単に資産に均等に投資するだけの*「1/Nポートフォリオ」(期待値の計算を完全に放棄した戦略)のパフォーマンスを比較しました。その結果、多くの現実的なデータセットにおいて、推定誤差の影響により、洗練された最適ポートフォリオのほとんどが、単純な1/Nポートフォリオに勝てなかったのです。これは、不正確な期待値に基づいて複雑な計算を行うことは、何もしないことよりも悪い結果をもたらしうる、という強力な証拠です。
非対称性と摩擦の視点から
なぜ、期待値という合理的な概念が、現実の市場ではこれほどまでに複雑な問題を引き起こすのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性と摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:客観的確率と主観的確率の非対称性
期待値の計算における最大の非対称性は、サイコロの目のように客観的に定まる「数学的な確率」と、人間が頭の中で認識する「主観的な確率」との間の深刻な乖離です。
プロスペクト理論が明らかにしたように、人間の意思決定は、この非対称な確率認識に強く支配されています [2]。例えば、発生確率1%という客観的な数値を、我々は単なる1%とは認識せず、それ以上に「起こるかもしれない」と過大評価してしまいます(確率加重関数)。また、利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛を2倍以上強く感じる(損失回避)という、利得と損失に対する感情の非対称性も持っています。
この人間の認知における構造的な非対称性こそが、市場に非効率性が生まれる根源です。客観的な期待値がマイナスであるにも関わらず、宝くじのような一攫千金の可能性(低い確率)に人々が群がったり、合理的に考えれば損切りすべき場面で、損失の苦痛から逃れるためにナンピン買いを続けたりする。これらの行動はすべて、この非対称な心理から説明できます。
このアノマリーを利用した収益機会とは、市場の大多数がこの主観的な期待値に支配されている中で、客観的な期待値に基づいた規律ある意思決定を貫くことで生まれるのです。
Friction:「推定誤差」という乗り越えられない摩擦
手数料やスプレッドのような基本的な摩擦に加え、期待値に基づく戦略が直面する、より本質的で克服困難な摩擦が存在します。
推定誤差という根源的な摩擦
金融市場における期待値計算の最大の弱点は、その計算の基礎となる「真の確率分布」を誰も知らないという事実です。我々が唯一頼れるのは、ノイズに満ちた過去のデータだけです。ロバート・マートンが示したように、過去のデータから将来の期待リターンを推定しようとする試みは、極めて大きな「推定誤差」という摩擦から逃れることができません [4]。
この推定誤差は、単なる技術的な問題ではなく、乗り越えることのほぼ不可能な、根源的な壁として機能します。バックテストでプラスの期待値を示した戦略が、実は過去のデータにおける単なる偶然のノイズを拾っただけであり、その真の期待値はマイナスであった、という事態は常に起こり得ます。
この摩擦の深刻さは、デミゲルらの研究が示した「最適ポートフォリオの失敗」によって浮き彫りになります [5]。期待値の推定という、最も重要でありながら最も不確実な作業を必要とする精緻なモデルが、その計算を完全に放棄した単純なモデルに敗北するという事実は、期待値の計算に内在する摩擦がいかに大きいかを物語っています。この摩擦を理解せず、計算上の期待値を盲信することは、破滅への近道となりかねないのです。
総括
・期待値は、確率と損益を掛け合わせて計算される「儲けの見込み」であり、全ての合理的な取引の基礎となる概念です。
・しかし、人間は客観的な期待値ではなく、損失回避や低い確率の過大評価といった、非対称な心理に基づいた「主観的な期待値」で行動する傾向があります [2].
・期待値に基づく戦略は、この人間の非合理性を利用することで収益機会となり得ますが、その一方で、金融市場における期待値の正確な推定は、統計的に極めて困難であるという大きな問題を抱えています [4]。
・この「推定誤差」という摩擦は非常に深刻であり、不正確な期待値に基づいて構築された精緻な最適ポートフォリオが、期待値の計算を放棄した単純なポートフォリオに負けてしまうという逆説的な結果さえ生み出します [5]。
用語集
期待値 (Expected Value) ある試行を行った際に、結果として得られる数値の平均値。「結果×その確率」を全て足し合わせることで計算される、合理的な意思決定の基礎。
期待効用理論 (Expected Utility Theory) 人々は金額の期待値を最大化するのではなく、その金額から得られる「効用(満足度)」の期待値を最大化するように行動するという理論。
プロスペクト理論 (Prospect Theory) 期待効用理論さえも成り立たない、現実の人間の非合理的な意思決定を説明する理論。損失回避や確率の主観的な歪みなどを特徴とする。
損失回避 (Loss Aversion) 同じ金額であれば、利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方を精神的に重く受け止めてしまうという人間の心理的傾向。
エクイティ・プレミアム (Equity Premium) 株式に投資することで期待されるリターンが、債券などの安全資産のリターンをどれだけ上回っているかを示す差。
推定誤差 (Estimation Error) 過去のデータなど、限られたサンプルから母集団の真のパラメータ(期待値など)を推定する際に生じる、避けられない誤差のこと。
標準誤差 (Standard Error) 推定誤差の大きさを測るための統計的な指標。
1/Nポートフォリオ (1/N Portfolio) ポートフォリオに組み入れるN個の資産に、均等に(N分の1ずつ)資金を配分するという、非常にシンプルな分散投資戦略。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
バックテスト ある投資戦略が、過去の市場データを用いてシミュレーションした場合に、どのようなパフォーマンスを示したかを検証すること。
参考文献一覧
[1] von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.
※書籍です
[2] Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-291.
https://doi.org/10.2307/1914185
[3] Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.
https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90061-3
[4] Merton, R. C. (1980). On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation. Journal of Financial Economics, 8(4), 323-361.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90007-0
[5] DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?. The Review of Financial Studies, 22(5), 1915-1953.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075
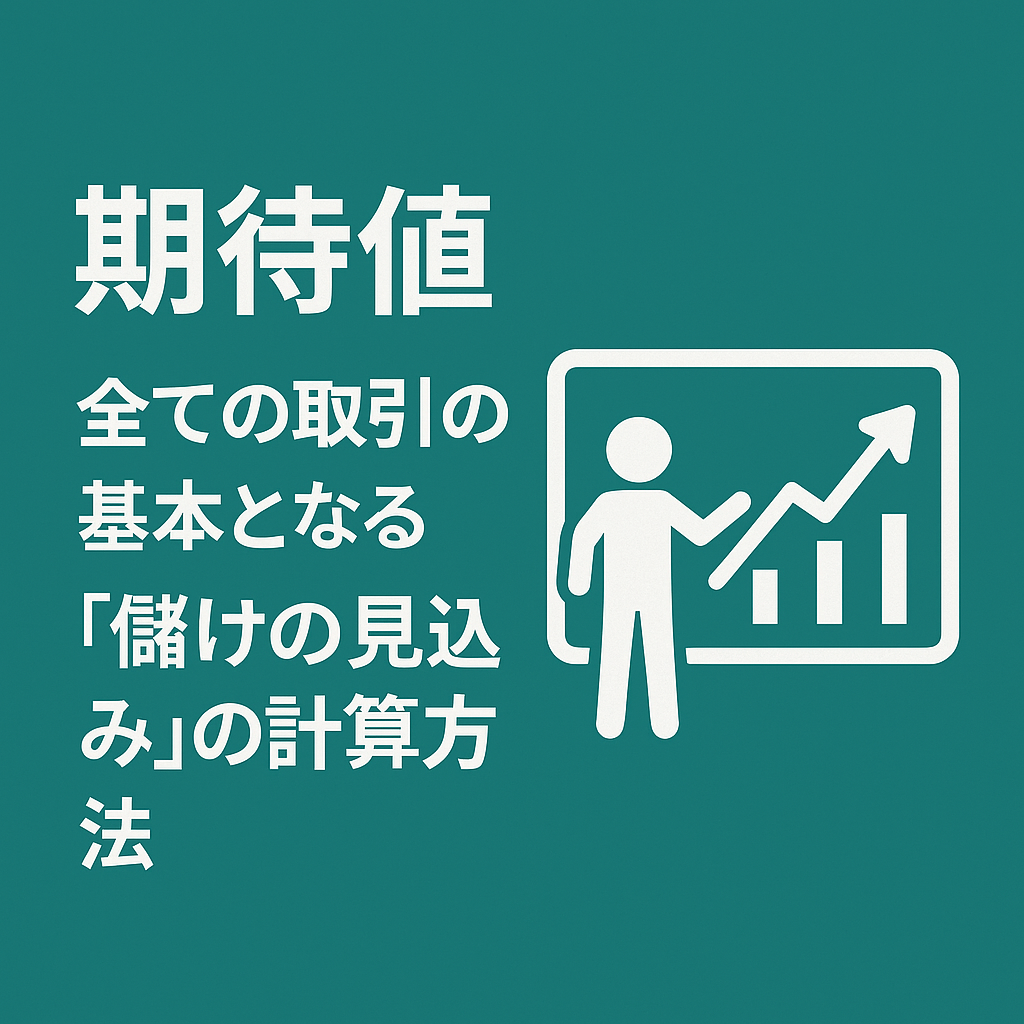
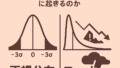
コメント