概論
今日のデリバティブ市場の繁栄を語る上で、決して避けては通れない金字塔的な理論が存在します。それが、1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによって発表された、ブラック=ショールズ・モデルです [1]。同時期にロバート・マートンもまた、この理論の発展に不可欠な貢献をしました [2]。彼らの功績は、それまでトレーダーの経験と勘に大きく依存していたオプションの価格決定問題に、初めて数学的な「正解」を与えたという点で、金融工学における革命でした。この功績により、ショールズとマートンは1997年にノーベル経済学賞を受賞しています(ブラックは受賞前に逝去)。
このモデルが画期的であったのは、その中心的なアイデアである「動的デルタヘッジ」と「無裁定理論」にあります。ブラック=ショールズ・モデルは、オプションと原資産である株式を特定の比率で組み合わせ、その比率を常に調整し続けることで、価格変動リスクが完全に相殺された「リスクフリー」のポートフォリオを組成できることを数学的に示しました。そして、市場に裁定機会(リスクなく利益を得られる機会)が存在しないのであれば、このポートフォリオが生むリターンは、安全資産である国債などと同じ(リスクフリー金利)になるはずです。この関係性から逆算することで、オプションの理論的な価格を一つの数式で導き出すことができるのです。
この公式は、主に5つのパラメータからオプション価格を算出します。すなわち、原資産価格、権利行使価格、満期までの期間、リスクフリー金利、そして原資産の価格変動の激しさを示すボラティリティです。このうち、将来のボラティリティだけが唯一、直接観測することのできない変数であり、この点が後にインプライド・ボラティリティという重要な概念を生み出すことになります。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所:金融工学に革命をもたらした「公式」
ブラック=ショールズ・モデルがもたらした最大の功績は、オプションという複雑な金融商品に、客観的で標準化された価格評価の尺度を提供したことです。これにより、市場参加者は共通の言語でオプションの価値を議論できるようになり、デリバティブ市場の流動性と取引量は爆発的に増大しました。
このモデルの最も永続的な遺産の一つが、「インプライド・ボラティリティ」という概念です。モデルの公式を逆算し、市場で実際に取引されているオプション価格から、市場参加者が将来のボラティリティをどの程度と織り込んでいるかを算出できるようになったのです。これは、市場のセンチメントを測る上で、今日でも不可欠な指標となっています。
モデルが発表された当初、その有効性は実証研究によっても確認されました。シカゴ・オプション取引所(CBOE)の初期のデータを分析した研究では、ブラック=ショールズ・モデルが市場価格から乖離したオプション(割安または割高なオプション)を特定する上で有効であり、裁定機会が存在したことが示唆されています [3]。これは、モデルをいち早く理解し、利用したトレーダーが、市場の非効率性から利益を得られた可能性を示しています。
短所:理想的世界と現実の乖離
その数学的なエレガンスと市場への絶大な影響力にもかかわらず、ブラック=ショールズ・モデルは、その根底にあるいくつかの非現実的な仮定のために、深刻な限界を抱えています。
このモデルは、例えば、取引コストや税金が存在しない、ボラティリティや金利は常に一定である、そして株価の変動は連続的で、正規分布に従うといった、極めて理想化された世界を前提としています [1, 2]。しかし、現実の市場はこれらの仮定を満たしません。
モデルの不完全性を最も象徴的に示す現象が、「ボラティリティ・スマイル(あるいはスキュー)」です。もしモデルが完璧に正しければ、同じ原資産のオプションは、権利行使価格が異なっていても、全て同じインプライド・ボラティリティを持つはずです。しかし、現実の市場では、権利行使価格によってインプライド・ボラティリティが異なるという歪みが恒常的に観測されています。特に、1987年のブラックマンデー以降、株価指数オプション市場では、暴落を警戒する需要から、アウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションのインプライド・ボラティリティが体系的に高くなる「ボラティリティ・スキュー」が定着しました [4]。これは、モデルが現実市場の「テールリスク(暴落リスク)」を適切に評価できていないことの動かぬ証拠です。
興味深いことに、モデルの限界の一部は、その創始者たち自身によっても早くから認識されていました。例えば、ロバート・マートンは、株価が時に連続的ではなく、ジャンプ(跳躍)するように不連続な動きを見せる現実をモデルに組み込むため、ブラック=ショールズ・モデルを拡張した「ジャンプ拡散モデル」を提唱しています [5]。これは、モデルが内包する理想と現実のギャップを埋めようとする、重要な理論的発展の一つです。
非対称性と摩擦の視点から
ブラック=ショールズ・モデルは、金融市場における「非対称性」を価格評価するための画期的なツールであると同時に、その理論が前提とする「摩擦のない」理想世界と、現実の市場とのギャップを浮き彫りにする存在でもあります。
Asymmetry:非対称な契約を評価する理論
オプション契約の本質は、その「非対称な」損益構造にあります。コールオプションの買い手は、損失が支払ったプレミアムに限定される一方で、利益は理論上無限大です。ブラック=ショールズ・モデルが成し遂げた核心的な功績は、この極めて非対称な金融商品の価値を、無裁定という合理的な原則に基づいて、数学的に評価可能にした点にあります。
しかし皮肉なことに、このモデルは、原資産である株価の変動が左右対称な正規分布に従うと仮定しています。現実の市場は、この仮定が誤りであることを「ボラティリティ・スキュー」という現象を通じて示しています [4]。市場は、理論モデルが想定する以上に、緩やかな上昇よりも突発的な暴落という「非対称な」リスクを強く警戒しているのです。モデルは非対称な契約を評価するために生まれましたが、その根底にある市場の非対称性を完全には織り込めていない、という矛盾を抱えているのです。
Friction:理想世界を阻む数々の摩擦
ブラック=ショールズ・モデルの美しい数式は、取引コストや市場の制約が一切存在しない、完全に「摩擦のない(frictionless)」世界を前提としています。現実の市場に存在する様々な摩擦こそが、モデルの理論価格と実際の市場価格との間に乖離を生む主要な原因です。
最も重要な摩擦は、モデルの理論的支柱である「動的デルタヘッジ」の実現を困難にする「取引コストの摩擦」です。理論上、リスクフリーのポートフォリオを維持するためには、ポジションを「連続的に」調整し続ける必要があります。しかし、現実には、売買の都度、売買スプレッドや手数料といった取引コストが発生するため、連続的なリバランスは不可能です。この摩擦は、理論通りの完璧なヘッジを阻害し、モデルの前提を根底から揺るがします。
また、モデルが前提とする「価格の連続性」も、現実には存在しない理想です。市場は時に、重要なニュースなどをきっかけに、価格が「ジャンプ」するように不連続な動きを見せます。この「ジャンプという摩擦」は、連続的なヘッジ戦略に大きな誤差を生じさせ、モデルが想定しない巨大な損失をもたらす可能性があります。この摩擦を乗り越えるため、マートンは株価のジャンプをモデルに組み込む理論的な拡張を試みています [5]。
総括
- ブラック=ショールズ・モデルは、1973年に発表された、オプションの理論価格を数学的に導出する画期的な公式です [1, 2]。
- その核心は、オプションと原資産を組み合わせてリスクフリーのポートフォリオを組成できるという「無裁定理論」と「動的デルタヘッジ」の概念にあります。
- このモデルは、標準化された価格評価尺度を提供したことでデリバティブ市場の発展を爆発的に加速させ、初期の実証研究ではその有効性も示唆されました [3]。
- 最大の弱点は、ボラティリティが一定である、株価リターンが正規分布に従うといった、多くの非現実的な仮定に基づいている点です。
- モデルの仮定と現実との乖離は、権利行使価格によってインプライド・ボラティリティが異なる「ボラティリティ・スマイル/スキュー」という現象に最も顕著に現れます [4]。
- モデルが無視する価格の不連続性(ジャンプ)といった「摩擦」を克服するため、ジャンプ拡散モデルのような拡張理論も開発されています [5]。
用語集
ブラック=ショールズ・モデル フィッシャー・ブラック、マイロン・ショールズ、ロバート・マートンによって構築された、オプションの理論価格を算出するための数学モデル。1997年のノーベル経済学賞の受賞理由となった。
オプション 特定の資産(原資産)を、将来の特定の期日までに、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で「買う権利(コール)」または「売る権利(プット)」のこと。
デルタヘッジ オプションの価格変動リスクを、原資産を売買することで相殺(ヘッジ)する手法。モデルでは、このヘッジを連続的に行うことでリスクを完全に除去できると仮定する。
無裁定理論 市場にリスクなく利益を得られる機会(裁定機会)は存在しないという仮定に基づき、資産価格を決定する理論。ブラック=ショールズ・モデルの理論的支柱。
インプライド・ボラティリティ (IV) オプションの市場価格を基に、ブラック=ショールズ・モデルを逆算して求められる、市場が予測する将来の変動率。
ボラティリティ・スマイル/スキュー 横軸に権利行使価格、縦軸にインプライド・ボラティリティを取った際に、グラフが笑顔(スマイル)や片側に歪んだ(スキュー)形になる現象。モデルの不完全性を示す。
正規分布 統計学で最も広く用いられる確率分布。平均値を中心に左右対称の釣鐘状の形をしているが、現実の金融市場に見られる極端な価格変動(テールリスク)を十分に表現できない。
リスクフリー金利 国債など、理論上リスクがゼロの安全資産から得られる金利。オプション価格の計算に用いられる。
権利行使価格 オプションの買い手が、原資産を売買する権利を行使できる価格。
ジャンプ拡散モデル 通常の連続的な価格変動に加えて、突発的で不連続な価格の「ジャンプ」を許容するよう、ブラック=ショールズ・モデルを拡張したモデル。
参考文献一覧
[1] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
https://www.jstor.org/stable/1831029
[2] Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141-183.
https://doi.org/10.2307/3003143
[3] Galai, D. (1977). Tests of market efficiency of the Chicago Board Options Exchange. The Journal of Business, 50(2), 167-197.
https://www.jstor.org/stable/2352152
[4] Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. The Journal of Finance, 49(3), 771-818.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00079.x
[5] Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90022-2
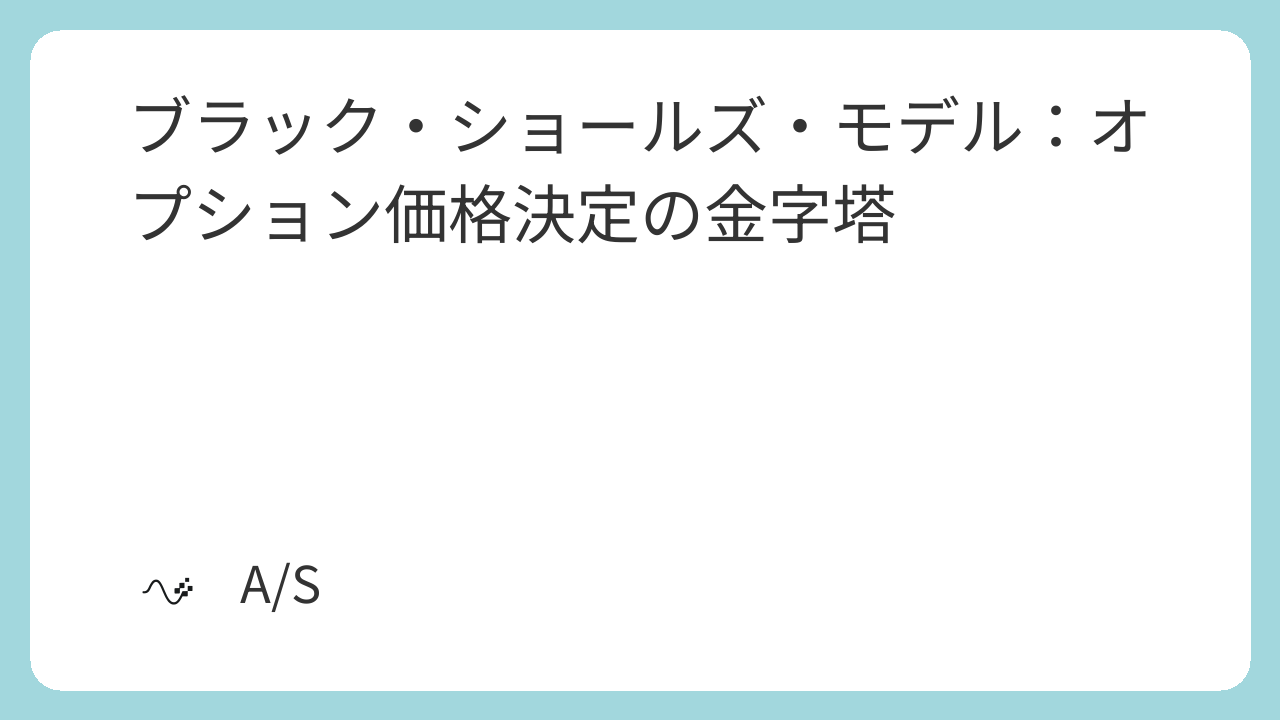
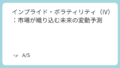
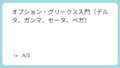
コメント