概論
前回の記事で解説したブラック=ショールズ・モデルは、オプションの理論価格を計算するための、エレガントで強力な公式です [1]。このモデルは、原資産の将来のボラティリティ(価格変動の激しさ)が、オプションの満期まで一定であるという、重要な仮定に基づいています。もしこの仮定が正しければ、同じ原資産を対象とするオプションは、権利行使価格や満期日が異なっていても、そこから逆算されるインプライド・ボラティリティ(IV)は全て同じ値になるはずでした。
しかし、現実のオプション市場を観測すると、この理論上の予測は明確に否定されます。実際に取引されているオプション価格からインプライド・ボラティリティを計算し、横軸に権利行使価格、縦軸にIVをとってプロットすると、そのグラフは水平な直線にはならず、歪んだ曲線を描くのです。この現象こそが、ボラティリティ・スマイル、あるいはボラティリティ・スキューと呼ばれる、市場の歪みです。
具体的には、権利行使価格が現在の価格から離れたアウト・オブ・ザ・マネー(OTM)のオプションのIVが、アット・ザ・マネー(ATM)のオプションのIVよりも高くなる傾向があり、グラフがまるで微笑んでいるかのように見えることから「ボラティリティ・スマイル」と呼ばれます。特に、株価指数オプション市場で顕著に見られるのが「ボラティリティ・スキュー」で、これは価格下落時に利益が出るプットオプションのIVが、価格上昇時に利益が出るコールオプションのIVよりも体系的に高くなる、片側に歪んだ(skewed)形状を指します。
この現象は、特に1987年のブラックマンデー(世界的な株価大暴落)以降、市場の恒久的な特徴として定着しました [2]。ボラティリティ・スマイルとスキューの存在は、ブラック=ショールズ・モデルが前提とする理想的な世界と、現実の市場との間に存在する深刻なギャップを、これ以上ないほど明確に示しているのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
ボラティリティ・スマイルやスキューは、それ自体が直接的な取引手法ではありません。しかし、この市場の「歪み」を理解し分析することは、リスクをより深く把握し、より精緻な投資戦略を構築するための、強力な洞察を与えてくれます。
長所:市場心理と確率分布の可視化
ボラティリティ・スマイルが持つ最大の価値は、それが市場参加者の将来に対する期待や恐怖を、極めて雄弁に物語っている点にあります。特に株価指数オプションに見られるボラティリティ・スキューの傾きは、市場が将来の株価暴落をどれだけ強く警戒しているかを測る、直接的な指標となります。これは、市場の「クラッシュ恐怖症(crash-o-phobia)」を可視化したものと言えるでしょう。
また、この現象は、ブラック=ショールズ・モデルの限界を乗り越えるための、より現実に即した新たな理論モデルの開発を促しました。例えば、ボラティリティが一定ではなく、それ自体が確率的に変動するという「確率的ボラティリティ・モデル」は、ボラティリティ・スマイルやスキューを理論的に再現することが可能です [3]。スマイルの発見は、金融工学をより現実に近い世界へと導く、重要なきっかけとなったのです。
さらに、スマイルカーブ全体が持つ情報を分析することで、市場が織り込む将来の株価の「リスク中立確率分布」を推定することも可能です。これは、ブラック=ショールズ・モデルが前提とする対称的な正規分布とは異なり、左側に長い裾野を持つ(=暴落の確率がより高い)、より現実的な確率分布を示します。この情報を読み解くことは、市場のコンセンサスを理解する上で極めて有用です [4]。
短所:モデルの複雑化と解釈の難しさ
ボラティリティ・スマイルの存在は、オプション取引の世界をより複雑で難解なものにしました。ブラック=ショールズ・モデルのシンプルな世界では、ボラティリティという一つの数値を予測すればよかったのに対し、現実には、権利行使価格ごと、満期ごとに異なる無数のIVが存在する「ボラティリティ曲面」と向き合わなければなりません。
この複雑性は、オプションの価格評価やヘッジングを格段に難しくします。どのIVを「正しい」ボラティリティとして参照すべきかという明確な答えはなく、誤ったIVを用いてヘッジ比率(デルタなど)を計算すれば、意図しない大きな損失を被るリスクがあります。
また、スマイルが示す情報が、将来の「真の確率」を直接反映しているのか、それとも単に投資家の「リスク回避度(リスクプレミアム)」を反映しているだけなのかを区別することは、極めて困難です。ある研究によれば、オプションの価格(ひいてはIV)は、原資産である株式の実際の収益分布の歪み(スキューネス)と関連していることが示されており、スマイルが単なる幻想ではなく、実体経済の情報を反映していることが示唆されています [5]。しかし、この二つの要素を完全に分離して解釈することは、現代の金融経済学における最も重要な未解決問題の一つであり続けています。
非対称性と摩擦の視点から
ボラティリティ・スマイルとスキューは、市場に内在する「非対称性」をこれ以上ないほど雄弁に物語る現象です。そしてそれは、理論と現実の間に存在する「摩擦」によって生み出されています。
Asymmetry:市場の非対称なリスク認識の顕在化
ボラティリティ・スキューは、市場参加者のリスク認識が本質的に「非対称」であることの直接的な証拠です。ブラック=ショールズ・モデルが前提とする正規分布の世界では、株価が50%暴落する確率と、100%高騰する確率は、極めて低いという点では同じように扱われます。しかし、現実の投資家は、リターンの分布が対称であるとは考えていません。特に1987年のブラックマンデーを経験して以降、市場は緩やかな上昇よりも、突発的で破壊的な暴落(テールリスク)をはるかに強く警戒するようになりました [2]。
この「クラッシュへの恐怖」という非対称な心理が、ダウンサイドをプロテクションするプットオプションへの高い需要を生み出し、そのインプライド・ボラティリティを押し上げています。ボラティリティ・スキューとは、まさしくこの市場の非対称な恐怖感を、オプション価格を通じて可視化したものなのです。この歪みは単なるノイズではなく、原資産である株式が持つ収益分布の歪みとも関連しており、市場の深い情報を内包していることが示唆されています [5]。
Friction:理想的なモデルと現実との摩擦
ボラティリティ・スマイルが存在する根源的な理由は、ブラック=ショールズ・モデルという、美しくも非現実的な「摩擦のない」理論と、複雑で摩擦に満ちた現実の市場との間に存在するギャップ、すなわち「モデルの摩擦」にあります。
ブラック=ショールズ・モデルは、ボラティリティが常に一定であるという、現実にはあり得ない仮定を置いています [1]。現実のボラティリティは、市場のセンチメントやニュースによって常に変動しています。このモデルの単純化された世界観を、複雑な現実のオプション価格に無理やり当てはめようとすると、その歪みを吸収するために、権利行使価格ごとにインプライド・ボラティリティの値を変えざるを得なくなります。ボラティリティ・スマイルとは、このモデルの摩擦が、目に見える形となって現れたものなのです。
この摩擦を低減するため、研究者たちは、ボラティリティ自体が確率的に変動することを許容する、より現実に即したモデル(確率的ボラティリティ・モデルなど)を開発してきました [3]。これらの高度なモデルは、スマイルやスキューの形状をより良く説明することができますが、それはモデルの複雑性を増大させるという代償を伴います。理論と現実の間の摩擦を乗り越える試みは、金融工学における永遠の課題であり続けているのです。
総括
- ボラティリティ・スマイルとスキューは、同じ原資産のオプションでも権利行使価格によってインプライド・ボラティリティ(IV)が異なる現象であり、ボラティリティが一定だと仮定するブラック=ショールズ・モデル [1] が現実と乖離していることを示す直接的な証拠です。
- 特に株価指数オプション市場では、価格下落時に価値を持つプットオプションのIVが割高になる「ボラティリティ・スキュー」が、1987年の株価暴落以降、恒常的な特徴となっています [2]。
- このスキューは、市場参加者が理論モデルの想定以上に、将来の暴落という「非対称な」リスクを強く警戒していることの現れです。
- この現象を説明するため、ボラティリティ自体が確率的に変動することをモデルに組み込んだ、確率的ボラティリティ・モデルなどが開発されました [3]。
- ボラティリティ・スマイルが示す歪みは、市場が織り込む将来の確率分布を推定するための貴重な情報源であり [4]、原資産のリスク特性とも関連していることが示唆されています [5]。
用語集
ボラティリティ・スマイル/スキュー 横軸に権利行使価格、縦軸にインプライド・ボラティリティを取った際に、グラフが笑顔(スマイル)や片側に歪んだ(スキュー)形になる現象。
インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility, IV) オプションの市場価格を基に、オプション価格モデルを逆算して求められる、市場が予測する将来の変動率。
ブラック=ショールズ・モデル オプションの理論価格を計算するための数学的なモデル。ボラティリティが一定であるなど、いくつかの理想的な仮定に基づいている。
権利行使価格 オプションの買い手が、原資産を売買する権利を行使できる価格。ストライクプライスとも呼ばれる。
アウト・オブ・ザ・マネー (Out-of-the-Money, OTM) オプション取引において、現時点で権利を行使すると損失が出る状態のこと。
アット・ザ・マネー (At-the-Money, ATM) オプション取引において、原資産価格と権利行使価格がほぼ等しい状態のこと。
確率的ボラティリティ・モデル ボラティリティが一定ではなく、時間と共に確率的に変動すると仮定する、より現実に即したオプション価格モデル。
リスク中立確率 デリバティブ価格を評価する際に用いられる、仮想的な確率測度。投資家のリスク選好を捨象した世界での確率分布を指す。
テールリスク 確率分布の裾野(テール)で発生する、発生確率は極めて低いが、一度発生すると壊滅的な損失をもたらすリスク。
プットオプション 原資産を将来の特定の時点に特定の価格で「売る権利」。価格下落に対する保険として機能する。
参考文献一覧
[1] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
https://www.jstor.org/stable/1831029
[2] Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. The Journal of Finance, 49(3), 771-818.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb00079.x
[3] Heston, S. L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility. The Review of Financial Studies, 6(2), 327-343.
https://doi.org/10.1093/rfs/6.2.327
[4] Bakshi, G., Kapadia, N., & Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. The Review of Financial Studies, 16(1), 101-143.
https://www.jstor.org/stable/1262727
[5] Figlewski, S. (2009). Estimating the implied risk neutral density for the U.S. market portfolio. In The risks of financial institutions (pp. 639-680). University of Chicago Press.
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549498.003.0015
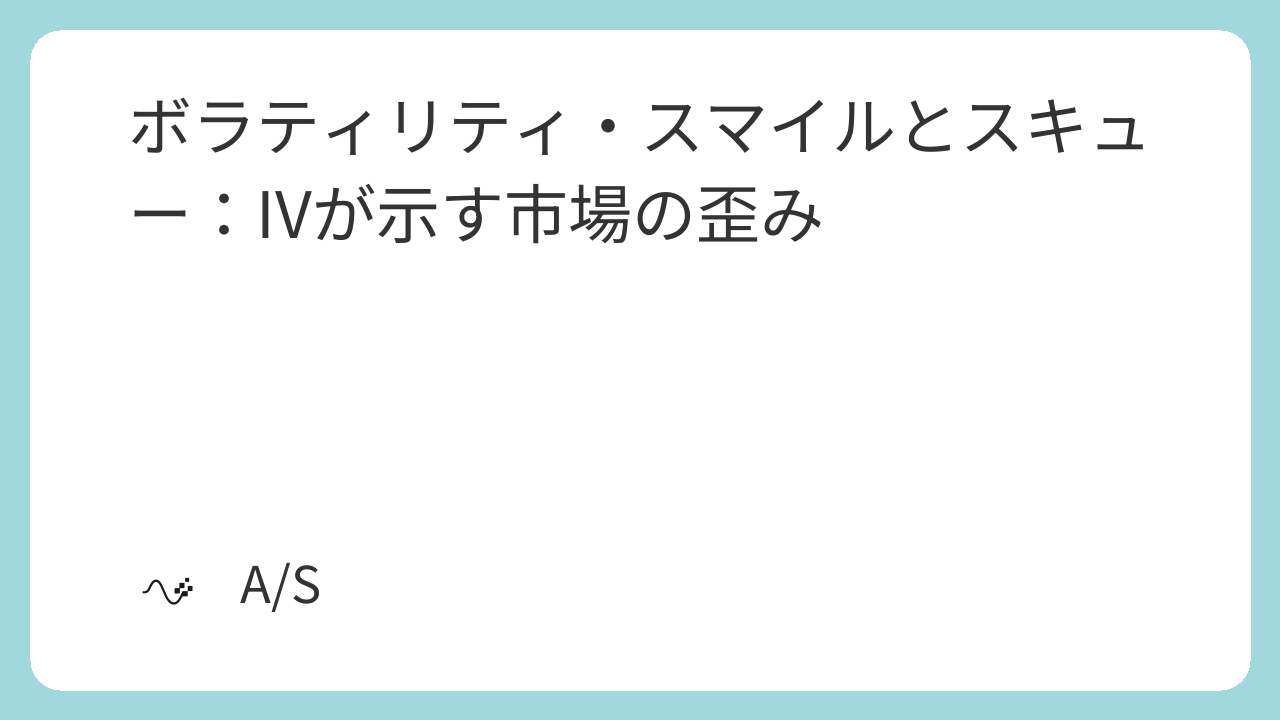
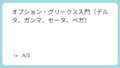
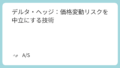
コメント