概論
トレードを行う際、私たちは画面に表示されている価格で売買できると期待します。しかし、特に成行注文を発注した時、実際に取引が成立した価格(約定価格)が、注文を出した瞬間の価格と異なっていることがあります。この、注文価格と約定価格の間に生じる不利な方向への「ズレ」が、スリッページです。
スリッページは、取引における目に見えにくい、しかし無視できないコストの一種です。この現象は、単なる取引システムの遅延だけでなく、市場のミクロ構造、すなわち個々の取引がどのように行われるかというメカニズムに深く根差しています。
この種の取引コストを体系的に分析する上で画期的な枠組みとなったのが、アンドレ・ペロルドによって提唱された「執行ショートフォール」という概念です。これは、取引を決定した時点の価格と、実際に取引が完了した後のポートフォリオ価値との差を測定するもので、スリッページは、この執行コストを構成する重要な要素の一つとして位置づけられています [1]。
スリッページが発生する主な原因は二つあります。一つは、注文が取引所に到達するまでの僅かな時間差の間に、市場価格そのものが変動してしまうこと。もう一つは、より本質的な問題として、自身の注文が市場に与える影響、すなわちマーケットインパクトです。特に、流動性が低い銘柄や、大きな数量の注文を出す際には、このスリッページがリターンを大きく蝕む要因となります。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
スリッページは、本質的にトレーダーが負担するコストであり、それ自体に「長所」は存在しません。しかし、スリッページが発生する可能性を受け入れる成行注文には「約定の確実性」という明確な利点があります。ここでは、スリッページというコストの性質と、それを管理するアプローチについて解説します。
長所、強み、有用な点について
スリッページを許容する成行注文の最大の強みは、取引を迅速かつ確実に成立させられる点にあります。価格の「ズレ」を許容しない指値注文は、市場価格が指定した価格に達しなければ、いつまでも約定しない可能性があります。特に、市場が急変している局面で、素早くポジションを構築、あるいは手仕舞いたい場合、多少のスリッページを許容してでも取引を成立させることが、より大きな損失を回避するために不可欠となることがあります。
また、スリッページを含む執行コストは、ただ受け入れるだけでなく、管理・最適化の対象となり得ます。ある研究では、市場のボラティリティや取引数量といった条件の下で、執行コストを最小化するための最適な取引戦略を数学的に導出する枠組みが示されています [4]。これは、スリッページという現象を理解し、その発生メカニズムをモデル化することで、より洗練された取引執行が可能になることを示唆しています。
短所、弱み、リスクについて
スリッページの最大の短所は、それがリターンを直接的に蝕む、予測困難な取引コストであるという点です。特に、機関投資家のような大口の取引においては、その影響は深刻です。
ある大規模な実証研究によれば、機関投資家が負担する執行コスト(スリッページや手数料など)は、取引金額の0.5%から1%以上に達することが報告されています。このコストは、特に売買のインパクトが大きい小型株において、より高くなる傾向がありました [2]。年間で何度も取引を繰り返すアクティブな戦略にとって、このコストの蓄積は、パフォーマンスに致命的な影響を与えかねません。
なぜ、特に大口の取引は大きなスリッページを生むのでしょうか。その背景には、市場参加者の間の「情報の非対称性」があります。市場の他の参加者は、大口の注文が、その銘柄に関する何らかの未公開情報を持つ「インフォームド・トレーダー」からのものである可能性を警戒します。そのため、大口の買い注文が出ると、売り手は価格を吊り上げ、逆に大口の売り注文が出ると、買い手は価格を切り下げて対応します。このメカニズムが、マーケットインパクト、すなわちスリッページを生み出すのです [3]。
さらに、スリッページの大きさは、個別の取引だけでなく、市場全体の環境にも大きく左右されます。市場全体の流動性が低下すると、個々の取引コストは上昇する傾向があることが示されています [5]。これは、市場が不安定な時期には、平時よりも大きなスリッページが発生しやすくなることを意味します。
また、近年の市場では、高頻度取引(HFT)が流動性供給に大きな役割を果たしていますが、その一方で、市場のストレス時にはHFTが流動性供給を引き揚げることで、スリッページが急拡大するリスクも指摘されています [6]。
非対称性と摩擦の視点から
スリッページという現象は、単なるコスト以上の、市場の根源的な性質を映し出す鏡です。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことで、なぜこの「ズレ」が避けられないのかを深く理解することができます。
Asymmetry:情報の非対称性と注文の非対称性
スリッページが生まれる根源には、市場参加者の間に存在する「情報の非対称性」があります。もし全ての参加者が同じ情報を同時に持っていれば、大口の注文が出ても、それが特別な情報を持っているとは誰も考えません。しかし、現実の市場では、一部のトレーダーが他の参加者が知らない情報を持っている可能性があります。
この情報の非対称性があるために、市場は常に「この大口注文は、何かを知っているインフォームド・トレーダーからのものではないか」という警戒心に満ちています [3]。この警戒心が、マーケットメーカーや他の参加者に、大口注文に対して不利な価格を提示させるのです。これが、マーケットインパクトとして現れるスリッページの本質です。
さらに、スリッページの発生には「注文の非対称性」も関わっています。市場から流動性を奪う「成行注文」は、流動性を提供する「指値注文」よりも、本質的に大きなスリッページを生み出す傾向があります。すぐに取引を成立させたいという要求(成行注文)は、その緊急性の対価として、スリッページというコストを支払うことになるのです。
Friction:レイテンシーと板の厚さという物理的な摩擦
スリッページは、市場に存在する物理的な「摩擦」そのものと言えます。手数料やスプレッドといった分かりやすい摩擦に加え、より根源的な二つの摩擦が存在します。
第一に、「レイテンシー(遅延)」という情報の摩擦です。あなたが発注ボタンをクリックしてから、その注文情報が取引所のサーバーに到達するまでには、たとえそれがミリ秒単位であっても、物理的な時間がかかります。その僅かな時間の間に、市場の状況は刻一刻と変化します。この情報の伝達速度の限界という摩擦が、意図した価格と約定価格の間にズレを生じさせる、最も基本的な原因の一つです。
第二に、「板の厚さ(市場の深さ)」という流動性の摩擦です。取引所の注文板(オーダーブック)は、連続的な価格のラインではなく、各価格帯にどれだけの注文が出されているかを示す、離散的な「壁」の集まりです。あなたの成行注文は、最も有利な価格の壁から順番に注文を消化していきます。もし注文数量が大きく、最初の壁(最も有利な価格の注文量)を突き破ってしまえば、次に有利な価格、その次に有利な価格へと、階段を駆け上がるように不利な価格で約定していくことになります。この注文板の「厚さ」という物理的な摩擦が、特に大口注文において深刻なスリッページを引き起こすのです。
総括
- スリッページとは、注文価格と実際の約定価格との間に生じる、トレーダーにとって不利な価格差のことです。
- これは、取引システムの遅延や、自身の注文が価格を動かすマーケットインパクトによって発生する、目に見えにくい取引コストの一種です [1]。
- 大口の取引や小型株では、スリッページを含む執行コストが取引金額の1%以上に達することもあり、リターンを大きく圧迫する要因となります [2]。
- スリッページの根源には、一部のトレーダーが有利な情報を持つ可能性を市場が警戒する「情報の非対称性」が存在します [3]。
- 物理的には、注文の到達時間(レイテンシー)や、注文板の厚さ(市場の深さ)といった「摩擦」がスリッページを引き起こします。
用語集
スリッページ 注文を出した時の価格と、実際に取引が成立した価格との間に生じる差のこと。特に、トレーダーにとって不利な方向に価格が動いた場合を指す。
約定 買い注文または売り注文が、取引所で成立すること。
成行注文 価格を指定せず、現在の市場価格で売買を成立させる注文方法。約定の確実性が高いが、スリッページが発生しやすい。
指値注文 売買したい価格を指定する注文方法。指定した価格か、それより有利な価格でしか約定しないが、取引が成立しない可能性もある。
市場のミクロ構造 個々の取引がどのように行われ、価格が形成されるかといった、市場の微細な構造やメカニズムを研究する分野。
執行ショートフォール 取引を決定した瞬間の価格と、全ての取引が完了した後の実際のポートフォリオ価値との差を測る、総合的な取引コストの尺度。
マーケットインパクト 自身の取引が、市場価格に影響を与えてしまうこと。特に大口の注文で顕著になる。
情報の非対称性 市場参加者の間で、保有している情報に質や量の差がある状態のこと。
流動性 資産を、市場価格に大きな影響を与えることなく、どれだけ迅速に、大量に売買できるかの度合い。
高頻度取引(HFT) 高性能なコンピュータと高速通信を利用して、ミリ秒単位で自動的に売買を繰り返す取引手法。
参考文献一覧
[1] Perold, A. F. (1988). The implementation shortfall: Paper versus reality. The Journal of Portfolio Management, 14(3), 4-9.
https://doi.org/10.3905/jpm.1988.409150
[2] Keim, D. B., & Madhavan, A. (1997). Transaction costs and investment style: An inter-exchange analysis of institutional equity trades. Journal of Financial Economics, 46(3), 265-292.
https://doi.org/10.1016/S0304-405X(97)00031-7
[3] Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6), 1315-1335.
https://doi.org/10.2307/1913210
[4] Almgren, R., & Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3(2), 5-40.
https://doi.org/10.21314/JOR.2001.041
[5] Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2001). Market liquidity and trading activity. The Journal of Finance, 56(2), 501-530.
https://www.jstor.org/stable/222572
[6] Brogaard, J., Hendershott, T., & Riordan, R. (2014). High-frequency trading and price discovery. The Review of Financial Studies, 27(8), 2267-2306.
https://www.jstor.org/stable/24465658
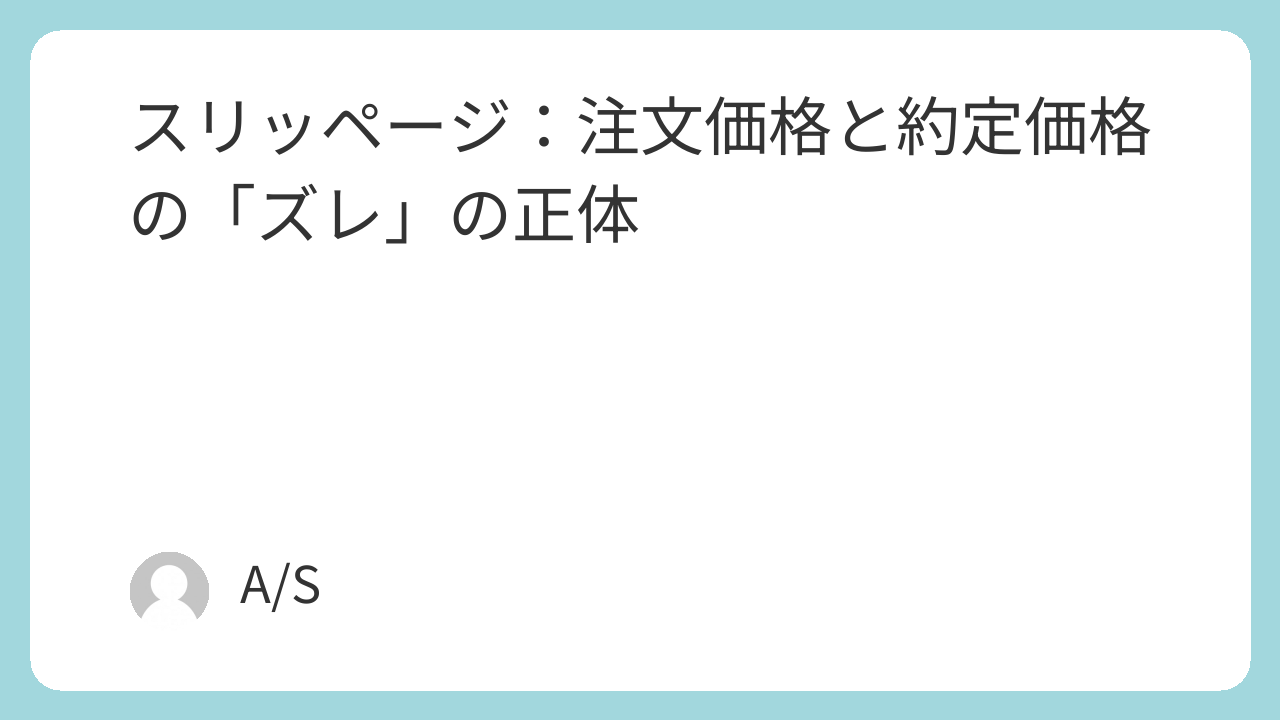
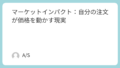
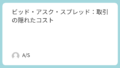
コメント