概論
株式取引を行う際、多くの投資家は売買手数料やスプレッドといった、目に見える「明示的なコスト」に注意を払います。しかし、特に大きな規模の取引においては、これらのコストを遥かに上回る、目に見えない「隠れたコスト」が存在します。それが、マーケットインパクトです。
マーケットインパクトとは、自分自身の取引が市場の需給バランスに影響を与え、結果として価格を自身にとって不利な方向へ動かしてしまう現象を指します。例えば、ある株式を大量に買おうとすれば、その買い圧力によって株価は上昇し、平均取得単価は注文を出す前よりも高くなってしまいます。逆に、大量に売ろうとすれば、売り圧力によって株価は下落し、平均売却単価は下がってしまいます。この約定価格の悪化こそが、マーケットインパクトというコストの正体です。
この現象を理論的に説明した金字塔的な研究が、カイルのモデルです。このモデルは、市場に存在する情報の非対称性を仮定し、情報を知る者(インサイダー)の取引が、その情報を持たないマーケットメーカーに価格の変動を通じてシグナルを送る過程を描写しました [1]。つまり、マーケットインパクトの根源には、取引という行動そのものが、市場に新たな「情報」を伝え、価格形成に影響を与えるという側面があるのです。
古くからの実証研究においても、マーケットインパクトは取引コストの主要な構成要素であることが示されており、多くの場合、売買手数料といった明示的なコストよりも遥かに大きいことが指摘されています [2]。この隠れたコストを理解し、管理することは、特に機関投資家にとって、リターンを最大化するための死活問題なのです。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
マーケットインパクトは、それ自体が利益を生むものではなく、本質的には取引における「コスト」あるいは「摩擦」です。したがって、その長所とは、インパクトの存在を理解し、それを管理・分析することによって得られる相対的な優位性を指します。
長所:インパクトの理解と管理がもたらす優位性
マーケットインパクトを深く理解することの最大の利点は、取引コストを削減し、投資リターンを向上させられる点にあります。近年の大規模な実証研究によれば、取引コスト、特にマーケットインパクトは極めて大きく、その大きさは資産クラスや市場、取引のタイミングによって大きく異なることが示されています [3]。このコストの存在を認識し、例えばVWAP(出来高加重平均価格)やTWAP(時間加重平均価格)といったアルゴリズム取引を用いて、大きな注文を時間や出来高に応じて分割して執行することは、インパクトを抑制し、最終的なリターンを改善するための標準的な手法となっています。
また、マーケットインパクトの存在、すなわち市場の非流動性は、新たなリターンの源泉にもなり得ることが示されています。市場の流動性が低い(=マーケットインパクトが大きい)銘柄は、その取引の難しさから敬遠されがちですが、そのリスクを引き受ける対価として、流動性の高い銘柄よりも高いリターンを提供する傾向があることが、多くの研究で明らかにされています [4]。この「非流動性プレミアム」を理解し、自らの執行能力に応じてポートフォリオに組み込むことは、一つの投資戦略となり得るのです。
短所:リターンを蝕む避けられないコスト
マーケットインパクトの最も直接的な短所は、それがリターンを蝕む、避けられないコストであるという点です。どんなに優れた投資アイデアがあったとしても、そのポジションを構築し、解消する過程で発生するマーケットインパクトが、期待される利益(アルファ)を上回ってしまえば、その戦略は机上の空論に終わります。
実際に、機関投資家の取引データを分析した古典的な研究では、マーケットインパクトの大きさが定量的に示されています。例えば、ある研究によれば、機関投資家による大規模な売り取引では、取引に関連する価格への負の影響が観測されました。また、大規模な買い取引においても、価格を押し上げる効果が見られました [5]。これらのコストは、多くの投資戦略が生み出すわずかな優位性を、容易に消し去ってしまうほどの大きさになり得るのです。
この事実は、あらゆる投資戦略にはその規模の限界、すなわち「戦略のキャパシティ」が存在することを意味します。ある投資戦略が、例えば10億円の規模では利益を生むとしても、1,000億円の規模で同じ戦略を実行しようとすれば、自身のマーケットインパクトによって価格が大きく動いてしまい、利益が消失、あるいは損失に転じる可能性があります。マーケットインパクトは、戦略の有効性をその規模と結びつけて考えることの重要性を教えてくれるのです。
非対称性と摩擦の視点から
マーケットインパクトは、市場が完璧に滑らかで効率的ではないという現実から生まれる現象です。その本質は、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:情報の非対称性が生み出す価格変動
マーケットインパクトが発生する根源には、市場参加者の間に存在する「情報の非対称性」があります。もし全ての参加者が全く同じ情報を同時に共有していれば、大きな注文が入ったとしても、それが新しい情報を含まない限り、価格は動かないはずです。
しかし、現実の市場では、一部の投資家が他の投資家よりも優れた情報や分析を持っている可能性があります。カイルのモデルが示したように、マーケットメーカーは、目の前の大口注文が、単なる資金の出し入れ(ノイズ取引)なのか、あるいは重要な情報を持った投資家(インフォームドトレーダー)によるものなのかを完全には見分けることができません [1]。この情報の非対称性があるため、マーケットメーカーは自身を守るために、大口の買い注文に対しては価格を上げ、大口の売り注文に対しては価格を下げて対応します。つまり、マーケットインパクトとは、取引の背後にあるかもしれない「情報」に対して、市場が価格を調整するプロセスそのものなのです。
また、インパクトの現れ方にも非対称性が見られます。実証研究によれば、買い取引による価格の上昇インパクトと、売り取引による価格の下落インパクトの大きさは、必ずしも対称的ではありません。市場の状況や流動性によって、どちらか一方のインパクトがより強く現れることがあります [5]。
Friction:リターンを蝕む市場の「摩擦」そのもの
マーケットインパクトは、金融市場に存在する様々な「摩擦」が凝縮されて現れた現象と言えます。それは、理論上の期待リターンと、実際に手にするリターンとの間に存在する、避けられないギャップの源泉です。
最も本質的な摩擦は、「市場流動性の限界」です。もし市場に無限の買い手と売り手が存在する、完全に滑らかな(frictionless)状態であれば、どれだけ大きな注文を出しても価格は動きません。しかし、現実の市場では、特定の価格で取引できる量は有限です。大口注文は、この限られた流動性を消費するため、より不利な価格を受け入れざるを得なくなります。この意味で、マーケットインパクトは市場の非流動性という摩擦の大きさを測る直接的な指標であり、この摩擦が大きい銘柄は、そのリスクの対価としてより高いリターンを要求される傾向があります [4]。
また、取引という行為そのものが情報を伝達してしまうという「情報の摩擦」も存在します。自分の取引意図が市場に漏れ伝わることで、他の投機家が先回りしてしまい、価格がさらに不利な方向へ動いてしまうのです。この情報の摩擦を最小限に抑えるために、機関投資家は自身の注文を巧妙に隠しながら執行する必要に迫られます。
これらの摩擦の存在は、投資戦略が生み出す超過リターン(アルファ)がいかに脆いものであるかを教えてくれます。多くの取引コストに関する研究が示すように、手数料やスプレッドといった明示的なコストよりも、マーケットインパクトという隠れた摩擦の方が、遥かに大きなコストとなり得るのです [2, 3]。
総括
- マーケットインパクトとは、自身の取引が市場価格を不利な方向へ動かしてしまう、取引の「隠れたコスト」です。
- その理論的な起源は、市場参加者間の「情報の非対称性」にあり、取引行動が価格形成に影響を与えるプロセスとして説明されます [1]。
- 実証研究によれば、マーケットインパクトは売買手数料などの明示的なコストを上回ることが多く、リターンを蝕む主要な要因です [2, 5]。
- マーケットインパクト(非流動性)の大きさは、それ自体が株式リターンを説明する体系的なリスクファクターとして認識されています [4]。
- マーケットインパクトは、あらゆる投資戦略に内在する「キャパシティ(規模)の限界」を決定づける要因であり、この「摩擦」を管理することが、特に大規模な資金を運用する上で極めて重要となります [3]。
用語集
マーケットインパクト 自身の取引行動が市場の需給に影響を与え、価格を自身にとって不利な方向へ動かしてしまう効果。取引における隠れたコストの主要因。
市場流動性 資産を、市場価格に大きな影響を与えることなく、どれだけ迅速に、大量に売買できるかの度合い。流動性が低い市場ほど、マーケットインパクトは大きくなる。
スリッページ 注文を出した時の価格と、実際に約定した時の価格との差のこと。マーケットインパクトはスリッページを発生させる主要な原因の一つ。
約定価格 実際に取引が成立した価格。
情報の非対称性 市場参加者の間で、保有している情報に質や量の差がある状態。マーケットインパクトが発生する根源的な理由とされる。
カイルのモデル 経済学者アルバート・カイルが提唱した、情報の非対称性が存在する市場で、インフォームドトレーダーの取引がどのように価格に影響を与えるかをモデル化した、市場マイクロストラクチャー理論の金字塔。
アルゴリズム取引 あらかじめ定められたプログラム(アルゴリズム)に基づき、コンピュータが自動的に売買注文のタイミングや数量を決定し、執行する取引。マーケットインパクトの抑制などを目的として広く用いられる。
VWAP (Volume-Weighted Average Price) 出来高加重平均価格。当日の取引所の総売買代金を総出来高で割って算出される平均価格。アルゴリズム取引では、この価格に近い価格での約定を目指すことが多い。
リミットオーダーブック (板) 指値注文(リミットオーダー)が価格順に並んだ一覧表のこと。市場の需要と供給の状況を視覚的に示す。
戦略のキャパシティ ある投資戦略が、自己のマーケットインパクトによって収益性を損なうことなく、運用できる資金量の上限。
参考文献一覧
[1] Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6), 1315-1335.
https://doi.org/10.2307/1913210
[2] Berkowitz, S. A., Logue, D. E., & Noser, E. A. (1988). The total cost of transactions on the NYSE. The Journal of Finance, 43(1), 97-112.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02591.x
[3] Frazzini, A., Israel, R., & Moskowitz, T. J. (2018). Trading costs. Journal of Financial Economics, 128(2), 295-313.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3229719
[4] Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Economics, 64(1), 31-62.
https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6
[5] Chan, L. K., & Lakonishok, J. (1995). The behavior of stock prices around institutional trades. The Journal of Finance, 50(4), 1147-1174.
https://doi.org/10.2307/2329347
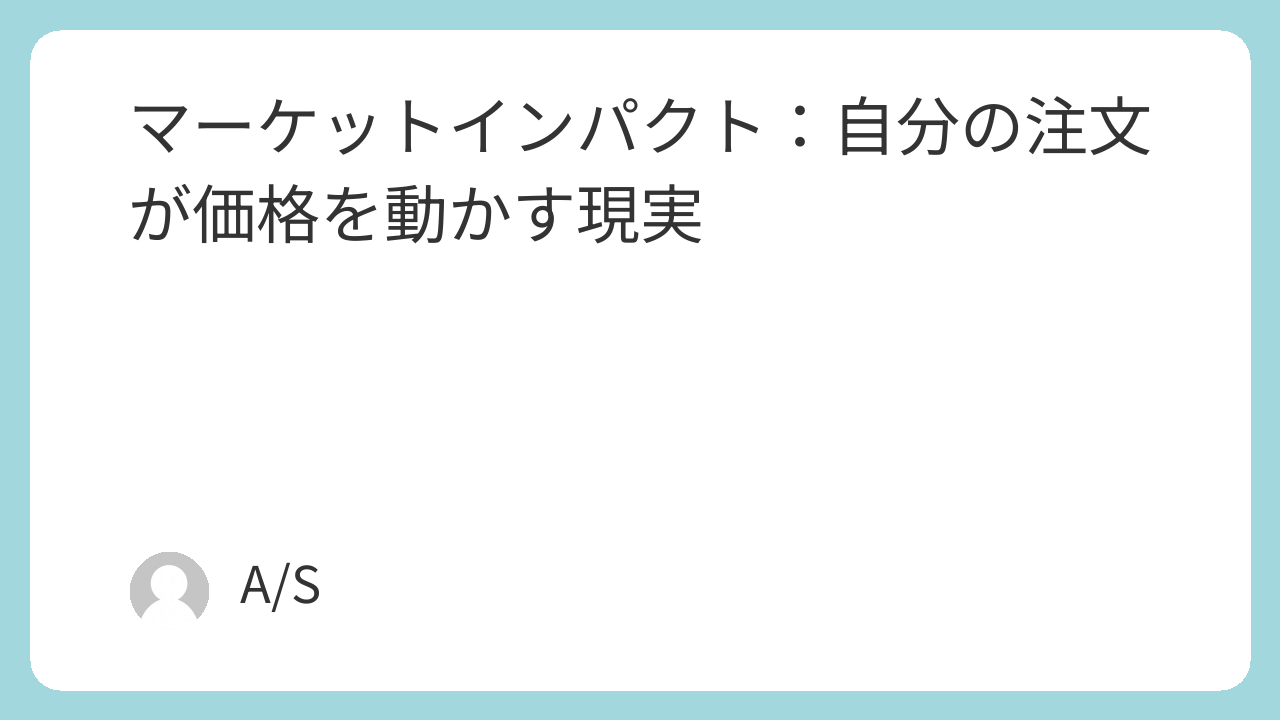
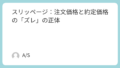
コメント