概論
市場の価格は、マクロ経済の動向や、長期的なファンダメンタルズの変化だけで動くわけではありません。企業の運命を左右する個別の「イベント」は、株価に短期的かつ大きな影響を与え、そこに特殊な投資機会を生み出します。イベントドリブン戦略とは、このような企業固有のイベント(コーポレート・イベント)によって生じる価格の歪みを収益機会として捉える、ヘッジファンドの代表的な戦略の一つです [1]。
この戦略が対象とする「イベント」は多岐にわたりますが、代表的なものとして、企業の合併・買収(M&A)、業績のサプライズがあった決算発表、あるいは自社株買いの発表などが挙げられます。イベントドリブン戦略は、これらのイベントの結果を予測し、市場がその価値を完全に織り込むまでの非効率なプロセスを利用します。
その中でも最も古典的でよく知られているのが、M&Aの発表を利用するマージャー・アービトラージ(合併裁定取引)です。これは、買収が発表された後、一般的に発生する被買収企業の株価と買収価格との差額(スプレッド)を利益として狙う戦略です。このスプレッドは、M&Aが無事に完了する確率と、完了するまでの時間に対するリターンを反映しています [2]。
また、決算発表もイベントドリブン戦略の重要な対象です。市場には、決算発表でポジティブ(あるいはネガティブ)なサプライズがあった企業の株価が、発表直後だけでなく、その後も数ヶ月にわたって同じ方向に緩やかに動き続けるという、ポスト・アーニングス・アナウンスメント・ドリフト(PEAD)として知られるアノマリーが存在します [3]。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
長所、強み、有用な点について
イベントドリブン戦略が多くの投資家を惹きつける最大の魅力は、そのリターンの源泉が、伝統的な株式市場全体の動きとは異なる点にあります。
市場全体との低い相関
イベントドリブン戦略、特にマージャー・アービトラージのリターンは、その成否が株式市場全体の上下動ではなく、「M&Aディールが無事に完了するかどうか」という個別のイベントに依存します。そのため、そのリターンは、市場が横ばいか上昇している局面では、市場リターンとの相関がないことが報告されています [2]。これは、ポートフォリオ全体のリスクを分散させる上で、非常に大きなメリットとなります。
収益事例1:マージャー・アービトラージのリターン
マージャー・アービトラージは、歴史的にプラスの超過リターンを生み出してきました。MitchellとPulvinoによる2001年の研究によれば、1981年から1996年の期間において、リスク・アービトラージの分散されたポートフォリオは、月あたり0.6%から0.9%の異常リターンを生み出していたことが示されています [2]。
収益事例2:ポスト・アーニングス・アナウンスメント・ドリフト(PEAD)
決算発表のサプライズを利用する戦略も、体系的な収益機会となり得ることが知られています。BernardとThomasによる1989年の研究では、決算発表後の株価がサプライズの方向に継続して動くドリフト現象が確認されており、これを売買ルールに組み込むことでリターンを得られる可能性が示唆されています [3]。
収益事例3:自社株買い発表後の長期リターン
企業による自社株買いの発表も、強力な投資シグナルとなり得ます。Ikenberryらによる1995年の研究では、自社株買いを発表した企業は、発表後の4年間で平均して12.1%の異常リターンを記録したことが示されました。特に、割安と見なされる「バリュー株」においては、そのリターンは平均で45.3%にも達しました [4]。
短所、弱み、リスクについて
その独自のリターンの源泉の裏で、イベントドリブン戦略は、予測が困難で、かつ発生した際の影響が非常に大きい、特殊なリスクを内包しています。
イベント・リスク(ディール・ブレイク・リスク)
マージャー・アービトラージにおける最大のリスクは、規制当局の反対や株主の承認否決などによって、発表されていたM&Aが破談になる「ディール・ブレイク・リスク」です。もしディールが失敗すれば、被買収企業の株価は買収発表前の水準にまで急落し、アービトラージャーは短期間で極めて大きな損失を被ることになります。このリターン特性は、平時にはコツコツと小さな利益を積み上げる一方で、稀に発生する市場の暴落時に大きな損失を被る「プット・オプションの売却」に似ていると指摘されています [2]。
失敗(損失)事例:市場全体の危機と「動けなくなる資本」
イベントドリブン戦略のリスクは、個別のイベントの成否だけに留まりません。市場全体を巻き込む金融危機時には、本来であれば無関係なはずの戦略までもが機能不全に陥ることがあります。Mitchell, Pedersen, Pulvinoによる2007年の研究では、市場のストレスが高まった際に、専門のアービトラージャーが巨額の資本を失い、その結果として、彼らが本来の役割である流動性の供給者から、むしろ流動性を求める側になってしまうケースが分析されています [5]。これは、現実世界の摩擦が裁定資本の動きを妨げ(Slow Moving Capital)、価格の歪みが是正されるどころか、むしろ拡大してしまうことを意味します。この種のシステミックなリスクは、個別のディールの成否をどれだけ精密に分析しても、避けることが困難な損失の源泉です。
非対称性と摩擦の視点から
イベントドリブン戦略がなぜ収益機会となり得るのか、そしてそのリターンがどのようなリスクと表裏一体であるのかは、「非対称性」と「摩擦」の観点から深く理解することができます。
Asymmetry:非対称なリターン構造
イベントドリブン戦略、特にマージャー・アービトラージの本質は、その非対称なリターンプロファイルにあります。この戦略は、M&Aディールが無事に完了すれば、比較的小さなリターン(スプレッド)を高い確率で得ることができます。しかし、もしディールが稀に破談となれば、株価は急落し、一度に大きな損失を被ることになります。
この「高確率で小さな利益」と「低確率で大きな損失」という構造は、プット・オプションを売却する際のペイオフと酷似しています [2]。オプションの売り手(保険の引受人)が、平時にはコツコツとプレミアム(保険料)を稼ぐ一方で、稀に発生する大災害(暴落)で壊滅的な支払いを要求されるのと全く同じです。この非対称なリスク構造を正確に理解し、管理することこそが、この戦略で成功するための鍵となります。
Friction:リターンの源泉としての「摩擦」
もしM&Aの完了が100%確実で、そのプロセスに何の時間もかからないならば、アービトラージのスプレッドは存在しないはずです。スプレッド、すなわちリターンが生まれるのは、ディールが完了するまでのプロセスに、様々な摩擦が存在するからです。
「規制」という制度的摩擦
M&Aが完了するためには、独占禁止法や安全保障上の観点から、規制当局の承認を得る必要があります。この承認プロセスには時間がかかり、そして常に不承認となるリスクが伴います。この規制という制度的摩擦こそが、アービトラージにおける不確実性の源泉であり、スプレッド(リスクプレミアム)を生み出す最大の要因です。
「資本」という市場の摩擦
たとえ理論上は魅力的な裁定機会が存在していても、それを利用するための資本が市場から枯渇してしまえば、戦略は機能しません。市場全体のストレスが高まる金融危機時には、専門のアービトラージャーですら巨額の資本を失い、ポジションを維持できなくなることがあります [5]。このように、裁定取引を実行するための資本そのものが制約を受ける(Slow Moving Capital)という市場の摩擦が、価格の歪みを是正する力を妨げ、時には損失を拡大させる原因となるのです。
総括
- イベントドリブン戦略とは、M&Aや決算発表といった企業固有のイベントによって生じる価格の歪みを利用する投資手法です [1]。
- その最大の長所は、リターンの源泉が市場全体の動きとの相関が低く、ポートフォリオの分散に貢献する点にあります [2]。
- 具体的な収益機会として、マージャー・アービトラージ [2]、ポスト・アーニングス・アナウンスメント・ドリフト [3]、自社株買い [4]などが学術的に報告されています。
- 最大の短所は、M&Aの破談といった「イベント・リスク」であり、発生確率は低いものの、一度起こると壊滅的な損失をもたらす非対称なリスクを内包しています [2]。
- 個別のイベントリスクだけでなく、市場全体の金融危機によって裁定資本が機能不全に陥るというシステミックなリスクも存在します [5]。
用語集
イベントドリブン戦略 (Event-Driven Strategy) 企業の合併・買収(M&A)、事業再編、経営破綻といった、株価に大きな影響を与えるコーポレート・イベントに着目し、そこから生じる収益機会を狙う投資戦略。
コーポレート・イベント (Corporate Event) 企業の財政状態や構造に大きな変化をもたらす出来事の総称。
マージャー・アービトラージ (Merger Arbitrage) 合併裁定取引とも呼ばれる。M&Aが発表された後、被買収企業の株価と買収価格との間に生じる差額(スプレッド)を利益として獲得することを狙う戦略。
裁定取引 (Arbitrage) 同一の価値を持つ資産間で価格差が生じた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を得ようとする取引。
スプレッド (Spread) この文脈では、マージャー・アービトラージにおいて、被買収企業の現在の株価と、買収が成立した際の受け取り価格との差額のこと。
ポスト・アーニングス・アナウンスメント・ドリフト (PEAD) 企業の決算発表が市場予想を上回る(あるいは下回る)サプライズだった場合に、その株価が発表後も数ヶ月にわたって同じ方向に緩やかに動き続けるアノマリー。
自社株買い (Share Repurchase) 企業が自社の発行済み株式を市場から買い戻すこと。一般的に、株主価値を高めるためのポジティブなシグナルと見なされる。
ディール・ブレイク・リスク (Deal Break Risk) マージャー・アービトラージにおいて、規制当局の不承認などによって、発表されていたM&Aが破談になるリスク。
プット・オプション (Put Option) ある資産を、将来の特定の期日までに、あらかじめ定められた価格で「売る権利」のこと。プット・オプションの売り手は、プレミアムを受け取る代わりに、価格が暴落した際に損失を被るリスクを負う。
システミックリスク (Systemic Risk) ある金融機関や市場の危機が、ドミノ倒しのように金融システム全体に波及していくリスク。
参考文献一覧
[1] Lhabitant, F. S. (2006). Handbook of hedge funds. John Wiley & Sons.
※書籍です
[2] Mitchell, M. L., & Pulvino, T. (2001). Characteristics of risk and return in risk arbitrage. The Journal of Finance, 56(6), 2135-2175.
https://doi.org/10.1111/0022-1082.00401
[3] Bernard, V. L., & Thomas, J. K. (1989). Post-earnings-announcement drift: Delayed price response or risk premium?. Journal of Accounting Research, 27, 1-36.
https://doi.org/10.2307/2491062
[4] Ikenberry, D., Lakonishok, J., & Vermaelen, T. (1995). Market underreaction to open market share repurchases. Journal of Financial Economics, 39(2-3), 181-208.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00826-Z
[5] Mitchell, M., Pedersen, L. H., & Pulvino, T. (2007). Slow moving capital. American Economic Review, 97(2), 215-220.
https://doi.org/10.1257/aer.97.2.215
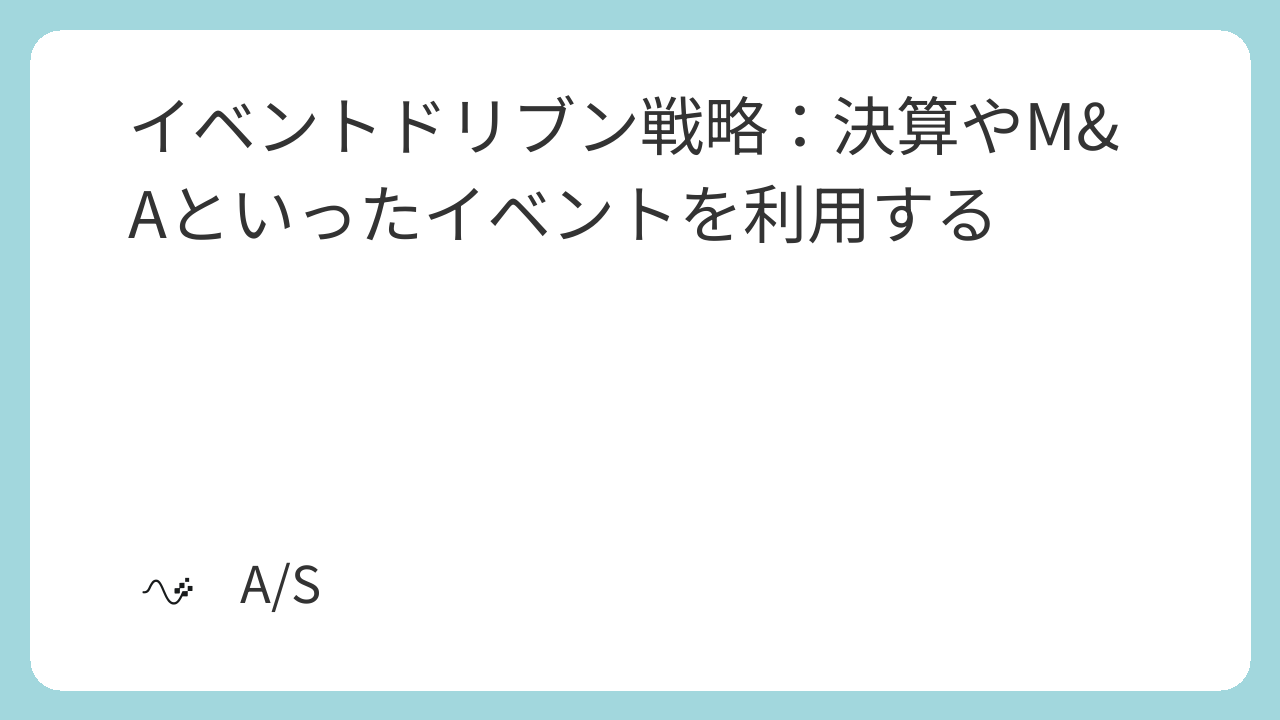
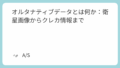
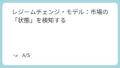
コメント