概論
グローバル化が進んだ現代において、海外の株式や債券へ投資することは、ポートフォリオの分散を考える上でごく自然な選択肢となりました。しかし、日本の投資家が米国の株式に投資する場合、そのリターンは米国の株価の変動だけでなく、米ドルと日本円の為替レートの変動によっても大きく左右されます。たとえ株価が上昇しても、円高が進めば円換算でのリターンは減少し、場合によっては損失を被ることさえあります。
この、投資家がコントロールできない為替レートの変動リスク、すなわち為替リスクを管理するための代表的な手法が、通貨ヘッジです。通貨ヘッジとは、先物為替予約などの金融派生商品(デリバティブ)を利用して、将来の為替レートをあらかじめ固定することで、為替変動がポートフォリオに与える影響を抑制しようとする戦略を指します。
この通貨ヘッジをどの程度行うべきか、という問いは、金融の世界における長年の論争の的となってきました。為替リスクを完全に除去するために100%ヘッジすべきだという考え方がある一方で、ヘッジにはコストがかかり、時にはポートフォリオの分散効果を損なう可能性もあるため、ヘッジしない方が望ましい、あるいは部分的にヘッジすべきだという主張も存在します。
この論争の核心には、為替リスクを単なる不要なノイズと見なすか、それともポートフォリオ全体のリスクを相殺する有益な要素と見なすか、という根本的な視点の違いがあります。本記事では、この通貨ヘッジの必要性について、学術的な研究成果を基に、その長所と短所の両面から深く掘り下げていきます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
通貨ヘッジは、ポートフォリオのリスクを管理する上で強力なツールとなり得ますが、その効果は万能ではなく、コストや機会損失といった無視できない側面も持ち合わせています。
長所、強み、有用な点について
通貨ヘッジがもたらす最も直接的で、かつ最大の恩恵は、ポートフォリオのリターンにおけるボラティリティ(変動性)の低減です。海外資産のリターンは、現地の資産リターンと為替リターンの二つの不確実性の源泉から構成されています。通貨ヘッジは、このうちの為替リターンという不確実性を取り除くことで、ポートフォリオ全体のリスクを明確に減少させます。
多くの実証研究が、このリスク削減効果を裏付けています。例えば、グレンとジョリオンによる1993年の研究は、主要国の株式および債券ポートフォリオにおいて、通貨ヘッジがポートフォリオの分散(ボラティリティ)を有意に減少させることを示しました [1]。彼らの分析によれば、特に国際債券ポートフォリオにおいては、為替リスクがリターンの変動の大部分を占めるため、ヘッジによるリスク削減効果は極めて大きいことが確認されています。
このリスク削減効果は、投資家が自身のリスク許容度に合わせてポートフォリオを管理する上で、非常に重要な意味を持ちます。為替の動きという予測困難な要素を排除することで、投資家は投資対象である海外資産そのもののパフォーマンスに、より集中することができるのです。また、為替ヘッジ付きの投資信託などが提供されている背景には、このような投資家のリスク管理ニーズが存在します。
短所、弱み、リスクについて
一方で、通貨ヘッジは「ただ飯(フリーランチ)」ではなく、いくつかの深刻な短所やコストを伴います。手放しでその有効性を称賛することはできません。
第一に、ヘッジには直接的なコストがかかります。為替先物予約などを用いる場合、二国間の金利差や、金融機関に支払う手数料、ビッド・アスク・スプレッドといったコストが発生します。このヘッジコストが主に二国間の金利差によって決定されるという考え方は、カバー付き金利パリティという裁定条件によって理論的に裏付けられています [5]。これらのコストは、長期間にわたってリターンを確実に蝕んでいく要因となります。
第二に、より本質的な問題として、通貨ヘッジがポートフォリオの分散効果を損なう可能性が指摘されています。これは、為替レートの変動が、海外資産の価格変動と負の相関を持つ場合に起こります。ペロルドとシュルマンが1988年に指摘したように、例えば世界的な金融危機の際には、安全資産とされる米ドルが買われる(ドル高になる)一方で、米国の株価は下落する、といった現象が見られます [2]。このような状況では、日本の投資家にとって、株価下落による損失の一部がドル高によって相殺されるという「自然なヘッジ」が働きます。通貨ヘッジは、この有益な分散効果をも消し去ってしまうのです。
第三に、最適なヘッジ比率が常に変動し、事前に知ることが極めて困難であるという問題があります。フルトによる1993年の研究は、ヘッジの期間が長くなるほど、最適なヘッジ比率は100%から低下する傾向があることを示唆しています [3]。また、キャンベルらの2010年の研究によれば、最適なヘッジ比率は投資家のリスク許容度や市場の期待リターン、ボラティリティに応じて動的に変化します [4]。さらに、為替リスクの重要性が増す中で、最適な通貨配分を決定することの難しさも指摘されています [6]。これらの事実は、通貨ヘッジというリスク管理手法の難しさを物語っています。
非対称性と摩擦の視点から
通貨ヘッジを行うか否かという決定は、単なるリスク削減の計算だけに留まりません。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことで、より深い洞察を得ることができます。
Asymmetry:「安全な避難所」という非対称性
通貨ヘッジの議論における最も重要な非対称性は、金融危機時における為替の「安全な避難所(セーフヘイブン)」としての性質です。
世界的な市場の混乱期には、投資家はリスクの高い資産(株式など)を売り、より安全と見なされる資産へと資金を移動させる「質への逃避」という行動を取る傾向があります。この時、米ドルや日本円といった特定の通貨が、安全な避難所として買われることがしばしばあります [2]。
この現象は、日本の投資家が米国の株式に投資している場合に、非対称なリターン構造を生み出します。市場が平穏な時は、株価と為替の動きに明確な関係性はないかもしれません。しかし、ひとたび金融危機が発生すると、米国株は下落し、同時に米ドルは(対円で)上昇するという、負の相関関係が顕著になることがあります。この時、為替リスクは、株価下落による損失を緩和する「自然な保険」として機能します。
通貨ヘッジは、この危機時にのみ現れる非対称で有益な関係性を、平時のリスクと共に消し去ってしまいます。ヘッジを行うという決定は、平時のボラティリティを低下させる代わりに、危機時の貴重な緩衝材を放棄するという、非対称なトレードオフを受け入れることを意味するのです。
Friction:ヘッジコストと「情報の摩擦」
通貨ヘッジの有効性を阻害する要因、すなわち「摩擦」は、直接的なコストと、より根源的な情報の不完全性に分けられます。
第一に、最も分かりやすい摩擦が「ヘッジコスト」です。これは単なる取引手数料だけでなく、主に二国間の短期金利差によって決定されます。日本の投資家が米ドルを円に対してヘッジする場合、もし米国の金利が日本よりも高ければ、その金利差がコストとしてリターンを押し下げます。このコストの根幹をなすのが、カバー付き金利パリティによって示される二国間の金利差です [5]。
第二に、より深刻なのが「情報の摩擦」です。前述の通り、理論上の最適なヘッジ比率は、将来のリターン、ボラティリティ、そして資産間の相関関係に依存しますが、これらの変数を正確に予測することは誰にもできません [4]。投資家は、ノイズに満ちた過去のデータから、最適なヘッジ比率を「推定」するしかないのです。この「未来を知り得ない」という根源的な情報の摩擦が、通貨ヘッジを科学から一種の「アート」へと変えてしまいます [6]。100%ヘッジやゼロヘッジといった単純なルールが、複雑な最適化モデルよりも実践で好まれることがあるのは、この情報の摩擦を乗り越えることの難しさを物語っているのです。
総括
- 通貨ヘッジは、海外資産投資における為替レートの変動リスクを抑制し、ポートフォリオのボラティリティを有意に減少させる効果があります [1]。
- 主な長所はリスク削減効果ですが、短所として、直接的なヘッジコストや、危機時に有益な分散効果を損なう可能性が挙げられます [2]。
- 理論上の最適なヘッジ比率は、投資家のリスク許容度や市場環境に応じて常に変動するため、事前に特定することは極めて困難です [3, 4, 6]。
- 金融危機時には、米ドルなどが「安全な避難所」として機能し、株価下落を為替差益が相殺することがあります。通貨ヘッジは、この非対称な緩衝効果を放棄するトレードオフを伴います。
- ヘッジコスト(主に金利差)や、将来を予測できないという「情報の摩擦」が、通貨ヘッジ戦略の有効性を左右する重要な要因となります [5]。
用語集
通貨ヘッジ 為替先物予約などのデリバティブを用いて、将来の為替レートを固定し、為替変動リスクを抑制する戦略。
為替リスク 外貨建て資産の価値が、為替レートの変動によって自国通貨建てで増減するリスク。
先物為替予約 将来の特定の期日に、あらかじめ決められた価格(為替レート)で、特定の通貨を売買することを約束する取引。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを表す指標。一般的に、標準偏差で測定される。
分散効果 値動きの異なる複数の資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減させる効果。
デリバティブ 株式、債券、為替などの原資産から派生した金融商品の総称。先物、オプション、スワップなどがある。
最適ヘッジ比率 ポートフォリオのリスクを最小化する、あるいは効用を最大化するために最適な、ヘッジを行う資産の割合。
安全資産(セーフヘイブン) 金融危機などの市場混乱時に、投資家が資金の避難先として選好する資産。米ドル、日本円、金などが代表例。
負の相関 二つの資産の価格が、互いに逆の方向に動く傾向があること。分散投資において重要な役割を果たす。
ヘッジコスト 通貨ヘッジを行う際に発生する費用の総称。主に二国間の金利差によって決まる部分と、取引手数料などのコストから成る。
参考文献一覧
[1] Glen, J., & Jorion, P. (1993). Currency hedging for international portfolios. The Journal of Finance, 48(5), 1865-1886.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05131.x
[2] Perold, A. F., & Schulman, E. C. (1988). The free lunch in currency hedging: Implications for investment policy and performance measurement. Financial Analysts Journal, 44(3), 45-50.
https://doi.org/10.2469/faj.v44.n3.45
[3] Froot, K. A. (1993). Currency hedging over long horizons. NBER Working Paper Series, (4355).
https://doi.org/10.3386/w4355
[4] Campbell, J. Y., Medeiros, K., & Viceira, L. M. (2010). Global currency hedging. The Journal of Finance, 65(1), 87-121.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2009.01524.x
[5] Popper, H. (1993). Long-term covered interest parity: evidence from currency swaps. Journal of International Money and Finance, 12(4), 439-448.
https://doi.org/10.1016/0261-5606(93)90005-V
[6] Kaplanis, E. C., & Schaefer, S. M. (1991). Exchange risk and international diversification in bond and equity portfolios. Journal of Economics and Business, 43(4), 287-307.
https://doi.org/10.1016/0148-6195(91)90027-T
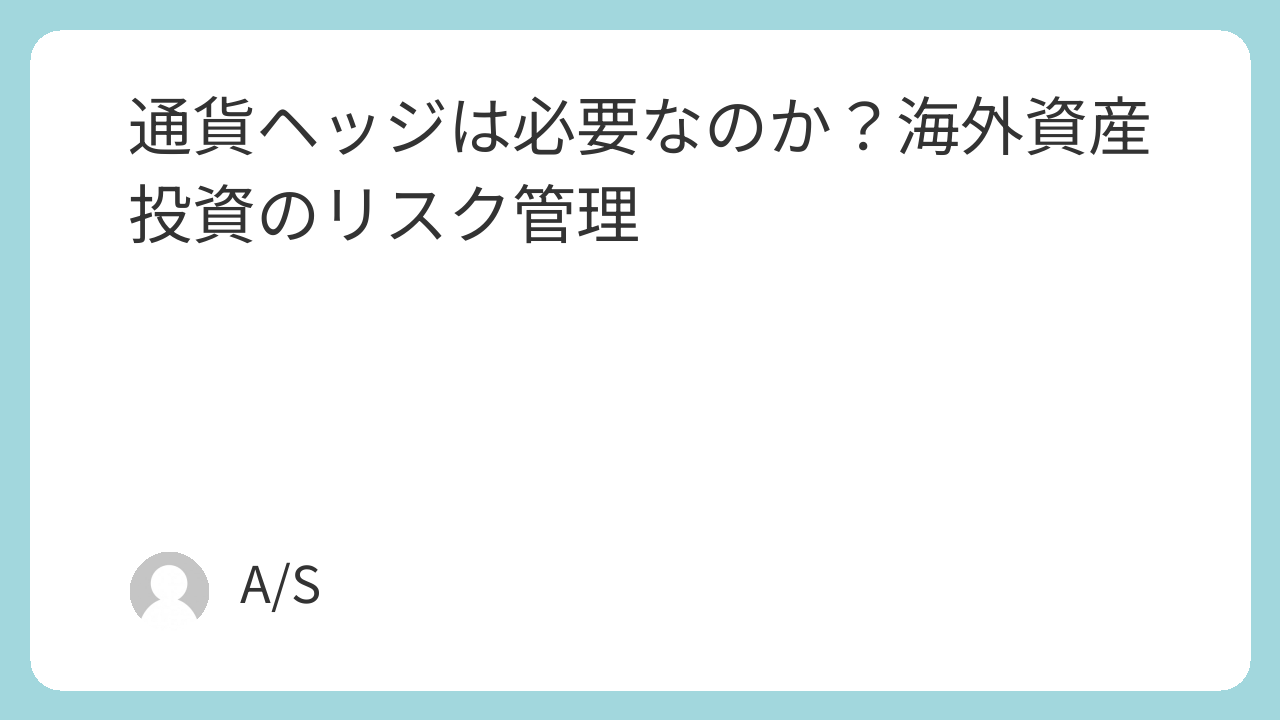
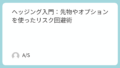
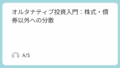
コメント