NTT株(9432)の概要
日本電信電話株式会社(NTT、銘柄コード:9432)は、単なる一通信企業ではありません。日本の経済史そのものであり、戦後復興から情報化社会への変遷を体現する存在です。その株価を分析することは、一企業の財務状況を追うだけでなく、国策、規制、技術革新、そして市場心理が複雑に絡み合う壮大な物語を読み解く試みと言えます。現在、NTTグループはNTTドコモが展開する移動通信事業を収益の柱としつつ 、データセンター事業や次世代光通信基盤「IOWN構想」といった未来への投資に舵を切っています。本稿では、日々のニュースに一喜一憂する短期的な視点から離れ、学術的な知見に基づき、NTT株に潜む長期的なエッジ(優位性)と、そのリターンを阻害する摩擦(フリクション)を、当メディア独自の視点から徹底的に解剖します。
NTTの株価を理解する上で不可欠なのが、その特異な出自です。NTTの起源は、日本の戦後復興期である1952年に、荒廃した通信インフラを再建する国家的な使命を帯びて設立された国営の「日本電信電話公社」に遡ります 。この公社が、1985年に民営化され、日本電信電話株式会社として株式市場に上場した出来事は、日本の資本市場における画期的な転換点でした。この民営化という行為は、単なる所有権の移転以上の意味を持ちます。学術研究の世界では、国営企業が民営化されることで、その財務および経営パフォーマンスが劇的に改善することが広く知られています。ウィリアム・メギンソンらが1994年に発表した国際的な実証研究では、民営化された企業は収益性、経営効率、そして設備投資額において有意な向上を示すことが明らかにされています 。この研究は、NTTが民営化によって手にした長期的な成長ポテンシャルの理論的根拠を与えてくれます。
その後、競争促進を目的として1999年には持ち株会社体制へと移行し、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズが設立され、現在のグループ構造の基礎が築かれました 。しかし、この民営化から30年以上が経過した現在でも、NTTの経営には「元国営企業」という出自が色濃く影を落としています。それは、全国津々浦々に通信サービスを提供する「ユニバーサルサービス責務」といった規制上の制約として、今なお経営の重石となっています。一方で、その過程で築き上げられた圧倒的な通信インフラは、他社が容易に模倣できない参入障壁として機能しています。現在議論が進むNTT法の改正は、政府保有株の売却や研究開発成果の開示義務の見直しを通じて、この「国策企業」としての最後の名残を断ち切り、真のグローバルな競争主体へと脱皮しようとする、数十年にわたる移行プロセスの最終章と位置づけることができます 。したがって、NTTの株価を分析する投資家は、この「公共性」と「収益性」の間で揺れ動いてきた歴史的文脈を理解することが不可欠なのです。
NTT株の長所・短所の分析
NTT株の長所:低ボラティリティに宿る不屈のエッジ
NTT株の最も顕著な長所の一つは、その「低ボラティリティ(低変動性)」という性質にあります。伝統的な金融理論では、高いリターンを得るためには高いリスクを取る必要があるとされますが、現実の株式市場では、むしろボラティリティの低い株式の方が、長期的に見て高いリスク調整後リターンを生み出すという「低ボラティリティ・アノマリー」が広く観測されています 。NTTは、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブな事業内容から、この低ボラティリティ銘柄の典型例と言えます。マルコム・ベイカーらの2011年の研究は、このアノマリーがなぜ存続するのかについて、多くの機関投資家がベンチマークとの乖離を抑えようとする制約や、個人投資家の宝くじ的な銘柄への選好といった、市場の構造的な要因と行動バイアスによって説明されることを示唆しています 。
この低ボラティリティという特性を、より体系的な収益機会へと昇華させた戦略が、アンドレア・フラッツィーニとラッセ・ペダーセンが2014年に提唱した「Betting Against Beta (BAB) ファクター」です 。この戦略の根底にある考え方は、レバレッジ(借り入れ)に制約のある多くの投資家が、高いリターンを求めて高ベータ(市場全体の値動きに敏感な)銘柄を過大評価し、買いすぎる傾向があるという点に着目します。その結果、高ベータ株のリスク調整後リターンは押し下げられます。一方で、レバレッジを利用できる投資家は、この価格の歪みを利用し、NTTのような低ベータ株をレバレッジをかけて買い持ちし、高ベータ株を売り持ちするポートフォリオを構築することで、市場の方向性に中立なまま、安定した超過リターンを狙うことができます。フラッツィーニとペダーセンの研究は、このBAB戦略が米国内外の株式市場や、債券、為替、コモディティといった多様な資産クラスにおいて、統計的に有意なプラスのリターンを生み出してきたことを実証しており 、NTT株が持つ低ベータという性質が、単なる防御的な特性に留まらず、学術的に裏付けられた「エッジ」の源泉となり得ることを示しています。
NTT株の短所:規制と市場心理という二重の圧力
NTT株が直面する最大の短所は、その出自に起因する規制リスクと、それに伴う市場のネガティブな心理です。現在進行中のNTT法改正の議論は、その象徴と言えます。この法改正の焦点の一つは、政府が現在も保有する約3分の1のNTT株の扱いです 。市場は、この巨大な株式が将来的に売却される可能性を常に意識しており、これは需給面での強力な売り圧力、すなわち「供給過剰懸念(オーバーハング)」として株価の上値を重くする要因となっています。企業のファンダメンタルズとは無関係に、巨大な売り手が控えているという事実そのものが、投資家心理を冷やし、株価の重石となっているのです。
この構造的な弱点が、具体的な損失として顕在化したのが、2024年5月に発表された2025年3月期の業績予想後の株価急落です 。この時、NTTは増収を見込みながらも、営業利益は大幅な減益となる見通しを示しました。このネガティブサプライズは、前述の政府保有株売却への懸念と相まって、投資家の売りを誘発し、株価は大きく下落しました 。これは、近年の投資家にとって最も分かりやすい損失事例と言えるでしょう。
しかし、このNTTの最近の不振は、低ボラティリティ・アノマリーそのものが機能しなくなったことを意味するわけではありません。むしろ、このアノマリーの本質を浮き彫りにしています。低ボラティリティ効果は、あくまで数十年にわたる統計的な「傾向」であり、短期的な株価の動きを保証するものではありません。NTTのケースが示すように、この長期的な統計的優位性は、業績悪化という強力なファンダメンタルズの変化や、法改正というイベントドリブンなリスクといった、個別企業固有の要因によって、短期的には容易に覆されてしまうのです。洗練された投資家にとっての教訓は、ファクターという追い風を理解しつつも、個別銘柄が持つ固有のリスクという向かい風を常に警戒する必要がある、ということに尽きます。
NTT株価について非対称性と摩擦の視点から
NTT株のAsymmetry:株価に織り込まれていない非対称な価値
NTTの企業価値を評価する上で、市場がまだ完全には織り込んでいない、非対称なプラスの要素が存在します。
第一に、その安定した配当政策がもたらす「配当クリエンテル効果」です。一般的に、配当は税制面で不利な場合が多いにもかかわらず、なぜ多くの企業が配当を支払い続けるのかは、金融における長年の謎でした。フランクリン・アレンらが2000年に発表した理論は、この謎を解く鍵として、機関投資家の存在を指摘しました 。彼らの理論によれば、配当は、税制上有利な機関投資家を株主として惹きつけるための「シグナル」として機能します。機関投資家は、その専門知識と規模から、個人投資家よりも企業の経営を監視する能力に長けています。したがって、企業はあえて税制上不利な配当を支払うことで、質の高い機関投資家という「監視役」を呼び込み、自社の経営の健全性を市場にアピールするのです。NTTの安定配当は、まさにこの理論を体現しており、質の高い株主層を形成するための非対称なシグナルとして機能しています。さらに、2023年の大規模な株式分割は、膨大な数の個人投資家という新たな株主層を生み出しました 。ボー・ベッカーらの2011年の研究は、特に退職後の高齢者層などが、地理的に近い企業の株を保有し、配当を強く選好する「ローカル配当クリエンテル」が存在することを示しています 。NTTの場合、NISA口座などを通じて全国に広がった新たな個人株主層が、この理論における「ローカル」な存在として、経営陣に対して安定配当を維持・向上させるよう、強力な圧力をかける存在となり、配当政策の安定性をさらに強固なものにしています。
第二に、IOWN構想に代表される研究開発投資がもたらす「非対称な成長オプション」です。市場はしばしば、研究開発(R&D)費用を単なるコストとして捉え、短期的な利益を圧迫する要因として嫌気します。しかし、学術研究は、R&D投資の価値が市場に過小評価されていることを一貫して示しています。バーク・レブとセオドール・スージアニスによる1996年の研究は、R&D投資が将来の株価リターンと正の相関を持つことを実証しました 。さらに、アレン・エバーハートらの2004年の研究では、R&Dを大幅に増加させた企業は、その後の長期的な株価および経営パフォーマンスが向上することが示されています 。NTTのIOWN構想への投資は、短期的な利益を犠牲にしているように見えますが、その本質は、将来の技術覇権を握るための「オプション」の購入です。もしこの構想が成功すれば、そのリターンは投下資本を遥かに上回る非対称なものとなり、現在の株価が織り込む悲観的なシナリオを覆すポテンシャルを秘めているのです。
NTT株のFriction:パフォーマンスを蝕む構造的な摩擦
一方で、NTTの株価の上昇を阻む、根深い構造的な「摩擦」も存在します。
最も代表的なものが、「ユニバーサルサービス責務(USO)」という規制上の摩擦です。これは、NTTが国営企業であった時代から引き継がれる法的義務であり、採算が取れない過疎地を含め、全国一律に通信サービスを提供するというものです 。この責務は、社会的な公平性を担保する一方で、NTTにとっては純粋な民間企業であれば負う必要のないコストを強制し、資本を非効率な分野に配分させるという、経営上の明確な摩擦として機能しています。学術的には、このような責務は市場の失敗を是正し社会全体の厚生を高める効果が議論される一方で 、企業レベルでは収益性を直接的に圧迫する要因となります。
もう一つ、近年注目すべきは、2023年の株式25分割がもたらした「流動性の摩擦」という、直感に反する現象です。一般的に、株式分割は投資単位を引き下げ、個人投資家の参入を促すことで流動性を高めると考えられています 。しかし、学術研究は、より複雑な実態を明らかにしています。ルスラン・ゴヤンコらの2009年の研究によれば、株式分割は長期的(12ヶ月以上)には流動性を改善させるものの、短期的(5〜12ヶ月)には、売買スプレッド(買値と売値の差)が拡大し、むしろ流動性を悪化させる傾向があることが示されています 。NTTの分割後の株価の不安定な動きの一部は、この短期的な流動性の摩擦によって説明できる可能性があります。多くの個人投資家の参入は、株主層を拡大する一方で、取引の「ノイズ」を増大させ、短期的な価格発見機能を非効率にするという、意図せざる摩擦を生み出したのかもしれません。
この株式分割がもたらした最も重要な帰結は、経営戦略における新たな摩擦の発生です。分割によって急増した個人株主層は、前述の通り、安定配当を強く志向する「配当クリエンテル」を形成しました。この株主層は、経営陣が配当を削減することに対して、極めて強い抵抗勢力となります。しかし、NTTの最大の非対称な成長機会は、巨額の資本投下を必要とするIOWN構想にあります。ここに、経営上の深刻なジレンマ、すなわち摩擦が生じます。短期的な株主還元を求める新たな株主層の期待と、長期的な成長のために内部留保を確保し再投資したいという経営の要請が、真っ向から衝突する可能性があるのです。今後、NTT経営陣がこの二つの相反する要求をいかに舵取りしていくかが、長期的な企業価値を決定づける上で、極めて重要な論点となるでしょう。
NTT株価分析の総括
NTT株(9432)の分析は、一企業の評価に留まらず、規制、歴史、市場アノマリー、そして投資家心理が織りなす複雑な力学を解明するプロセスです。以下に本稿の要点をまとめます。
- NTTは、そのディフェンシブな事業特性から、長期的に高いリスク調整後リターンをもたらす傾向がある「低ボラティリティ・アノマリー」の典型例です。これは、投資家にとっての構造的なエッジとなり得ます。
- しかし、この長期的なエッジは、NTT法改正に伴う政府保有株の売却懸念(供給過剰リスク)や、短期的な業績悪化といった、企業固有の強力な逆風によって、短期的には容易に打ち消されます。
- 企業の安定配当は、質の高い機関投資家を惹きつけ経営を監視させる「シグナル」として機能し、非対称な価値を生み出しています。2023年の株式分割は、この「配当クリエンテル」を個人投資家層にも拡大させました。
- 一方で、この新たな配当重視の株主層の期待と、IOWN構想のような巨額の長期投資の必要性との間で、経営戦略上の「摩擦」が生じる可能性があります。
- NTTの最大の非対称なポテンシャルは、短期的な利益を圧迫する研究開発投資、特にIOWN構想にあります。これが成功した場合、現在の市場評価を覆す破壊的な成長オプションとなり得ます。
| 要因 (Factor) | 内容 (Description) | 株価への影響 (Impact on Stock Price) | 関連する理論/概念 (Related Theory/Concept) |
| NTT法改正 (NTT Law Revision) | 政府保有株の売却可能性と研究開発義務の緩和。国際競争力強化が目的。 | 短期:供給過剰懸念による下落圧力(摩擦)。長期:経営自由度向上による上昇期待(非対称性)。 | 民営化企業のパフォーマンス理論 、規制の経済学 |
| 株式25分割 (1-for-25 Stock Split) | 投資単位を引き下げ、個人投資家の参入を促進。株主数が急増。 | 短期:流動性の短期的な悪化リスク(摩擦)。長期:流動性向上と株主層拡大による安定化期待。 | 株式分割の流動性効果 、シグナリング理論 |
| 業績・配当政策 (Earnings & Dividend Policy) | 2025年3月期は増収減益予想。一方で、安定的な増配を継続。 | 短期:減益予想による下落圧力。中長期:安定配当が株価を下支え。 | Post-Earnings Announcement Drift (PEAD), 配当クリエンテル効果 |
| IOWN構想 (IOWN Initiative) | 次世代光通信基盤への巨額な研究開発投資。 | 短期:研究開発費による利益圧迫要因(摩擦)。長期:成功時の破壊的成長ポテンシャル(非対称性)。 | 成長オプション理論、R&D投資と株価リターン |
| 低ボラティリティ特性 (Low-Volatility Characteristic) | 景気変動に強いディフェンシブ銘柄としての性質。 | 長期:リスク調整後リターンが市場を上回る傾向(エッジ)。 | 低ボラティリティ・アノマリー 、Betting Against Beta (BAB) |
用語集
低ボラティリティ・アノマリー (Low-Volatility Anomaly) 株式市場において、理論的な予測とは逆に、株価の変動性(ボラティリティ)が低い銘柄群が、高い銘柄群よりも長期的に高いリスク調整後リターンを上げる傾向があるという経験則。
Betting Against Beta (BAB) ファクター 低ベータ(市場感応度が低い)銘柄をレバレッジをかけて買い、高ベータ銘柄を売り持ちすることで、市場の方向性に中立なポートフォリオを構築する投資戦略。レバレッジ制約のある投資家の行動によって生じる価格の歪みを利用する。
配当クリエンテル効果 (Dividend Clientele Effect) 投資家が自らの税率や所得ニーズに応じて、特定の配当政策を持つ企業の株式を選好し、結果として企業の株主層(クリエンテル)が形成されるという理論。
ユニバーサルサービス責務 (Universal Service Obligation) 通信事業者が、採算性に関わらず、全国一律の条件で基本的な通信サービスを提供することを義務付ける法的な制度。NTTが国営企業であった時代から引き継ぐ規制上の制約。
非対称なペイオフ (Asymmetric Payoff) 投資における潜在的なリターンが、潜在的な損失よりも著しく大きい(またはその逆の)状況。研究開発投資は、失敗すれば投資額を失うが、成功すれば莫大なリターンを生む可能性があるため、非対称なペイオフを持つ。
摩擦 (Friction) 理論通りに市場が機能することを妨げる、手数料、税金、規制、情報格差などの現実世界の障害要因の総称。リターンの獲得を阻害する要因となる。
株式分割 (Stock Split) 1株を複数の株式に分割し、発行済み株式数を増やすこと。株価が下がるため、投資家が買いやすくなる効果があるが、企業価値そのものは変わらない。
IOWN構想 (IOWN Initiative) NTTが推進する、現在のインターネットの限界を超える、光技術をベースとした次世代の革新的な情報通信基盤構想。
NTT法 (NTT Act) 日本電信電話株式会社の事業範囲、政府による株式保有、研究成果の開示義務などを定めた法律。現在、その見直しが議論されている。
リスク調整後リターン (Risk-Adjusted Return) リターンの絶対額だけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを取ったかを考慮に入れたリターンのこと。シャープレシオなどが代表的な指標。
NTT株価のアノマリー・エッジ研究のためのアクション
すぐにできること
NTT株の現状を評価するために、まずはその配当利回りに注目すべきです。現在の利回りを、過去の平均水準や、他の大手通信キャリア、あるいは高配当株として知られる他業種の銘柄と比較します。これにより、現在の株価が配当価値の観点から割安か割高かを判断する一つの材料となります。同時に、株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)といった基本的なバリュエーション指標を、NTT自身の過去5年間のレンジと比較し、現在の株価が歴史的に見てどの水準にあるかを客観的に把握することが重要です。
時間をかけてじっくり取り組むこと
長期的な視点からは、二つの大きな変動要因を継続的に監視する必要があります。第一に、NTT法改正の進捗です。国会での議論や政府の方針発表を注視し、政府保有株の売却が具体的にどのようなスケジュールと方法で進められるのかを見極めることが、需給面での最大のリスクを管理する上で不可欠です。第二に、IOWN構想の進展です。これはNTTの将来を左右する最大の非対称な機会であるため、定期的な技術開発のマイルストーン達成のニュースや、実用化に向けた提携企業の発表などを追い、この壮大な構想が単なる「夢物語」で終わるのか、それとも現実的な収益源へと繋がりそうなのかを長期的に評価していくべきです。
参考文献一覧
- Megginson, W. L., Nash, R. C., & van Randenborgh, M. (1994). The financial and operating performance of newly privatized firms: An international empirical analysis. The Journal of Finance, 49(2), 403–452.
- Baker, M., Bradley, B., & Wurgler, J. (2011). Benchmarks as limits to arbitrage: Understanding the low-volatility anomaly. Financial Analysts Journal, 67(1), 40–54.
- Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), 1–25.
- Allen, F., Bernardo, A. E., & Welch, I. (2000). A theory of dividends based on tax clienteles. The Journal of Finance, 55(6), 2499–2536.
- Becker, B., Ivković, Z., & Weisbenner, S. (2011). Local dividend clienteles. The Journal of Finance, 66(2), 655–684.
- Lev, B., & Sougiannis, T. (1996). The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D. Journal of Accounting and Economics, 21(1), 107-141.
- Eberhart, A. C., Maxwell, W. F., & Siddique, A. R. (2004). An examination of long-term abnormal stock returns and operating performance following R&D increases. The Journal of Finance, 59(2), 623-650.
- D’souza, J., & Megginson, W. L. (1999). The financial and operating performance of privatized firms during the 1990s. The Journal of Finance, 54(4), 1397-1438.
- Goyenko, R. Y., Holden, C. W., & Ukhov, A. D. (2009). Do stock splits improve liquidity?. Journal of Financial Economics, 92(1), 98-114.
- Cremer, H., Gasmi, F., Grimaud, A., & Laffont, J. J. (2001). The economics of universal service: Theory. The Economic Journal, 111(473), 319-339.
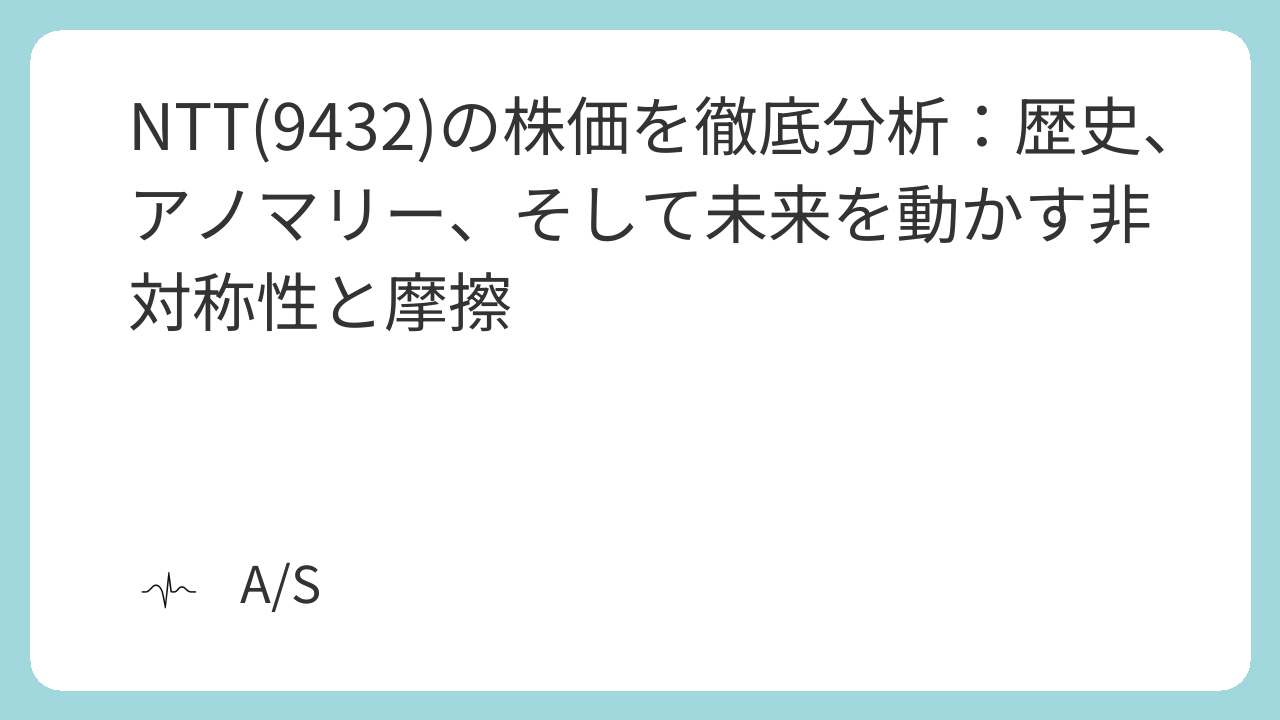
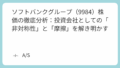
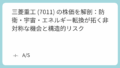
コメント