インデックス投資は、S&P 500のような特定の株価指数に連動することを目指す、シンプルで低コストな投資手法として広く普及しています。多くの投資家にとって、それは市場の平均的なリターンを得るための「自動運転」のような、受動的で賢明な選択と見なされています。しかし、この自動運転車の台数が増え続けることで、道路全体の交通の流れ、つまり市場そのものの性質が変化し始めているとしたらどうでしょうか。インデックス投資の爆発的な普及は、決して市場に中立な行為ではなく、価格形成や企業行動に無視できない「歪み」を生じさせている可能性が、数多くの学術研究によって指摘されています。
この問題の根源には、株式に対する需要の性質があります。もし株式の価格がその本質的価値だけで決まるのであれば、需要の増減は価格に影響を与えないはずです。しかし、Andrei Shleiferが1986年の論文で示したように、現実の株式市場では、ある銘柄を買いたい人が増えれば、その銘柄の価格は上昇します [1]。これは、株式の需要曲線が右下がりであることを意味します。インデックスファンドが指数への採用を理由に特定の銘柄を機械的に購入するとき、その銘柄のファンダメンタルズに何の変化がなくても、この需要の増加が株価を押し上げるのです [1]。Jeffrey Wurglerは2011年の研究で、このようなインデックス投資への連動がもたらす経済的な帰結について警鐘を鳴らしています [2]。
インデックス投資が市場に与える影響は、もはや無視できるものではありません。WurglerとZhuravskayaの2002年の研究は、このような需要の変化によって生じた価格の歪みを、裁定取引がいかに修正しきれないかを示しました [3]。さらに近年の研究では、ETF(上場投資信託)の保有率が高い銘柄ほど、その株価のボラティリティ(変動性)が高まる傾向にあることも明らかにされています [4]。また、その影響は株価だけにとどまりません。インデックスファンドを運用する巨大なパッシブ運用会社が、投資先企業の議決権を行使することで、企業の経営方針、すなわちコーポレートガバナンスにまで大きな影響を及ぼし始めているのです [5]。この記事では、こうした学術的な知見に基づき、インデックス投資の自動運転が市場にどのような歪みをもたらしているのかを解き明かしていきます。
インデックス投資の普及がもたらす市場の変化
なぜインデックス投資の「歪み」が重要なのか
インデックス投資が市場に与える歪みを理解することは、現代の投資家にとって極めて重要です。なぜなら、市場の大部分が「自動運転」モードで動いていることを知らなければ、個々の銘柄や市場全体の動きを正しく解釈することができないからです。
例えば、ある企業の株価が上昇したとき、その背景には優れた新製品の発表や好調な決算があるのかもしれません。しかし、現代の市場では、その企業が主要な株価指数に新規採用されたという、企業価値とは無関係な理由だけで株価が大きく上昇する現象が頻繁に起こります。これは、指数に連動するためにインデックスファンドが一斉にその銘柄を買い入れるからです [1]。このメカニズムを知らなければ、投資家は株価上昇を企業のファンダメンタルズが改善した証拠だと誤解し、割高な価格で投資してしまう可能性があります。
歪みを知らないことのリスクと知ることのメリット
この歪みを知らない最大のリスクは、市場価格が常に企業の真の価値を反映しているという幻想を抱いてしまうことです。Wurglerの研究が示すように、同じ指数に組み入れられている銘柄は、それぞれの企業の業績とは関係なく、一緒に値動きする傾向(コ・ムーブメント)が強まります [2]。市場全体が下落する局面では、優良企業もそうでない企業も、インデックス売りによって一蓮托生で売られてしまうのです。
一方で、この歪みの存在を理解していれば、それを逆手にとることも可能です。例えば、指数から除外されることが決まった銘柄は、そのファンダメンタルズに関わらず、インデックスファンドからの機械的な売却圧力にさらされます。その結果として株価が過剰に下落したタイミングを、長期的な視点を持つ投資家は絶好の買い場と捉えることができるかもしれません。市場の非効率性を生み出す歪みは、見方を変えれば、そこに新たな投資機会が眠っていることを示唆しているのです。
利益例と損失例
インデックス投資がもたらす歪みは、具体的な利益や損失に直結します。
利益例としては、株価指数への新規採用を予測する戦略が挙げられます。例えば、S&P 500に採用される銘柄には時価総額や収益性などの基準があります。これらの基準を満たし、近々採用される可能性が高い銘柄を事前に特定し投資しておくことで、正式な採用発表後にインデックスファンドからの大量の買い需要が発生し、株価が上昇する恩恵を受けることが期待できます。これはまさに、Shleiferが示した需要の変化が価格を動かす効果を狙ったものです [1]。
損失例としては、その逆のケースが考えられます。ある銘柄が指数から除外された場合、インデックスファンドはその銘柄を機械的に売却しなければなりません。これにより、企業の業績とは無関係に株価は下落圧力を受けます。もし投資家がその銘柄を保有しており、このメカニズムを知らなければ、突然の株価下落にうろたえ、不必要な損失を被る可能性があります。また、インデックスに含まれる人気銘柄に集中投資している場合、そのインデックス全体が売られる局面では、個別企業の価値とは関係なく大きな損失を被るリスクがあります。
インデックス投資に潜む非対称性と摩擦
Asymmetry:価格を問わない買い手という非対称性
市場におけるインデックス投資の最大の特徴は、その投資行動が価格に鈍感である、という点にあります。これが市場に存在する根本的な非対称性の源泉です。
アクティブ投資家は、企業の価値を分析し、現在の株価が割安か割高かを判断して売買を行います。彼らは価格に敏感な参加者です。一方、インデックスファンドは、指数に連動するという唯一の目的のために、構成銘柄の株価が割高であろうと、市場全体が過熱していようと、機械的に買い続けます。彼らは価格に鈍感な参加者です。
この「価格を問わない買い手」と「価格を吟味する買い手」の間の非対称性が、市場に歪みを生み出します。指数に採用された銘柄に対して、インデックスファンドという巨大な買い手が、価格を問わずに需要を生み出し続けることで、株価は本来あるべき水準から乖離していく可能性があります [1, 2]。この乖離は、価格に敏感なアクティブ投資家にとっては、裁定取引の機会を提供します。
Frictions:裁定取引の限界という摩擦
市場に価格の歪みが生まれても、効率的な市場であれば、裁定取引者(アービトラージャー)がすぐにその歪みを修正するはずです。例えば、インデックスへの採用によって過大評価された銘柄があれば、裁定取引者はその銘柄を空売りすることで、価格を適正水準に戻そうとします。
しかし、現実の市場には、この裁定取引を困難にする様々な「摩擦」が存在します。WurglerとZhuravskayaの研究が示すように、裁定取引にはリスクが伴います [3]。インデックス買いの勢いが予想以上に長く続けば、空売りした裁定取引者は大きな損失を被るかもしれません。また、裁定取引を行うには資金や担保が必要であり、そのコストも摩擦となります。
このように、理論上は修正されるべき価格の歪みが、裁定取引の限界という摩擦によって、長期間にわたって市場に残り続けることがあります。インデックス投資の規模が大きくなればなるほど、この歪みを生み出す力は強まり、それを修正しようとする裁定取引の力を上回ってしまうのです。
インデックス投資の知識を投資に活かすための具体的なアクション
すぐできること
インデックス投資が市場に与える影響を理解した上で、すぐに行動に移せることはいくつかあります。
まず、自身が保有している、あるいは関心のある銘柄が、どの主要な株価指数に含まれているかを把握することです。そして、その指数の定期的な銘柄入れ替えがいつ行われるかを意識するだけでも、株価の不可解な動きに対する理解が深まります。ある日の株価変動が、企業固有のニュースではなく、指数関連のフローによるものかもしれない、という視点を持つことが重要です。
また、市場全体の動きを見る際にも、特定の大型株が指数全体に与える影響の大きさを認識する必要があります。特に、時価総額加重平均型のインデックスでは、少数の巨大企業の株価動向が、指数全体のパフォーマンスを大きく左右しているという事実を理解しておくべきです。
長期的に取り組むこと
長期的な資産形成の観点からは、インデックス投資の歪みを踏まえた上で、より洗練された戦略を検討することが推奨されます。
一つの方向性として、S&P 500のような伝統的な時価総額加重指数への集中を避け、ポートフォリオを多様化させることが挙げられます。例えば、全銘柄を均等な比率で組み入れる均等加重指数や、特定のファクター(バリュー、グロースなど)に着目したスマートベータ指数などを組み合わせることで、特定の巨大銘柄の値動きにポートフォリオ全体が振り回されるリスクを低減できます。
さらに、インデックス投資の普及は、皮肉にも、個別企業の詳細なファンダメンタルズ分析の価値を高める可能性があります。市場の大部分が企業の価値を問わずに売買を行うようになることで、企業の本質的な価値と株価の間に生まれた歪みを見つけ出すことに、より大きなリターンが期待できるかもしれないからです。また、Appelらの研究が示すように、パッシブ運用会社は「物言わぬ株主」ではなく、投資先企業の経営に積極的に関与するようになっています [5]。投資先の企業が、これらの巨大なパッシブ株主とどのような関係を築いているかを分析することも、長期的な企業価値を評価する上で新たな視点となるでしょう。
総括
- インデックス投資は、市場に対して中立な行為ではなく、その普及が市場に様々な「歪み」をもたらしています。
- インデックスファンドは、構成銘柄を価格に鈍感に売買するため、企業のファンダメンタルズとは無関係な価格変動を生み出す要因となります [1]。
- 指数に採用された銘柄群は、本来の企業価値とは関係なく、市場全体の値動きに連動しやすくなる「コ・ムーブメント」という現象が強まります [2]。
- ETFの普及は、特にその構成銘柄の株価ボラティリティを増大させる傾向があることが指摘されています [4]。
- 裁定取引には限界やリスクといった「摩擦」が存在するため、インデックス投資によって生じた価格の歪みは、簡単には修正されずに市場に残り続けます [3]。
- パッシブ運用会社は、その巨大な議決権を通じて投資先企業の経営(コーポレートガバナンス)に大きな影響力を持つ存在となっています [5]。
用語集
インデックスファンド S&P 500や日経平均株価のような特定の株価指数の動きに連動する投資成果を目指す投資信託。
ETF(上場投資信託) 証券取引所に上場しており、株式と同様に売買できる投資信託のこと。多くは株価指数などの指標に連動するインデックス型である。
裁定取引(アービトラージ) 同一の価値を持つ商品間で価格差が生じた際に、割高な方を売り、割安な方を買うことで、リスクなく利益を確定させようとする取引。
コ・ムーブメント 複数の資産価格が、それぞれの個別の要因とは関係なく、同じ方向に動く傾向のこと。
需要曲線 ある商品の価格と、消費者がその価格で購入したいと考える量(需要量)との関係を示したグラフ。通常、価格が下がるほど需要量は増えるため、右下がりの曲線となる。
コーポレートガバナンス 企業経営を監視・規律する仕組みのこと。株主の利益を最大化するために、経営者の不正を防ぎ、効率的な経営が行われるよう監督することを指す。
参考文献一覧
[1] Shleifer, A. (1986). Do Demand Curves for Stocks Slope Down?. The Journal of Finance, 41(3), 579–590.https://doi.org/10.2307/2328486
[2] Wurgler, J. (2011). On the Economic Consequences of Index-Linked Investing. American Economic Review, 101(3), 418–422.https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1667188
[3] Wurgler, J., & Zhuravskaya, E. (2002). Does Arbitrage Flatten Demand Curves for Stocks?. The Journal of Business, 75(4), 583–608.https://doi.org/10.1086/341636
[4] Ben-David, I., Franzoni, F., & Moussawi, R. (2018). Do ETFs Increase Volatility?. The Journal of Finance, 73(6), 2481-2535.https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1967599
[5] Appel, I. R., Gormley, T. A., & Keim, D. B. (2016). Passive Investors, Not Passive Owners. Journal of Financial Economics, 121(1), 111-141.https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.03.003
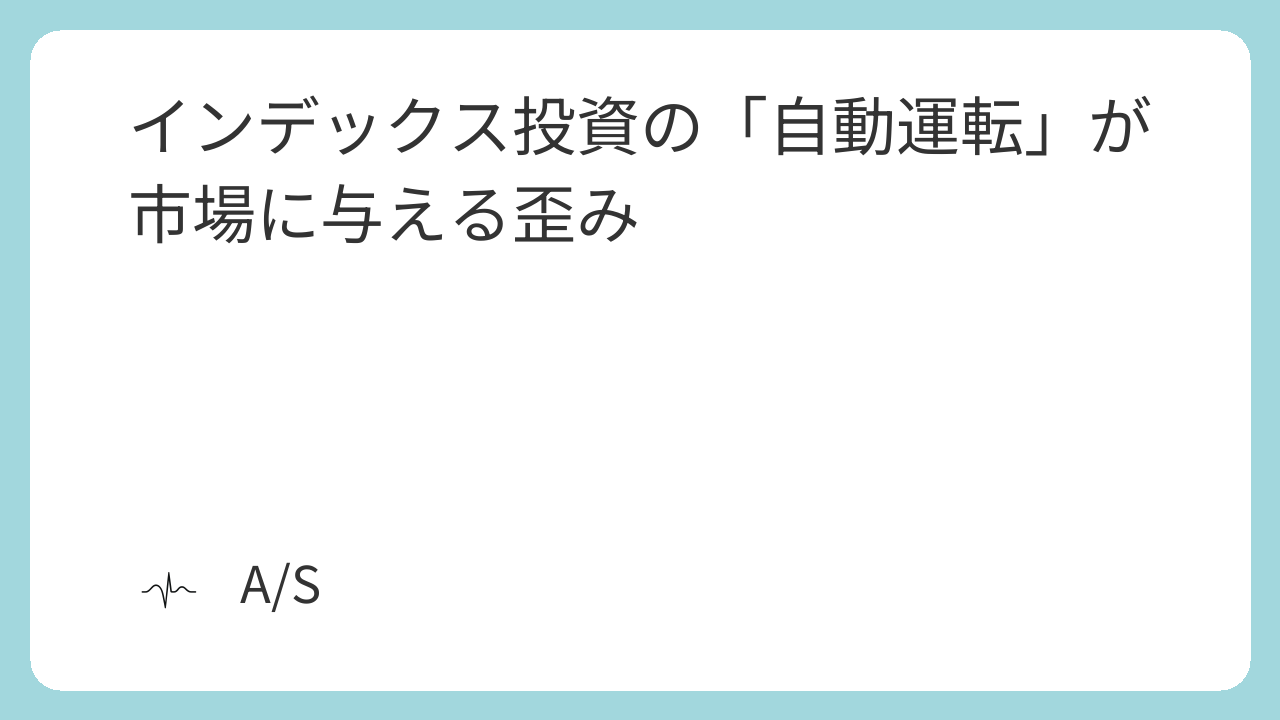
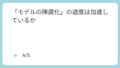
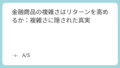
コメント