投資の世界における意思決定のプロセスは、大きく二つのアプローチに分類されます。一つは、事前に定義された厳格なルールに基づき、感情を排して機械的に取引を行うシステマティック戦略。もう一つは、ファンダメンタルズ分析、市場の雰囲気、地政学リスクといった多様な情報を基に、人間の経験と直感、すなわち裁量によって判断を下す裁量戦略です。この二つのアプローチを巡り、「人間の判断を超えるシステムは存在するのか」、あるいは「システムでは捉えきれない市場の機微を人間は読み解けるのか」という問いは、長年にわたり投資家の間で議論されてきました。
システマティック戦略、特にマネージドフューチャーズに代表されるトレンドフォロー戦略は、その有効性が学術的にも広く研究されています。例えば、Moskowitzらの研究では、株式インデックス、通貨、コモディティ、債券といった多様な資産クラスにおいて、過去12ヶ月のリターンがプラスの資産を買い、マイナスの資産を売るという単純な「時系列モメンタム」戦略が、長期間にわたり有意なリターンを生み出してきたことが示されています [5]。このような戦略は、人間の行動バイアスを利用し、規律ある執行を通じて利益を積み上げることを目指します。
一方で、市場は常に変化し、過去のデータからは予測不能な新しい現象が発生します。このような局面では、ルールベースのシステマティック戦略が機能不全に陥る可能性があり、経験豊富な人間の裁量判断が優れた結果をもたらすことも考えられます。実際に、プロの通貨マネージャーのパフォーマンスを調査した研究では、そのスキルがリターンの源泉となっている可能性が示唆されています [3]。
この記事では、「システマティック戦略は裁量戦略より常に優れているのか」という根源的な問いに迫ります。まず両戦略の基本的な概念とその重要性を解説し、それぞれの長所と短所を具体的な例を交えて探ります。さらに、本メディア独自の視点である「非対称性」と「摩擦」の観点から、各戦略の収益の源泉と、その利益を阻害する要因を解き明かします。最終的に、この知識を投資家が自身の投資スタイルを確立するためにどう活かすべきか、具体的なアクションを提示します。
投資アプローチの選択:システマティック戦略と裁量戦略の重要性
なぜアプローチの選択が重要なのか
投資における成功は、単に「何を買うか」だけでなく、「どのように意思決定するか」に大きく依存します。システマティック戦略と裁量戦略は、この意思決定の根幹をなす哲学であり、どちらを選択するかは投資家のパフォーマンス、リスク許容度、そして精神的な負担にまで影響を及ぼします。システマティック戦略は、感情的な判断ミスを排除し、検証可能なルールに基づいて一貫した行動を保証します。一方、裁量戦略は、モデルでは捉えきれない質的な情報や、市場の構造変化に柔軟に対応できる可能性を秘めています。自身のアプローチを明確に理解し、選択することは、長期的に市場で生き残るための第一歩です。
アプローチを理解しないことのリスク
自身がどちらのアプローチに依拠しているかを理解しないまま投資を行うことは、重大なリスクを伴います。例えば、裁量的な判断を下しているにもかかわらず、都合の良いデータだけを見て「システムに従っている」と自己正当化してしまうことがあります。これは、損失を出した際に自分の判断ミスを認められず、損切りを遅らせる原因となります。逆に、システマティック戦略を採用しているにもかかわらず、市場の短期的な変動に不安を覚え、ルールを破って途中で介入してしまうこともあります。これは「システムを信じきれない」という矛盾であり、戦略が本来持つはずのエッジを自ら破壊する行為に他なりません。
各戦略における利益例と損失例
利益例として、システマティックなトレンドフォロー戦略が挙げられます。2008年の金融危機のような大きな市場トレンドが発生した際、この戦略は下落する株式などの資産を売り持ち(ショート)にし、安全資産として上昇する債券などを買い持ち(ロング)にすることで、多くの投資家が損失を出す中で大きな利益を上げることができました [4]。これは、事前に定められたルールに従い、感情に流されずにトレンドを追い続けた結果です。
一方で損失例として、同じくシステマティック戦略が、明確なトレンドのない方向感の乏しい市場で機能しなくなるケースがあります。このような市場では、小さな価格変動によって売買シグナルが頻繁に発生し、その都度小さな損失を積み重ねてしまう「Whipsaw(往復びんた)」と呼ばれる状況に陥ります。裁量戦略の損失例としては、一人のカリスマ的なファンドマネージャーが自身の相場観に固執し、市場が発する明らかな警告サインを無視した結果、巨額の損失を計上するケースが歴史上繰り返されています。
パフォーマンスの源泉と市場環境への適応
システマティック戦略のリターン特性
システマティック戦略、特にヘッジファンドが用いるダイナミックな取引戦略のリターン分布は、正規分布から大きく外れた特徴を持つことが知られています [1]。例えば、トレンドフォロー戦略の月次リターンは、多くの期間でゼロ近辺に集中する一方で、ごく稀に非常に大きなプラスのリターン、あるいはマイナスのリターンを生み出す傾向があります。これは、オプションの買い戦略の損益プロファイルに似ており、トレンドが発生しない期間は小さなコスト(損失)を払い続け、一度大きなトレンドが発生した際に大きな利益を獲得する、という性質を持っています [2]。この特性を理解することは、システマティック戦略の長期的な有効性を評価する上で不可欠です。
裁量戦略のスキルとアルファ
裁量戦略の成功は、マネージャーの「スキル」に大きく依存します。このスキルは、情報の収集・分析能力、市場心理の読解力、そしてリスク管理能力など、多岐にわたります。プロの通貨マネージャーのパフォーマンスを分析した研究によれば、彼らが生み出すリターンの一部は、システマティックな要因だけでは説明できず、マネージャーの裁量的な判断、すなわちスキルに起因する可能性が示唆されています [3]。優れた裁量トレーダーは、システマティックモデルが定量化できないような、政治的イベントや規制の変更といった質的情報をリターンに変えることができるのです。
市場環境による優劣の変化
システマティック戦略と裁量戦略のどちらが優れているかは、市場の環境、すなわち「レジーム」によって変化します。大規模な金融緩和や財政出動によって一方向のトレンドが形成されやすい市場では、トレンドフォローなどのシステマティック戦略が優位に立つ傾向があります。一方で、中央銀行の政策変更や突発的な地政学リスクなど、市場の前提が覆るような局面では、過去のデータに依存するシステマティック戦略が機能しなくなり、状況の変化をいち早く察知し適応できる裁量マネージャーが優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。
投資戦略に潜む非対称性と摩擦
非対称性:収益機会の源泉
システマティック戦略における収益機会の非対称性は、市場参加者の行動バイアスに根差しています。例えば、時系列モメンタム戦略が有効なのは、投資家が新たな情報に対して初期には過小反応し、その後トレンドが明確になると追随していくという、体系的な遅れを利用しているためです [5]。システムは、この人間の非合理的な行動パターンを、感情なく、疲れ知らずで繰り返し利用することでエッジを得ます。一方、裁量戦略における非対称性は、情報の解釈能力にあります。優れた裁量マネージャーは、公開されている膨大な情報の中から、他の市場参加者がまだ価値を認識していない重要な情報を見出し、それを独自の分析によって利益機会へと結びつけます。これは、システムには模倣困難な、人間ならではの洞察力に由来する非対称性です。
摩擦:利益を阻害する要因
システマティック戦略が直面する主要な「摩擦」は、取引コストとモデルの陳腐化です。戦略が売買シグナルを生成するたびに、スプレッドや手数料といった取引コストが発生し、リターンを侵食します。また、市場の構造変化によって、過去のデータで有効だったルール(モデル)が将来的にも機能する保証はなく、常に陳腐化のリスクに晒されています。裁量戦略における最大の摩擦は、言うまでもなくマネージャー自身の行動バイアスです。人間は、自信過剰になって過大なリスクを取ったり、損失を確定させたくないという心理から損切りを遅らせたり(損失回避バイアス)、多数派の意見に流されたり(ハーディング)する傾向があります。これらの心理的な罠が、合理的な判断を妨げ、パフォーマンスを悪化させる最大の収益阻害要因となります。
自身の投資アプローチを確立するためのアクション
すぐできること
まず、自身の性格や思考の癖を客観的に分析することから始めましょう。あなたは感情の波に左右されやすいタイプでしょうか、それとも規律を守り、データに基づいた判断を得意とするタイプでしょうか。過去の自分の投資行動を振り返り、成功した取引と失敗した取引の意思決定プロセスを書き出してみてください。そこに、裁量的な判断がうまく機能したのか、それとも感情的なミスが多かったのか、あなたの投資家としての特性を見出すヒントが隠されています。
長期的に取り組むこと
長期的な目標として、システマティックな思考と裁量的な判断を融合させる「ハイブリッドアプローチ」の構築を目指すことを推奨します。例えば、システマティックな分析ツールを用いて投資候補となる銘柄群をスクリーニングし、その中から最終的な投資対象を自身の裁量的な分析(企業の競争優位性や経営者の質など)に基づいて決定する、といった方法です。また、ポートフォリオの一部をシステマティック戦略で運用し、別の一部を裁量戦略で運用するなど、異なるアプローチを組み合わせることで、特定の市場環境への依存度を下げ、より安定したリターンを目指すことも有効な手段となります。
総括
- 投資戦略は、ルールに基づく「システマティック戦略」と、人間の判断による「裁量戦略」に大別されます。
- どちらか一方が「常に」優れているわけではなく、それぞれに長所と短所、そして得意な市場環境が存在します。
- システマティックなトレンドフォロー戦略は、長期的に有効なリターンを生むことが学術的に示されていますが [4, 5]、トレンドのない市場では機能しにくい特性を持ちます [2]。
- 優れた裁量マネージャーは、モデルでは捉えきれない質的情報を分析する「スキル」によって、システマティックな要因を超えるリターンを生み出す可能性があります [3]。
- システマティック戦略の収益は市場参加者の行動バイアスを源泉とし、裁量戦略の収益はマネージャーの情報解釈能力に由来するという非対称性があります。
- 一方で、システマティック戦略は取引コストとモデル陳腐化、裁量戦略は行動バイアスという「摩擦」をそれぞれ抱えています。
- 投資家は自身のリスク許容度や性格を理解し、両アプローチの長所を組み合わせる視点を持つことが重要です。
用語集
- システマティック戦略 事前に定義された明確なルールやアルゴリズムに基づき、機械的かつ客観的に投資判断を行う戦略。感情の介入を排除することを目的とする。
- 裁量戦略 市場データ、経済ニュース、地政学リスクなどの多様な情報を基に、投資家自身の経験、直感、分析に基づいて主観的に投資判断を行う戦略。
- トレンドフォロー戦略 市場に発生した価格トレンド(上昇または下落)を識別し、その方向に追随してポジションを取る投資戦略。システマティック戦略の代表例の一つ。
- 時系列モメンタム 個別の資産の過去のリターン(勢い)に基づいて投資判断を行う戦略。過去のリターンがプラスであれば買い、マイナスであれば売るというルールを用いる。クロスセクション・モメンタムとは区別される。
- 行動バイアス 人間が意思決定を行う際に、経験則や先入観、感情などによって非合理的な判断を下してしまう心理的な傾向のこと。プロスペクト理論などが有名。
- マネージドフューチャーズ CTA(商品投資顧問業者)が、主に先物市場でトレンドフォロー戦略などを用いて運用する投資商品の総称。
参考文献一覧
[1] Fung, W., & Hsieh, D. A. (1997). Empirical characteristics of dynamic trading strategies: The case of hedge funds. The Review of Financial Studies, 10(2), 275-302.https://doi.org/10.1093/rfs/10.2.275
[2] Fung, W., & Hsieh, D. A. (2001). The risk in hedge fund strategies: Theory and evidence from trend followers. The Review of Financial Studies, 14(2), 313-342.https://doi.org/10.1093/rfs/14.2.313
[3] Pojarliev, M., & Levich, R. M. (2008). Do professional currency managers beat the benchmark?. Financial Analysts Journal, 64(5), 18-32.https://doi.org/10.3386/w13714
[4] Hurst, B., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2013). Demystifying managed futures. SSRN Working Paper No. 2179772.https://ssrn.com/abstract=2333776
[5] Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. Journal of Financial Economics, 104(2), 228-250.https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.003
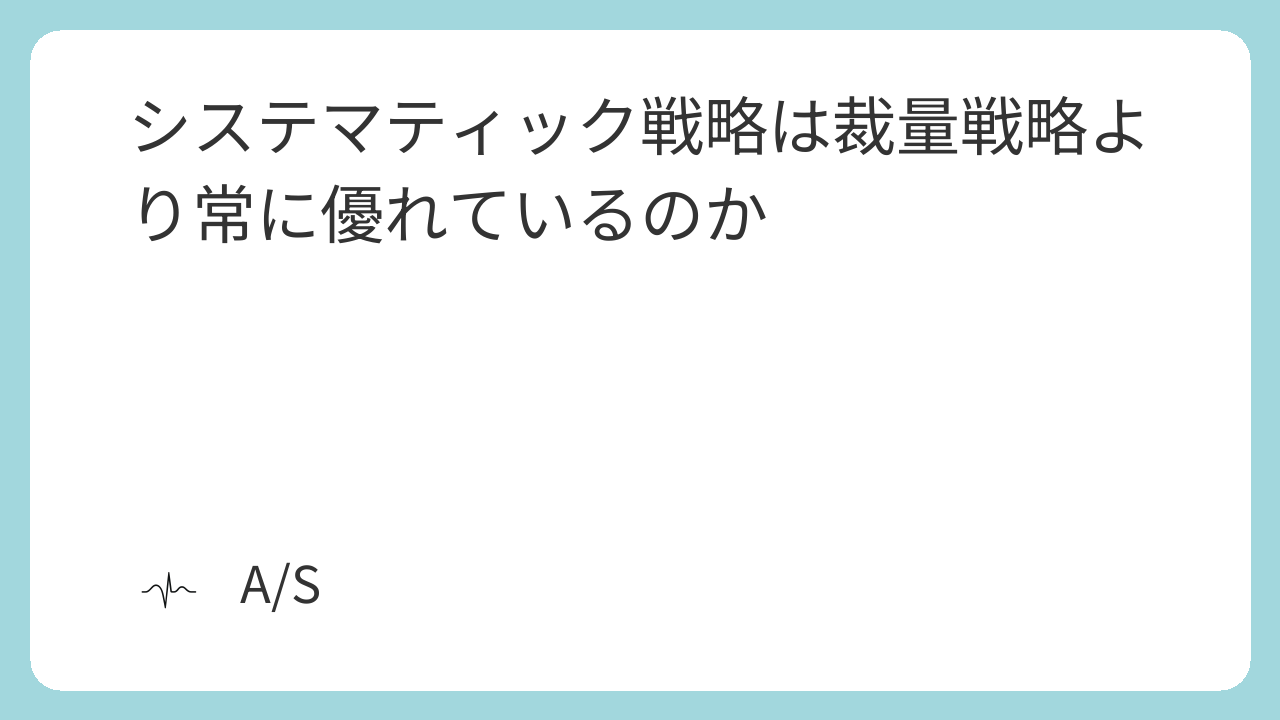
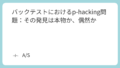
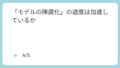
コメント