将来の価値が不確実な資産、例えば株のオプションの「公正な価格」は、一体どのように決まるのでしょうか。一つの素朴な考えは、株価が上がる現実の確率と下がる現実の確率を予測し、期待される将来の利益を計算して、それを現在価値に割り引く、というものです。しかし、この方法には根本的な難問が付きまといます。それは、「適切な割引率とは何か?」という問題です。リスクのある資産の割引率は、リスクのない資産の金利(リスクフリーレート)に、リスクに対する上乗せ分(リスクプレミアム)を加える必要がありますが、このリスクプレミアムを正確に知ることは誰にもできません。
この難問を、驚くべき発想で解決するのが「リスク中立確率」の概念です。これは、私たちが現実に観測している確率(物理的確率)とは異なる、資産価格を評価するためだけに作られた「架空の確率」です。この架空の世界では、全ての投資家がリスクに対して中立的、つまりリスクを取ることに追加的なリターンを要求しないと仮定されます。その結果、この世界では全ての資産の期待リターンが、安全資産のリターンであるリスクフリーレートと等しくなります。
このような非現実的な仮定を置くことで、私たちはリスクプレミアムという厄介な問題を計算から完全に消し去り、デリバティブ(金融派生商品)の価格を客観的に、一意に決定することができるのです。この一見奇妙なアイデアは、市場に「裁定機会(リスクなく利益を確定できる機会)は存在しない」という、現代ファイナンスの最も基本的な原則に深く根差しており、厳密な数学的理論によって支えられています [1, 2]。
この記事では、デリバティブ価格理論の心臓部とも言えるリスク中立確率の本質と、その背景にある無裁定理論、そしてこの強力なツールを投資家がどう理解すべきかを徹底的に解説します。
リスク中立確率がデリバティブ価格の鍵を握る
なぜこの架空の確率が、現実の金融市場で取引される商品の価格を決める上で、これほどまでに中心的な役割を果たすのでしょうか。その理由は、リスク中立確率が「裁定機会の不在」という市場の鉄則と表裏一体だからです。
リスク中立確率を知らないことのリスク
この概念を理解せずにデリバティブ取引に臨むことは、羅針盤なしで航海に出るようなものです。投資家は、自分自身の主観的な相場観、つまり「現実の確率」に基づいてオプションの価値を過大または過小に評価してしまう危険性があります。例えば、「この株は絶対に上がるはずだ」という強い思い込みから、オプションの本質的な価値(無裁定価格)を無視して取引を行い、結果的に市場の合理性に打ち負かされて損失を被ることになりかねません。オプションの価格は、市場参加者の将来予測の平均ではなく、無裁定の原理によって数学的に決定されているのです。
利益例:裁定機会のない「公正な価格」の発見
リスク中立確率の力を最も単純な形で示したのが、コックス、ロス、ルービンシュタインによって開発された二項オプション価格モデルです [5]。
現在100円の株価が、次の期に120円に上昇するか、90円に下落するかのどちらかだとします。この株を原資産とする、行使価格100円のコールオプション(買う権利)の価値はいくらになるでしょうか。リスク中立の考え方では、上昇・下落の「現実の確率」は一切使いません。代わりに、このオプションの将来の価値(上昇すれば20円、下落すれば0円)を、原資産である株式と安全資産(例えば国債)の組み合わせで完全に再現(複製)できるポートフォリオを考えます。
この複製ポートフォリオを作るために必要な現在のコストを計算すると、それがオプションの唯一の「公正な価格」となります。もしオプションの市場価格がこの価格からずれていれば、誰もがリスクなく利益を上げられる裁定取引が可能になってしまうからです。そして、この計算を成立させている背後の確率こそが、リスク中立確率なのです。
損失例:主観的確率による誤った価格評価
ある投資家が、独自の分析に基づき、前述の株価が上昇する「現実の確率」は70%だと強く信じているとします。彼はこの70%という主観的な確率を用いてオプションの期待価値を計算し、「このオプションは本来もっと価値があるはずだ」と結論付け、市場で取引されている価格を割安だと判断して大量に購入しました。しかし、市場価格は、現実の確率がどうであれ、裁定機会が存在しないように決まる唯一の価格です。結局、株価は期待通りには動かず、この投資家は主観と客観的な価格とのギャップによって損失を被りました。これは、市場の価格形成メカニズムを誤解した典型的な失敗例です。
無裁定理論とマルチンゲール理論の深いつながり
リスク中立確率という概念は、単なる便利な計算トリックではありません。それは、「資産価格の基本定理」として知られる、現代ファイナンス理論の最も深遠な結果の一つに結びついています。
資産価格の基本定理
この定理は、極めてエレガントな形で、市場の健全性と資産価格評価の数学的構造を結びつけます。非常に簡潔に言うと、この定理は以下の二つの要素から成り立っています。
- 市場に裁定機会が存在しないことと、リスク中立確率(専門的には同値マルチンゲール測度)が存在することは、数学的に等価である。
- 市場が「完備(あらゆる金融商品のリスクを既存の資産で完全にヘッジできる)」であるならば、リスク中立確率は一意に定まり、あらゆるデリバティブの価格が裁定によって一意に決まる。
この定理は、ハリソン、クレプス、プリスカといった研究者たちの貢献によって確立され [1, 2]、その後、デルバンとシャッハーマイヤーらによって、より一般的な形で証明されました [3, 4]。これは、私たちが日常的に目にするデリバティブの価格が、いかに強固な理論的基盤の上に成り立っているかを示しています。
同値マルチンゲール測度とは
リスク中立確率の数学的な正式名称は「同値マルチンゲール測度」です。ここで「マルチンゲール」とは、大雑把に言えば「将来の期待値が現在の値と等しくなる」ような確率過程のことです。リスク中立の世界では、全ての資産価格をリスクフリーレートで割り引いたものは、マルチンゲールとして振る舞います。これは、「全ての資産の期待リターンがリスクフリーレートに等しい」という直感的な説明の、厳密な数学的表現なのです。
リスク中立確率に潜む非対称性と摩擦
この美しく整合的な理論も、現実の市場という複雑な世界に適用される際には、様々な「非対称性」と「摩擦」に直面します。
ポジティブファクター:非対称性(Asymmetry)
理論と現実の間に生じるギャップこそが、高度な知識を持つ市場参加者にとっての収益機会、すなわち非対称性の源泉となります。理論モデルは、取引コストがなく、流動性が無限で、市場が常に合理的に動くことを前提としています。しかし、現実の市場はそうではありません。
例えば、ある複雑なデリバティブの市場価格が、理論的な無裁定価格から一時的に乖離することがあります。これは、市場参加者のモデルの誤り、情報の非対称性、あるいは一時的な需給の偏りなどが原因で起こり得ます。この乖離(シグナル)を、精緻な価格評価モデル [5] とその数学的背景 [1, 2, 3, 4] を駆使して誰よりも早く発見し、裁定取引やそれに近い取引を行うことで、専門的なトレーダーは利益を上げます。理論を知り、その限界を知ることで、初めて現実の市場におけるエッジが生まれるのです。
ネガティブファクター:摩擦(Friction)
一方で、理論が現実で完璧に機能するのを妨げる様々な「摩擦」が存在します。
第一に、そして最大の摩擦が「モデルリスク」です。二項モデル [5] にせよ、より有名なブラック・ショールズ・モデルにせよ、それらは現実の複雑な株価変動を単純化した近似モデルに過ぎません。現実の株価は、モデルが想定しないようなジャンプ(不連続な変動)をしたり、ボラティリティ(変動率)が常に一定ではなかったりします。このモデルと現実とのズレは、特に市場が混乱した際に大きな損失を生む原因となり、モデル自体がリスクの源泉となるのです。
第二に、「取引コストと流動性の摩擦」です。理論は、手数料ゼロで、いつでも好きなだけ売買できる摩擦のない世界を仮定しています。しかし現実には、オプションを複製するためのポートフォリオを組成・維持するには、売買スプレッドや手数料といった取引コストがかかります。これにより、理論価格の周りに「裁定不可能な領域」が生まれ、わずかな価格の歪みは利益に結びつかなくなります。
第三に、「市場の不完備性」という摩擦です。現実の市場は、必ずしも「完備」ではありません。つまり、世の中のすべてのリスクを、既存の金融資産を組み合わせて完全にヘッジ(相殺)できるわけではないのです。このような市場では、リスク中立確率が一意に定まらず、デリバティブの価格も一意には決まらないため、価格評価にさらなる不確実性が生じます。
リスク中立の考え方を投資に活かすためのアクション
リスク中立確率は高度に専門的な概念ですが、そのエッセンスを理解することは、すべての投資家にとって有益です。
すぐできること
まず最も重要なのは、オプションの価格に織り込まれている情報(特にインプライド・ボラティリティ)が、市場による「将来予測」ではないと理解することです。それは、無裁定の枠組みの下で、そのオプションのリスクをヘッジするために、市場がいくらのコスト(保険料)を要求しているか、という指標です。インプライド・ボラティリティが高いからといって、市場が「現実に大きな変動が起こる」と予測していると短絡的に考えるのではなく、「大きな変動に対するヘッジの需要が高い」と解釈するべきです。
長期的に取り組むこと
デリバティブ取引に本格的に関心を持つのであれば、二項モデル [5] のような基本的な価格決定モデルの仕組みを学ぶことは避けて通れません。価格がどのように構築されるかを理解することは、その商品を賢く利用するための第一歩です。
さらに、自身が考える「現実の確率」と、オプション価格から逆算される「リスク中立確率」との間に、どのような差があるかを分析する視点を持つことです。この差には、市場が織り込んでいるリスクプレミアムに関する情報が凝縮されています。もし、自分の分析によって、市場が特定のリスクを過小評価(または過大評価)していると判断できるならば、そこに洗練された投資戦略を組み立てる機会が生まれるかもしれません。
総括
この記事では、現代ファイナンスの中核をなすリスク中立確率という概念を解説しました。
- リスク中立確率は、デリバティブの価格を無裁定の原則に基づき一意に決定するための、数学的な「架空の確率」です。
- この架空の世界では、全ての資産の期待リターンがリスクフリーレートに等しくなると仮定され、リスクプレミアムの推定問題を回避できます。
- 市場に裁定機会が存在しないことと、リスク中立確率が存在することは、数学的に等価であり、これは「資産価格の基本定理」として知られています。
- 理論と現実のギャップは、専門家にとっての収益機会(非対称性)の源泉となります。
- モデルリスクや取引コストといった「摩擦」が、理論の現実への適用を困難にし、リスクの源泉となります。
- 投資家は、オプション価格を将来予測ではなく、リスクの市場価格として理解することが重要です。
用語集
- デリバティブ: 株式、債券、為替などの原資産から派生した金融商品の総称。先物、オプション、スワップなどがある。金融派生商品。
- オプション: ある資産を、将来の特定の期日までに、あらかじめ定められた価格で「買う権利(コールオプション)」または「売る権利(プットオプション)」のこと。
- 裁定取引: 同じ価値を持つ商品の価格が一時的にずれた際に、割安な方を買い、割高な方を売ることで、リスクなく利益を確定させる取引。アービトラージ。
- リスクフリーレート: リスクがゼロの安全資産から得られる利回りのこと。通常、信用力の高い先進国の短期国債の利回りが使われる。無リスク金利。
- マルチンゲール: 確率論の用語。ある確率過程において、過去の全ての情報を与えられた下での、将来の期待値が現在の値と等しくなる性質を持つもの。
参考文献一覧
[1] Harrison, J.M., & Kreps, D.M. (1979) “Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets.” Journal of Economic Theory.https://doi.org/10.1016/0022-0531(79)90043-7
[2] Harrison, J.M., & Pliska, S.R. (1981) “Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading.” Stochastic Processes and their Applications.https://doi.org/10.1016/0304-4149(81)90026-0
[3] Dalang, R.C., Morton, A., & Willinger, W. (1990) “Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models” Stochastics and Stochastics Reports.https://doi.org/10.1080/17442509008833613
[4] Delbaen, F., & Schachermayer, W. (1994) “A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing.” Mathematische Annalen.https://doi.org/10.1007/BF01450498
[5] Cox, J.C., Ross, S.A., & Rubinstein, M. (1979) “Option Pricing: A Simplified Approach.” Journal of Financial Economics.https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1
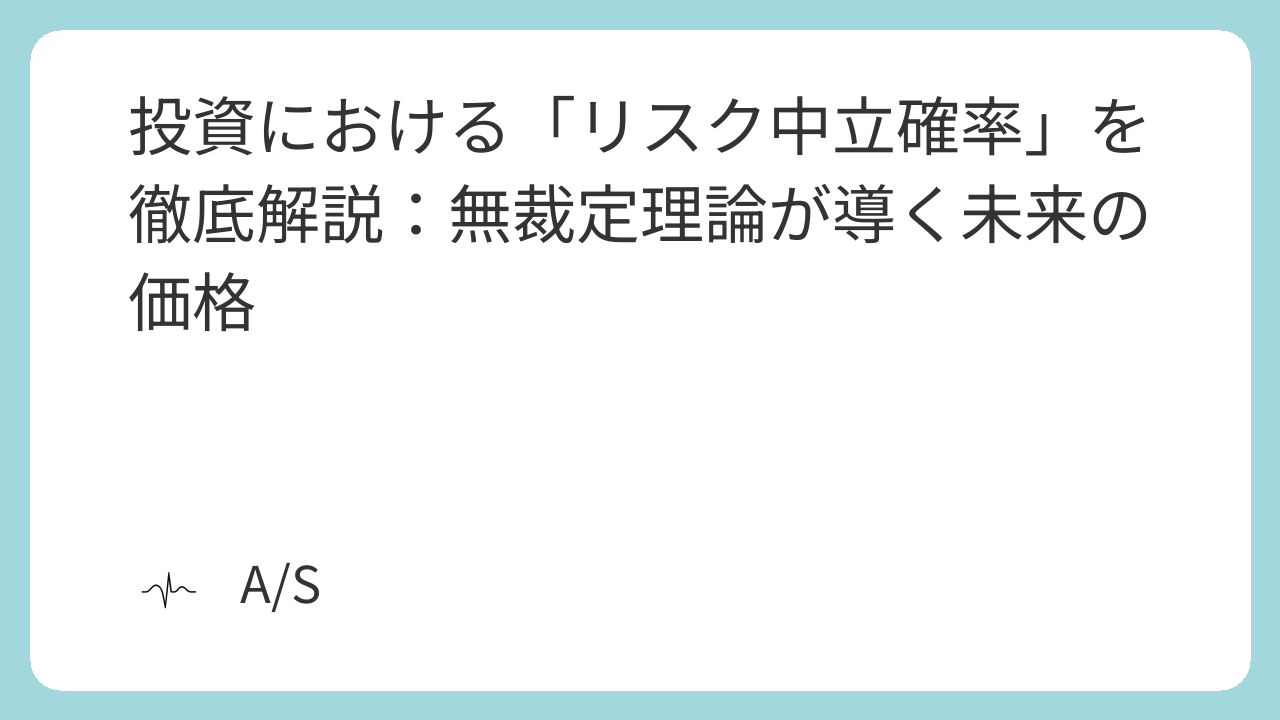
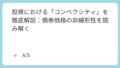
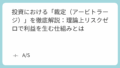
コメント