概論:センチメント分析とは何か?市場の「気分」を測る試みの進化
金融市場の価格は、企業のファンダメンタルズやマクロ経済の動向といった合理的な要因だけで決まるわけではない。そこに、しばしば非合理的で感情的な人間の心理が深く関わっていることは、経験豊富な投資家であれば誰もが肌で感じるところだろう。この捉えどころのない市場の「気分」や「心理」を、客観的かつ定量的に測定し、投資のエッジへと昇華させようとする試み、それがセンチメント分析の核心である。
センチメント分析の根底にある「投資家センチメント」という概念は、学術的には「将来のキャッシュフローと投資リスクに関する、手元の事実では正当化されない信念」と定義される 。これは、市場参加者が時に過度に楽観的になったり、悲観的になったりすることで、資産価格がその本質的価値から乖離する可能性を示唆している。センチメント分析とは、この価格の歪みの源泉となる市場心理を体系的に捉えるためのアプローチなのである。
センチメント分析の初期の試みは、市場参加者に直接その心理を問う、サーベイ(調査)ベースの指標が中心であった。その代表例が、1987年から続く米国個人投資家協会(AAII)のセンチメントサーベイである 。これは、個人投資家に対して今後6ヶ月の株式市場の見通し(強気、弱気、中立)を毎週尋ねるもので、市場の過熱感や悲観の極みを測る指標として、特に逆張りのシグナルとして注目されてきた 。同様に、ミシガン大学消費者信頼感指数のような、より広範な経済心理を測る指標も、投資家心理の代理変数として分析に用いられてきた 。また、市場が織り込む将来の変動期待を反映するCboeボラティリティ指数(VIX指数)は、その性質から「恐怖指数」とも呼ばれ、市場参加者のリスク回避度合いを示すリアルタイムのセンチメント指標として広く認知されている 。
しかし、これらのサーベイや市場ベースの指標は、センチメントを間接的に、あるいは比較的低い頻度でしか捉えられないという限界があった。センチメント分析における真の革命は、コンピューティングパワーの爆発的な向上と、インターネット上に溢れる膨大な非構造テキストデータの出現によってもたらされた。自然言語処理(NLP)技術の進化は、ニュース記事、ソーシャルメディアの投稿、企業の決算報告といったテキストデータから、人々の意見や感情を直接抽出し、定量化することを可能にしたのである 。
この技術的パラダイムシフトは、センチメント分析の性質を根底から変えた。人々が「どう思うか」と答える「表明された選好(Stated Preference)」を測定するサーベイに対し、人々が実際に何を話題にし、何を検索し、何を読んでいるかという「行動」から心理を推測する「顕示された選好(Revealed Preference)」の分析が可能になったのだ。この、より直接的で、よりリアルタイムなセンチメントの測定こそが、現代のセンチメント分析が新たなエッジの源泉として期待される所以である。
【ご案内】
筆者はAI/LLMナラティブ経済学が市場予想において最も将来性が高い領域であると考え、特に重点的に研究しています。もしよろしければ関連記事群もご覧ください。
【AIでマーケットを読み解く】-AI/LLMナラティブ経済学の基礎-
【ナラティブ経済学 入門/概論】
現在上記カテゴリの記事は現在15本程度ですが、最終的にそれぞれ100テーマほど書く予定で、タイトルはすでに決まっています。
センチメント分析の長所と収益機会:テキストデータからアルファを探る
テキストデータから市場心理を読み解く現代的なセンチメント分析は、単なる概念的な存在に留まらず、実際に市場の非効率性を捉え、超過リターンを生み出す可能性が数多くの学術研究によって示されてきた。その収益機会は、分析対象となるテキストソースの多様化と共に拡大してきた。
ニュースメディアのセンチメント分析:ウォール街のコラムが市場を動かす
センチメント分析が学術的に確固たる地位を築くきっかけとなったのが、ポール・テトロックによる2007年の画期的な研究である 。彼は、ウォール・ストリート・ジャーナルの著名なコラム「Abreast of the Market」のテキスト内容を定量化し、メディアの論調が株式市場に予測力を持つことを初めて実証した。
その核心的な発見は、コラムの悲観度(Pessimism)が高い日には、市場価格に下方圧力がかかり、その後数日かけて価格がファンダメンタルズへと回帰する、というパターンが存在することであった 。この「初期の価格反応とその後の反転」という動きは、ニュースが新たなファンダメンタル情報を提供したのではなく、投資家センチメントを介して一時的な価格の歪みを生み出したことを強く示唆している。さらに、悲観度が異常に高い、あるいは低い日には、市場の取引高が急増することも見出された 。これは、センチメントが投資家間の意見の不一致を増大させ、取引を活発化させるという、行動ファイナンスの理論モデルと整合的な結果である。
ソーシャルメディアのセンチメント分析:Twitterが拓いた可能性とその現実
ニュースメディアよりもさらにリアルタイムなセンチメントの源泉として注目を集めたのが、Twitter(現X)に代表されるソーシャルメディアである。膨大な数のユーザーが瞬時に意見を発信するプラットフォームは、市場の集合的な心理を捉えるための理想的な観測所と見なされた。
この分野の初期の研究として特に有名なのが、ボーレン、マオ、ゼンによる2011年の論文である 。彼らは、Twitter上の投稿から抽出した「Calm(穏やかさ)」といった複数の気分の次元が、ダウ平均株価(DJIA)の日々の騰落を予測する力を持つと主張した。その研究では、センチメント指標を用いることで、DJIAの方向性を87.6%という驚異的な精度で予測できたと報告されており、ソーシャルメディアを用いたセンチメント分析への期待を一気に高めることになった 。この研究を皮切りに、ソーシャルメディア上のセンチメントや投稿量が、市場のボラティリティやリターンと関連していることを示す研究が数多く現れた 。
企業開示情報からのシグナル抽出:決算説明会のセンチメント分析
投資家センチメントだけでなく、企業経営者自身のセンチメントもまた、将来の業績を予測する上で重要な情報源となる。その代表的なテキストソースが、企業の決算発表時に行われるカンファレンスコール(決算説明会)の議事録(トランスクリプト)である 。
決算説明会は、経営陣による業績報告のプレゼンテーション部分と、アナリストとの質疑応答(Q&A)部分から構成される。学術研究は、これらの議事録に含まれる言葉のトーンやセンチメントを分析することで、将来の株価リターンを予測できることを示している 。特に、台本が用意されたプレゼンテーション部分よりも、経営陣の即興的な応答が求められるQ&Aセッションの方が、より多くの情報を含んでいる可能性が指摘されている 。また、経営陣の回答だけでなく、アナリストがどのような質問を投げかけるか、その質問のトーン自体も将来のリターンを予測する上で有益なシグナルとなり得ることが示唆されている 。
現代的センチメント分析:FinBERTから大規模言語モデル(LLM)への進化
センチメント分析の精度は、その背後にある自然言語処理(NLP)技術の進化と密接に連動している。初期の辞書ベースの手法から、より文脈を理解する能力に長けた現代的なモデルへの移行は、センチメント分析の能力を飛躍的に向上させた。
この進化における重要なマイルストーンが、FinBERTの登場である 。これは、Googleが開発した画期的な言語モデルであるBERTを、金融分野の大量のテキストデータで事前学習し、金融センチメントの分類タスクでファインチューニング(微調整)したモデルである 。一般的な言語モデルでは理解が難しい金融特有の専門用語や文脈を捉える能力に優れており、センチメント分析の精度を大きく向上させた 。
そして現在、センチメント分析の最前線は、BloombergGPTやFinGPT、そしてGPT-4oに代表される、さらに巨大で高性能な大規模言語モデル(LLM)へと移っている 。これらのモデルは、より広範な知識と高度な言語理解能力を持ち、金融センチメントの分類タスクにおいて、80%を超える高い精度を達成することが近年の研究で報告されている 。この技術的進化は、センチメント分析が捉えることのできる情報の質と深さを、新たな次元へと引き上げつつある。
| アプローチ | 手法 | 長所 | 短所 | 代表的研究・ツール |
| 辞書ベース | 事前定義されたポジティブ/ネガティブ単語リストを用いて単語をカウントする。 | シンプルで透明性が高く、計算が高速。 | 文脈、皮肉、専門用語を理解できず、誤分類が多い。 | Tetlock (2007) |
| 古典的機械学習 | ラベル付けされたデータから、単語の出現頻度などの特徴量を用いてセンチメントのパターンを学習する(例:SVM)。 | 単純な単語カウントを超えるパターンを学習できる。 | 特徴量の設計に専門知識が必要。文脈の理解には限界がある。 | – |
| トランスフォーマー | Attention機構により、文中の単語間の関係性を捉え、文脈に応じた意味を理解する。 | 文脈やニュアンスの理解に優れ、高い精度を達成する。 | 計算コストが高く、モデルの解釈が困難(ブラックボックス)。 | FinBERT |
| 大規模言語モデル (LLM) | さらに巨大なデータとモデルサイズにより、高度な言語理解と生成能力を持つ。 | ゼロショット/フューショット学習能力が高く、多様なタスクに柔軟に対応可能。 | 計算コストが非常に高い。ハルシネーション(幻覚)のリスク。 | BloombergGPT , GPT-4o |
センチメント分析の短所とリスク:そのエッジは本物か?
センチメント分析は、その華々しい研究成果の裏で、数多くの深刻な課題とリスクを抱えている。バックテスト上の驚異的なリターンが、現実の市場では「幻のアルファ」に終わりかねない理由は、技術的な限界から市場の構造的な問題にまで及ぶ。
辞書の壁:金融特有の文脈を無視したセンチメント分析の限界
センチメント分析の初期の研究が直面した根源的な問題は、言語の文脈依存性である。ラフランとマクドナルドによる2011年の影響力のある研究「When Is a Liability Not a Liability?」は、この問題を痛烈に指摘した 。
彼らの分析によれば、一般的なセンチメント分析で広く用いられてきたハーバード大学の辞書は、金融文書のトーンを測定する上で深刻な誤分類を引き起こす。例えば、「liability(負債)」「tax(税金)」「cost(費用)」といった単語は、企業の年次報告書(10-K)においては中立的かつ事実を述べる文脈で使われるのが通常である。しかし、一般辞書ではこれらがネガティブな単語としてカウントされてしまう 。実際に、ハーバード辞書がネガティブと判定した単語の実に4分の3近くが、金融の文脈ではネガティブな意味合いを持たない単語であったことが示された 。この発見は、ドメイン(特定分野)の知識を欠いたナイーブなセンチメント分析がいかに危険であるかを浮き彫りにし、FinBERTのような金融特化モデル開発の必要性を示唆した。
再現性の危機とデータマイニング:「Twitterムード」の熱狂と終焉
センチメント分析の分野は、科学の世界全体を揺るがす「再現性の危機」と無縁ではない。その象徴的な事例が、先に紹介した「Twitterのムードが株価を予測する」というボーレンらの研究を巡る論争である。
ラチャンスキーとパブによる2017年の追試研究は、ボーレンらの元論文を徹底的に検証し、その驚異的な結果を再現することに失敗した 。彼らは、元の結果が、分析期間を恣意的に選択したことによるデータスヌーピング(データマイニング)や、詳細が公開されていない独自のアルゴリズムに起因する偶然の産物である可能性が高いと結論付けた 。この批判を裏付けるかのように、ボーレンらの研究成果を実際の取引に応用するために設立されたヘッジファンド「Derwent Capital Markets」は、運用開始から2年足らずで失敗し、閉鎖に追い込まれている 。この一件は、学術的なバックテストと、現実の市場におけるトレーディングとの間に存在する、深く、そしてしばしば越えがたい溝を物語る強力な教訓である。
幻のアルファ:取引コストがセンチメント分析戦略の利益を蝕むという現実
多くのセンチメント分析戦略、特にソーシャルメディアのような高頻度のデータソースを利用する戦略は、必然的にポートフォリオの高い売買回転率を伴う 。学術的な研究ではしばしば無視されがちな取引コストは、このような戦略の収益性を根底から覆しかねない、極めて重要な現実的制約である 。
取引コストとは、単に証券会社に支払う手数料だけを指すのではない。売値と買値の差であるビッド・アスク・スプレッドや、自らの注文が価格を不利な方向に動かしてしまうマーケットインパクトも含まれる。特に、センチメント・アノマリーが強く現れるとされる銘柄は、流動性の低い小型株であることが多い。これらの銘柄を空売りしようとする際には、株式の借入が困難であったり、非常に高い貸株料が発生したりすることがある。近年の研究では、多くのアノマリーの超過リターン、特にショートサイドの利益は、このような現実的な空売りコストを考慮に入れると、そのほとんどが消滅してしまうことが示されている 。理論上のアルファは、執行の摩擦によって完全に削り取られてしまう危険性が常にあるのだ。
大規模言語モデル(LLM)の課題:ハルシネーションとブラックボックス問題
FinBERTやGPT-4oといった最新のLLMはセンチメント分析の精度を大きく向上させたが、それらが新たな「聖杯」でないこともまた事実である。これらのモデルは、金融という精密さと説明責任が求められる領域で用いるには、特有の課題を抱えている。
第一に、解釈可能性の問題、すなわち「ブラックボックス」問題がある。LLMがなぜ特定のテキストをポジティブ、あるいはネガティブと判断したのか、その判断根拠を人間が理解することは極めて困難である 。これは、リスク管理やモデルのデバッグを著しく難しくする 。
第二に、ハルシネーション(幻覚)のリスクである。LLMは、事実に基づかない情報を、もっともらしく生成してしまうことがある 。金融情報のように正確性が絶対的に求められる分野において、この問題は致命的となり得る。
第三に、金融特有の推論能力の欠如である。LLMは流暢な文章を生成するが、金融分析に不可欠な数値データや比較表現の正確な推論には弱さを見せることが研究で指摘されている 。
最後に、コストとスケーラビリティの問題がある。最先端のLLMの学習と運用には膨大な計算資源が必要であり、これは一部の大規模な金融機関以外にとっては大きな参入障壁となる 。センチメント分析の歴史は、発見、熱狂、裁定、そして摩擦というサイクルを繰り返してきた。新たな技術が登場するたびに、新たなエッジが発見されたように見えるが、やがて多くの参加者がその機会に殺到し、裁定機会は薄れていく。そして最終的に残るのは、取引コストや情報処理の限界といった「摩擦」に見合うだけの、ごくわずかなリターンなのである。このサイクルを理解することは、センチメント分析というツールと冷静に向き合う上で不可欠である。
非対称性と摩擦の視点から解き明かすセンチメント分析
センチメント分析がなぜ機能し得るのか、そしてなぜそのエッジはしばしば現実の取引で捉えきれないのか。その本質は、当メディアの根幹をなす「非対称性(Asymmetry)」と「摩擦(Friction)」の観点から解き明かすことができる。センチメント効果は、市場参加者の行動や情報処理能力に存在する様々な「非対称性」から生まれ、そして市場に存在する様々な「摩擦」によって、完全には消滅しないまま存続しているのである。
Asymmetry:情報の非対称性と「限定された注意力」
センチメント分析が機能する根源には、投資家が情報を処理する際の認知的な非対称性が存在する。その最も代表的なものが、バーバーとオーディアンが2008年の論文「All That Glitters」で提唱した、売買における「探索問題の非対称性」である 。
彼らの主張によれば、投資家が株式を「買う」際には、数千もの銘柄の中から投資対象を選び出すという、途方もない探索問題に直面する。人間の認知能力には限界があるため(限定合理性)、全ての選択肢を合理的に比較検討することは不可能である。その結果、投資家は、ニュースで話題になった、取引高が急増した、あるいは株価が急騰・急落したといった、「注意を引きやすい(attention-grabbing)」銘柄だけを購入の候補とする傾向がある 。一方で、株式を「売る」際には、このような探索問題はほとんど存在しない。なぜなら、大半の個人投資家は、自分が既に保有している、ごく限られた銘柄の中から売却対象を選ぶだけだからである 。この「買う時」と「売る時」の探索プロセスの根本的な非対称性が、注目を集める出来事が、売り圧力よりも買い圧力を不均衡に生み出す原因となる。
この「限定された注意力」仮説は、ダ、エンゲルバーグ、ガオによる2011年の研究で、より直接的な証拠によって裏付けられた 。彼らは、Googleの検索量指数(SVI)を、個人投資家の「注意力」の直接的な指標として用いた。分析の結果、特定の銘柄のSVIが急増すると、その後の短期的な株価上昇と、それに続く長期的な価格の反転(下落)が予測されることがわかった 。これは、注意力の高まりが個人投資家の買いを誘発し、一時的な過大評価(オーバープライシング)を生み出していることを示唆しており、バーバーとオーディアンが提唱した非対称なメカニズムが実際に市場で機能している強力な証拠である。
Asymmetry:センチメントと株価特性の非対称な関係
投資家センチメントが市場に与える影響は、全ての株式に対して均一ではない。センチメントの影響を特に受けやすい銘柄と、そうでない銘柄が存在する。この「影響の非対称性」を体系的に示したのが、ベーカーとワーグラーによる2006年の研究である 。
彼らの理論によれば、センチメントの波が市場を覆った際に、その影響を最も強く受けるのは、「評価が主観的で、かつ裁定取引が困難な」特性を持つ株式である 。具体的には、時価総額が小さい小型株、ボラティリティが高い株、赤字企業、無配当株、急成長株、そして財務的に困難な状況にある株などがこれに該当する 。これらの銘柄は、確固たる評価のアンカー(錨)を持たないため、投資家の楽観や悲観といった感情の揺れに株価が翻弄されやすい。実際に、彼らの分析では、市場全体のセンチメントが高い時期にはこれらの銘柄群のリターンが相対的に低く(=過大評価されている)、センチメントが低い時期にはリターンが相対的に高い(=過小評価されている)という、明確なパターンが確認された 。この株価特性による影響の非対称性は、センチメント分析をより精緻な戦略へと昇華させる上で、極めて重要な示唆を与えている。
Friction:「裁定取引の限界」という根源的な摩擦
もし市場が完全に効率的であれば、センチメントによって生じた価格の歪みは、合理的な裁定取引者によって即座に修正されるはずである。しかし、現実の市場では、価格の歪みが長期間にわたって存続することがある。なぜなら、教科書的な裁定取引は、現実には様々なリスクとコスト、すなわち「摩擦」に直面するからである。この問題を理論的に解明したのが、シュライファーとヴィシュニーによる1997年の金字塔的論文「裁定取引の限界」である 。
彼らの核心的な主張は、現実世界の裁定取引は、自己資金で小規模なポジションを取る無数の投資家によって行われるのではなく、他人の資金を運用する、ごく少数の専門的なプロフェッショナルによって行われる、という点にある 。この「専門知識と資金の分離」という代理人問題(エージェンシー問題)が、裁定取引の有効性を制限する根源的な摩擦となる。例えば、ある裁定取引者がセンチメントによる割高な銘柄を空売りしたとしよう。もし、市場の熱狂がさらに高まり、その銘柄がさらに上昇した場合、裁定取引者は短期的に損失を被る。その損失を見た資金の出し手(投資家)は、裁定取引者の能力を疑い、資金を引き揚げてしまうかもしれない。その結果、裁定取引者は、価格の歪みが最も拡大し、最大の収益機会が訪れているはずのまさにその時に、ポジションの解消を余儀なくされるのである 。この「価格の歪みが是正される前に、資金が枯渇するかもしれない」というリスクが、裁定取引者を臆病にし、センチメントによる価格の歪みが市場に存続することを許してしまうのだ。
Friction:空売り制約と取引コストという物理的な摩擦
「裁定取引の限界」という理論的な摩擦に加え、センチメント・アノマリーの存続を支えているのが、より具体的で物理的な摩擦である。その代表が、空売り制約とそれに伴うコストである。
スタンボー、ユー、ユアンによる2012年の研究は、投資家センチメントと空売り制約の相互作用を分析し、アノマリーの収益構造に存在する決定的な非対称性を明らかにした 。彼らの分析によれば、多くのアノマリーの超過リターンは、市場全体のセンチメントが高い時期に、その戦略の「ショートサイド(空売り対象の銘柄群)」から生まれていることが示された 。これは、投資家の楽観が行き過ぎて生じた過大評価を、空売りによって利益に変えることが、アノマリー収益の源泉であることを意味する。
しかし、なぜこの過大評価は簡単に修正されないのか。その答えが空売り制約という摩擦にある。過大評価されやすい銘柄は、しばしば個人投資家に人気があり、機関投資家の保有が少ないため、空売りのための株式の借入が困難で、高い貸株料が必要となる 。この物理的な摩擦が、裁定取引をコストに見合わないものにし、過大評価が市場に放置されることを許容する 。センチメント・アノマリーは、この空売りという行為にまとわりつく物理的な摩擦によって、その存在を保護されている「要塞」のようなものなのである。この摩擦がなければ、アノマリーはとうの昔に裁定取引によって消滅していたかもしれない。
総括
- センチメント分析は、市場の非合理的な心理を定量化する試みであり、その手法はサーベイ調査から始まり、現代のLLMによる高度なテキスト解析へと劇的に進化してきた。
- 学術研究は、ニュースメディア、ソーシャルメディア、企業開示情報といった多様なテキストソースに含まれるセンチメントが、将来の株価リターンや取引高を予測する力を持つことを一貫して示してきた 。
- しかし、センチメント分析の有効性は、金融文脈の誤解 、再現性の問題やデータマイニングのリスク 、そして取引コストという巨大な「摩擦」によって、現実の取引においては大きく制限される。
- センチメント効果の根源には、投資家が株式を売買する際の「限定された注意力」の偏りや 、センチメントの影響を受けやすい株式の特性(小型株、高ボラティリティ株など)といった「非対称性」が存在する 。
- 最終的に、センチメントに起因するアノマリーが市場に存続するのは、「裁定取引の限界」という理論的な制約 や、「空売り制約」という物理的な摩擦が、価格の歪みを完全に是正することを妨げているからである 。
用語集
センチメント分析 (Sentiment Analysis) ニュース記事、ソーシャルメディア、決算報告書などのテキストデータから、そこに表現されている意見、感情、評価(ポジティブ、ネガティブ、ニュートラルなど)を抽出し、定量化する技術。オピニオンマイニングとも呼ばれる。
自然言語処理 (Natural Language Processing, NLP) 人間が日常的に使っている言語(自然言語)を、コンピュータに処理・解析させるための技術分野。センチメント分析は、NLPの応用分野の一つである。
行動ファイナンス (Behavioral Finance) 伝統的な経済学が仮定する「合理的な人間像」に対し、心理学の知見を取り入れ、人間の認知バイアスや感情が金融市場に与える影響を分析する学問分野。
限定された注意力 (Limited Attention) 人間が一度に処理できる情報量や、注意を向けられる対象には限界があるという概念。投資家が全ての銘柄を常に監視することは不可能であり、注目を集める銘柄に取引が集中する原因となる。
裁定取引の限界 (Limits of Arbitrage) 現実の市場では、裁定取引はリスクやコストを伴うため、価格の歪みを完全に、かつ即座に修正する力は限定的であるという理論。この限界があるため、センチメントによる非効率性が市場に存続し得る。
空売り制約 (Short-Sale Constraints) 制度的な規制や、貸株市場での株式の借入困難、高い貸株料など、特定の銘柄を空売りすることを妨げる様々な要因。過大評価された銘柄の価格是正を遅らせる原因となる。
取引コスト (Transaction Costs) 金融商品を売買する際に発生する費用の総称。売買手数料、ビッド・アスク・スプレッド、マーケットインパクトなどが含まれ、理論上のリターンを現実のリターンへと引き下げる主要な要因である。
辞書ベース手法 (Lexicon-Based Method) センチメント分析の古典的な手法の一つ。「良い」「悪い」といった感情的な極性を持つ単語をリスト化した辞書(レキシコン)を用い、テキスト中に含まれる単語を数えることで全体のセンチメントを判定する。
大規模言語モデル (Large Language Model, LLM) 膨大な量のテキストデータを用いて学習された、非常に巨大なニューラルネットワークモデル。文脈の理解や文章の生成において、人間のような高い能力を示す。GPTシリーズなどが代表例。
FinBERT Googleが開発した言語モデルBERTを、金融分野のテキストで追加学習・ファインチューニングしたモデル。金融特有の専門用語や文脈の理解に優れており、金融センチメント分析の精度を大きく向上させた。
VIX指数 (VIX Index) シカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出・公表している、S&P 500種株価指数オプションの価格から算出される、市場が期待する将来30日間の変動率(ボラティリティ)。「恐怖指数」とも呼ばれ、市場参加者のリスク回避度を示すセンチメント指標として利用される。
データマイニング (Data Mining) 大量のデータの中から、統計的に偶然発生したに過ぎない相関関係を、意味のあるパターンであるかのように見つけ出してしまうこと。バックテストにおいて「偽りのエッジ」を生み出す原因となる。
参考文献一覧
Tetlock, P. C. (2007). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market. The Journal of Finance, 62(3), 1139-1168.
Baker, M., and Wurgler, J. (2006). Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Barber, B. M., and Odean, T. (2008). All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors. The Review of Financial Studies, 21(2), 785-818.
Bollen, J., Mao, H., and Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1-8.
Loughran, T., and McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks. The Journal of Finance, 66(1), 35-65.
Shleifer, A., and Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. The Journal of Finance, 52(1), 35-55.
Stambaugh, R. F., Yu, J., and Yuan, Y. (2012). The short of it: Investor sentiment and anomalies. Journal of Financial Economics, 104(2), 288-302.
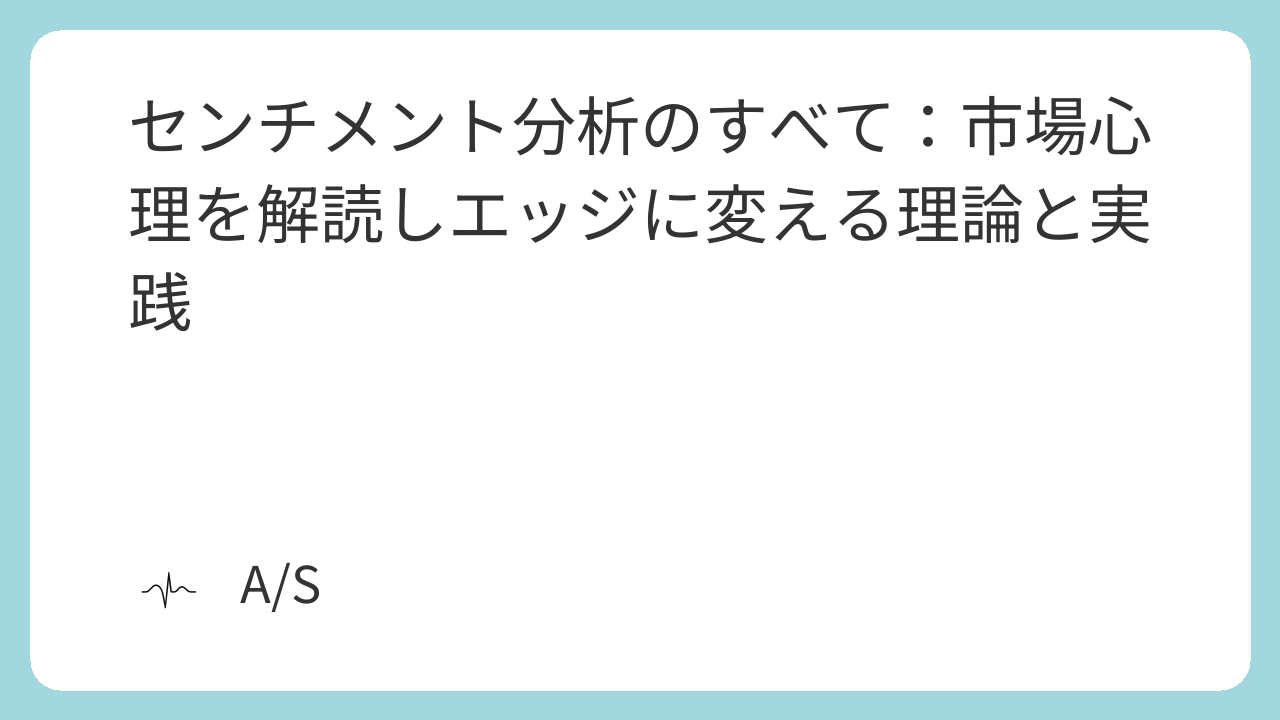
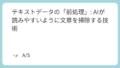
コメント