概論
ポートフォリオを構築し、一度資産配分を決めたら、あとは放置しておけばよいのでしょうか。市場は常に変動しており、何もしなければポートフォリオの中身は当初の計画から大きく乖離していきます。例えば、株式50%、債券50%で始めたポートフォリオが、株価の好調によって気づけば株式70%、債券30%になっているかもしれません。これは、当初意図したものよりも遥かに高いリスクを取っている状態を意味します。
この資産配分の「崩れ」を、規律をもって定期的に修正する行為が、リバランス戦略です。具体的には、価格が上昇して目標比率を超えた資産の一部を売却し、その資金で価格が下落して比率が低下した資産を買い増すことで、ポートフォリオを元の目標資産配分に戻す作業を指します。
この戦略を巡る議論の核心には、「リバランスはリターンを高めるのか、それともリスクを管理するための手段なのか」という根源的な問いが存在します。リバランスが「高く売って、安く買う」という逆張り的な取引を内包するため、特定の市場環境下ではリターンの向上に寄与する可能性が指摘されています。この効果は「リバランス・ボーナス」とも呼ばれ、その源泉は分散されたポートフォリオを機械的にリバランスする行為そのものにあるとされています [1]。
しかし、その主たる価値はリターンの追求よりも、むしろリスク管理にあるという見方が有力です。ある実証研究によれば、リバランス戦略の優位性は、絶対リターンの向上ではなく、ポートフォリオのボラティリティ(リスク)を有意に減少させる点に起因すると結論付けられています [2]。本記事では、このリバランス戦略が持つ二つの側面、すなわちリスク抑制効果とリターン向上効果について、学術的な知見を基にその理論と現実を深く掘り下げていきます。
長所・短所の解説、利益例・損失例の紹介
リバランスは、多くの投資家にとってポートフォリオ管理の基本とされていますが、その効果は万能ではなく、市場の状況によっては裏目に出ることもあります。その長所と短所を、批評的な視点から解説します。
長所、強み、有用な点について
リバランス戦略の最大の強みは、感情を排した規律あるリスク管理を可能にする点にあります。そして、その規律が副次的にリターンを生み出す可能性も秘めています。
まず、最も重要な効果はリスクの抑制です。ポートフォリオを放置すると、一般的にリスクの高い資産(株式など)の比率が時間と共に増加していく傾向があります。リバランスは、この比率を定期的に引き下げることで、ポートフォリオ全体のボラティリティが過度に上昇することを防ぎ、当初定めたリスク水準を維持する役割を果たします。ある実証研究では、リバランス戦略がバイ・アンド・ホールド戦略と比較して、シャープ・レシオなどのリスク調整後リターンを一貫して有意に改善させることが報告されており、その効果はほぼ完全にリスクの低減によるものであることが示されています [2]。
次に、リターン向上効果、いわゆる「リバランス・ボーナス」です。このボーナスは、各資産のリターンが平均回帰的な性質を持つ、すなわち上がったり下がったりを繰り返すレンジ相場で特に発生しやすくなります [1]。このような市場では、リバランスによる「値上がりした資産の売却(利益確定)」と「値下がりした資産の購入(安値拾い)」という機械的な逆張り取引が、単純な保有継続戦略を上回るリターンを生み出すのです。ある研究では、主要な資産クラスのリターン水準が同程度の場合、リバランスがアウトパフォームすることが示されています [3]。
さらに、近年の研究では、取引コストとリターンの予測可能性を考慮に入れた、より動的なアプローチも提案されています。これは、市場の状況に応じて取引のタイミングと規模を最適化するものであり、静的なルールからの進化を示唆しています [4]。
短所、弱み、リスクについて
一方で、リバランス戦略は決して万能薬ではありません。その逆張り的な性質が、特定の市場環境では大きな足かせとなります。
最大の弱点は、一方向に強いトレンドが継続する市場でのパフォーマンス劣後です。例えば、何年にもわたって株式市場だけが上昇し続けるような強気相場では、リバランスは上昇を続ける株式を定期的に売却し、相対的にパフォーマンスの悪い資産を買い増す行為となります。その結果、単純に当初のポートフォリオを持つ続けるバイ・アンド・ホールド戦略に、リターンで大きく劣後することになります。
この現象は、実際の株価指数においても観測されています。ある研究では、米国の小型株指数であるRussell 2000において、指数から除外された銘柄で構成されるバイ・アンド・ホールド・ポートフォリオが、公式にリバランス(銘柄入れ替え)された指数自体を大幅にアウトパフォームしたことが示されました。これは、除外された銘柄がその後強いモメンタム(価格上昇の持続性)を示したためであり、リバランスの逆張り的な性質が裏目に出た典型例です [5]。
また、リバランスは売買を伴うため、取引コスト(手数料やスプレッド)と税金という、無視できない現実的な問題に直面します。特に、頻繁にリバランスを行えば行うほど、これらのコストはリターンを確実に蝕んでいきます。取引コストを考慮すると、リバランスによるリターン向上効果のかなりの部分が相殺されてしまう可能性も指摘されており、リバランスの頻度とコストのバランスを慎重に考慮する必要があります [2]。
非対称性と摩擦の視点から
リバランスという規律ある行動は、なぜこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その本質を、当メディアの根幹をなす「非対称性」と「摩擦」の観点から解き明かすことができます。
Asymmetry:リターンの非対称性と感情の非対称性
リバランスが収益機会を生み出す根源には、市場リターンの「非対称性」があります。資産価格は一方的に上昇し続けるわけではなく、上昇と下落を繰り返します。特に、異なる資産クラス間では、その変動のタイミングがずれることが多く、この非対称な値動きこそがリバランス・ボーナスの源泉となります [1]。リバランスは、この非対称性を利用し、値上がりした資産の利益を確定し、それを原資に割安になった資産へ再投資するという、機械的な価値移転のプロセスなのです。
もう一つの重要な非対称性は、投資家の「感情の非対称性」です。人間は、利益を得る喜びよりも、損失を被る痛みの方を強く感じる傾向があります(プロスペクト理論)。市場が熱狂している時は楽観に傾きすぎてリスクを取りすぎ、市場が悲観に暮れている時は恐怖に支配されて投げ売りしてしまう。リバランスは、この感情の非対称性に対する強力な解毒剤として機能します。熱狂の中で機械的に利益を確定させ、恐怖の中で冷静に買い向かう。この規律が、非合理的な行動から投資家を守り、長期的なリターンを安定させるのです。
Friction:取引コストと「行動」の摩擦
リバランス戦略の有効性を阻害する要因、すなわち「摩擦」は、物理的なものと心理的なものの二種類に大別されます。
まず、最も分かりやすい物理的な摩擦が、取引コストと税金です。リバランスは売買を伴うため、手数料、スプレッド、そして利益確定に伴うキャピタルゲイン税といったコストが必ず発生します。これらの摩擦は、リバランスによるリターン向上効果を直接的に蝕みます [2]。したがって、リバランスの頻度を過度に上げると、この摩擦によってリターンが削られ、本末転倒な結果になりかねません。
しかし、より強力で、多くの投資家が乗り越えられないのが、心理的な「行動の摩擦」です。好調な資産を売却し、不調な資産を買い増すというリバランスの行為は、人間の直感に反します。利益が出ているものを手放すことへの抵抗感(プロスペクト理論における損失回避)や、下落している資産をさらに買い増すことへの恐怖が、規律あるリバランスの実行を妨げるのです。この「分かっていてもできない」という行動の摩擦こそが、多くの投資家がリバランスの恩恵を十分に受けられない、最大の原因と言えるでしょう。
総括
- リバランス戦略とは、市場変動によって崩れた資産配分を、当初の目標比率に定期的に修正する規律あるポートフォリオ管理手法です。
- 最大の長所は、ポートフォリオのリスクを当初意図した水準に維持し、リスク調整後リターンを改善させる効果にあります [2]。
- 市場がレンジ相場のように平均回帰的な動きをする場合、リバランスは「高く売り、安く買う」という逆張り取引を内包するため、「リバランス・ボーナス」と呼ばれるリターン向上効果をもたらす可能性があります [1]。
- 一方で、市場が一方向の強いトレンド(モメンタム)を持つ場合、リバランスはバイ・アンド・ホールド戦略にリターンで劣後する可能性があります [5]。
- リバランスの有効性は、取引コストや税金といった「物理的な摩擦」と、感情に流されて規律を守れない「行動の摩擦」によって大きく左右されます。
用語集
リバランス ポートフォリオ内の資産の価格変動によって変化した資産配分の比率を、元の目標比率に戻すように調整すること。
資産配分(アセットアロケーション) 投資資金を、株式、債券、不動産など、異なる種類の資産(アセットクラス)に、どのような割合で配分するかを決定すること。
ポートフォリオ 投資家が保有する、株式、債券、不動産などの金融資産の組み合わせ、またその一覧。
現代ポートフォリオ理論 ハリー・マーコウィッツによって提唱された、リターンだけでなくリスクも考慮して、最も効率的なポートフォリオを構築すべきだとする理論。
リスク許容度 投資家が、資産価値の変動(リスク)をどの程度受け入れることができるかという度合い。
リバランス・ボーナス リバランスを行うことで、単純に資産を保有し続ける(バイ・アンド・ホールド)場合と比べて、追加的に得られるリターンのこと。「分散リターン」とも呼ばれる。
バイ・アンド・ホールド 一度購入した資産を、市場の短期的な変動に惑わされずに長期間保有し続ける投資戦略。
ボラティリティ 資産価格の変動の激しさを表す指標。一般的に、標準偏差で測定される。
平均回帰 ある変数が、その長期的な平均値から乖離した場合に、将来的に平均値の方向へ戻っていく傾向があるという性質。
逆張り 市場の大多数の投資家の意見や行動とは逆のポジションを取る投資戦略。リバランスは、その性質上、逆張り的な取引を含む。
参考文献一覧
[1] Willenbrock, S. (2011). Diversification Return, Portfolio Rebalancing, and the Commodity Return Puzzle. Financial Analysts Journal, 67(4), 42-49.
https://doi.org/10.2469/faj.v67.n4.1
[2] Dichtl, H., Drobetz, W., & Wambach, A. (2012). Where is the value added of rebalancing?. Working Paper.
※ワーキングペーパーです
[3] Plaxco, L. M., & Arnott, R. D. (2002). Rebalancing a Global Policy Benchmark. The Journal of Portfolio Management, 28(2), 9-22.
https://doi.org/10.3905/jpm.2002.319828
[4] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. The Journal of Finance, 68(6), 2309-2340.
https://doi.org/10.1111/jofi.12080
[5] Cai, J., & Houge, T. (2007). Index Rebalancing and Long-Term Portfolio Performance. SSRN Working Paper Series.
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.970839
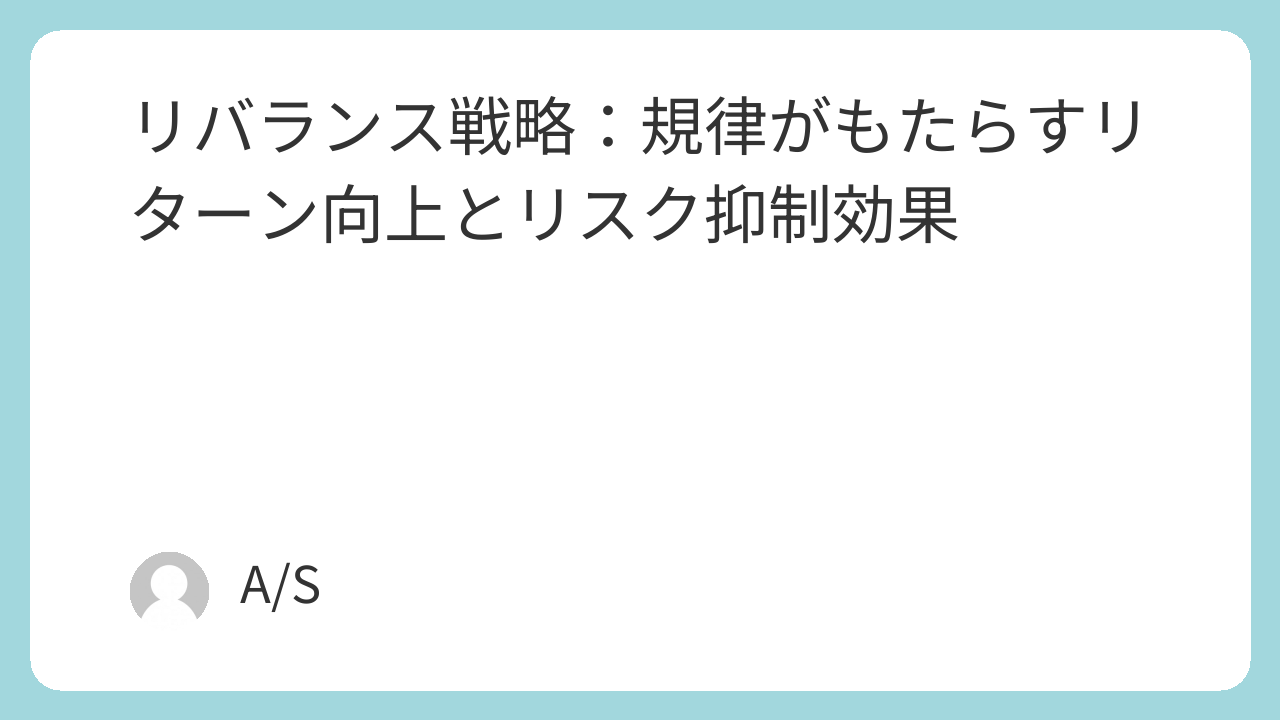
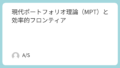
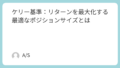
コメント