現代の金融市場は、人間のトレーダーではなく、コンピューターアルゴリズムが取引の主役となっています。その取引スピードはマイクロ秒、あるいはナノ秒の領域に達し、市場の効率性を高める一方で、新たなリスクを生み出しています。その最も象徴的な現象が「フラッシュ・クラッシュ」です。これは、市場価格が数分といった極めて短い時間のうちに、理由なく暴落し、その後すぐに元の水準近くまで急回復する異常な値動きを指します。2010年5月6日に米国市場で発生したフラッシュ・クラッシュは、この現象の代表例として広く知られています [1, 2]。
このような現象はなぜ起こるのでしょうか。その根源には、市場に参加する多数のアルゴリズムが、あたかも一つの思考を持っているかのように、ほぼ同時に同じような行動をとってしまう「アルゴリズムの同質化」という問題が潜んでいます。個々のアルゴリズムは、価格や出来高、注文の状況といった公開情報を基に、利益を最大化するよう合理的に設計されています。しかし、その設計思想や参照するデータが似通っているため、ある出来事をきっかけに、無数のアルゴリズムが一斉に売り注文を出すといった事態が発生するのです。
この記事では、なぜアルゴリズムは同質化してしまうのか、そしてその同質化がどのように市場の流動性を枯渇させ、フラッシュ・クラッシュのような破滅的な現象を引き起こすのかを、学術的な研究成果に基づいて解き明かしていきます。一部の研究では、このような超高速で発生する極端なイベントは、市場の電子化とアルゴリズム取引の普及に伴い、増加傾向にある可能性も指摘されています [3]。
アルゴリズムの同質化がもたらす市場への脅威
なぜアルゴリズムの同質化を理解すべきなのか
今日の金融市場では、取引の大部分がアルゴリズムによって実行されています。これは、もはやアルゴリズムの動向を無視して投資を行うことができない時代になったことを意味します。アルゴリズムの同質化を理解することは、現代市場に内在する構造的なリスクを理解することに他なりません。
この問題の恐ろしい点は、個々のアルゴリズムがそれぞれ合理的に行動した結果として、市場全体が非合理的で破滅的な状況に陥る可能性があることです。例えば、あるアルゴリズムが市場の小さな異変を察知して安全のために取引から撤退することは、単体で見れば合理的な判断です。しかし、数千のアルゴリズムが同じ異変を察知し、一斉に撤退すれば、市場から買い手がいなくなり、価格が暴落する引き金となります。これは、個人の合理的な行動が集団の不利益に繋がる「合成の誤謬」の典型例です。投資家は、自身が意図しない極端な価格変動に突如として巻き込まれ、大きな資産を失うリスクに常に晒されているのです。
同質化が引き起こすフラッシュ・クラッシュのメカニズム
アルゴリズムの同質化は、主に二つのメカニズムを通じてフラッシュ・クラッシュを引き起こします。
一つ目は「流動性の蒸発」です。通常時、高頻度取引(HFT)を行うアルゴリズムの多くは、常に買い注文と売り注文を提示するマーケットメーカーとして機能し、市場に潤沢な流動性(取引のしやすさ)を供給しています。しかし、市場の不確実性が高まると、彼らはリスクを回避するために一斉に注文を取り消し、流動性供給者から消費者へと役割を変えます。2010年のフラッシュ・クラッシュを詳細に分析した研究では、巨大な売り注文をきっかけにHFTが次々と売り側に回り、買い支える存在がいなくなったことが暴落を加速させたと報告されています [1]。
二つ目は「売り圧力の連鎖」です。2010年の事例では、あるミューチュアル・ファンドによるE-mini S&P 500先物への大規模な売り注文が引き金となりました [1]。この最初の大口注文を、他の多数のアルゴリズムが「市場に何か悪い情報が出た」という危険なシグナルとして解釈しました。その結果、価格の下落を検知したアルゴリズムがさらに売り注文を出し、その売りがさらなる価格下落を招き、また別のアルゴリズムの売りを誘発するという、自己増殖的な暴落のループが発生したのです。ある分析によれば、この時、市場の注文フローの「毒性(不利な取引をさせられる危険性)」が急激に高まったことで、多くのアルゴリズムが取引から一斉に撤退し、価格の暴落を止められなくなったと解釈されています [5]。
投資家が被る損失の具体例
個人投資家がフラッシュ・クラッシュに巻き込まれた場合、深刻な損失を被る可能性があります。最も典型的なシナリオは、あらかじめ設定しておいたストップロス注文が意図せず発動してしまうケースです。例えば、ある株式を100ドルで購入し、90ドルにストップロス注文を設定していたとします。フラッシュ・クラッシュによって株価が一瞬だけ80ドルまで暴落し、すぐに100ドルに戻ったとしても、ストップロス注文は最も価格が低い瞬間に約定してしまい、90ドルで売却が確定してしまいます。投資家は本来失うはずのなかった資産を失い、その後の価格回復の恩恵も受けられないという、理不尽な結果に終わるのです。
アルゴリズムの同質化に潜む非対称性と摩擦
Asymmetry:スピードと情報の非対称性
アルゴリズムの同質化の背景には、ナノ秒単位の「スピード」をめぐる非対称性が存在します。
高頻度取引(HFT)を行うトレーダーは、莫大な投資を行って取引所のできるだけ近くにサーバーを設置し、他の誰よりも早く注文を出すことで利益を得ようとします。このスピードの優位性は、他の市場参加者に対する圧倒的な非対称性となります。彼らは、ミリ秒単位で発生する価格のズレを捉えたり、他の投資家の注文動向を先読みしたりすることで、極めて短期的な利益を積み重ねます。
しかし、この熾烈なスピード競争こそが、皮肉にもアルゴリズムの戦略を単純化させ、同質化を招く要因となっています。複雑で時間のかかる分析を行うよりも、単純なシグナル(例えば、価格の急落や注文量の急増)に対して、いかに速く反応するかが優先されるためです。その結果、多くのアルゴリズムが似たようなロジックを採用し、同じシグナルに対して画一的な反応を示すようになり、市場全体の不安定性を高めるのです。
Friction:市場設計が引き起こす摩擦
現代の市場の仕組み自体が、アルゴリズムの同質化とフラッシュ・クラッシュを助長する「摩擦」として機能している側面があります。
その一つが、「連続取引(コンティニュアス・ダブルオークション)」という市場設計です。これは、注文が届き次第、いつでも取引を成立させる仕組みであり、スピードの速さが直接的に有利になるため、HFT間の過度な「軍拡競争」を煽る原因となっています [4]。この問題を緩和するため、一部の研究者からは、例えば100ミリ秒ごとに注文をまとめて一度に約定させる「頻繁なバッチオークション」という新しい市場設計が提案されています [4]。これは、スピードという優位性を無効化し、価格の正確性を優先することで、市場の安定性を高めようとする試みです。
また、「市場の断片化」も摩擦の一つです。同じ金融商品(例えば、特定の企業の株式)が、ニューヨーク証券取引所やNASDAQなど、複数の取引所で同時に取引されています。これにより、ある一つの取引所で発生した価格の混乱が、アルゴリズムを通じて瞬時に他の取引所に伝播し、問題が指数関数的に拡大する可能性があります。この断片化された構造が、フラッシュ・クラッシュの際に売り圧力の連鎖を加速させる一因となりました。
アルゴリズム時代の市場で投資家が取るべき行動
すぐにできること
- ストップロス注文を再考する: 安易に設定したストップロス注文は、フラッシュ・クラッシュのような一時的な価格の乱高下の際に、意図しない安値で資産を売却してしまうリスクを孕んでいます。より低い価格で指値のストップ注文(ストップリミット注文)を使う、あるいは市場が異常な変動を見せている際にはあえて取引を手控えるなど、注文方法について再検討することが重要です。
- 市場のルール変更に関心を持つ: 規制当局や取引所は、フラッシュ・クラッシュの再発を防ぐために、常に新しい規制や市場の仕組みを導入しようとしています。例えば、相場が急変動した際に取引を一時中断する「サーキット・ブレーカー制度」の強化などが挙げられます。こうした動向に関心を持つことは、現代市場のリスクを理解する上で役立ちます。
長期的に取り組むこと
- 徹底したポートフォリオの分散: 特定の株式や資産クラスに投資を集中させることは、その市場でフラッシュ・クラッシュが発生した際に、資産全体に致命的なダメージを受けるリスクを高めます。地理的にも、資産クラス的にも、相関の低い複数の資産に投資を分散させることは、こうした予期せぬイベントに対する最も効果的な防御策の一つです。
- 市場のミクロ構造への理解を深める: アルゴリズム取引、HFT、オーダーブックの動き、流動性の意味など、現代の電子市場が実際にどのように機能しているかについての基本的な知識を身につけることは、長期的に見て賢明な投資判断を下すための土台となります。市場の表面的な価格変動だけでなく、その裏側にある構造を理解しようと努めることが重要です。
総括
フラッシュ・クラッシュは、単なる偶然の事故ではなく、アルゴリズム取引が市場を支配する現代において、いつでも起こりうる構造的なリスクです。
- その根源には、多数のアルゴリズムが同じようなシグナルに反応し、一斉に同じ行動をとってしまう「アルゴリズムの同質化」という問題があります。
- この同質化は、HFT間の過度なスピード競争や、連続取引といった市場の仕組みそのものによって助長されています [4, 5]。
- 同質化したアルゴリズムが一斉に行動を起こす結果、市場の流動性が突如として蒸発し、自己増殖的な価格の暴落が引き起こされるのです [1]。
- 私たち投資家は、こうした新たな市場環境に適応し、ストップロス注文の潜在的リスクを認識したり、ポートフォリオを徹底的に分散させたりといった、新たな防衛策を講じる必要があります。
用語集
- アルゴリズム取引 (Algorithmic Trading) コンピュータープログラムが、あらかじめ定められたルールや指示に基づいて、自動で金融商品の取引を行う手法のこと。
- フラッシュ・クラッシュ (Flash Crash) 金融市場において、価格が数分などの極めて短い時間で突如暴落し、その後すぐに元の水準近くまで回復する現象。
- 高頻度取引 (High-Frequency Trading / HFT) アルゴリズム取引の中でも特に、高性能なコンピューターと高速な通信回線を利用して、ミリ秒やマイクロ秒といった極めて短い時間間隔で膨大な量の取引を繰り返す手法。
- 流動性 (Liquidity) ある金融商品を、市場価格に大きな影響を与えることなく、いつでも売買できる度合いのこと。「流動性が高い」とは、取引が活発で、売りたい時にすぐに買い手が見つかる状態を指す。
- マーケットメーカー (Market Maker) 常に売り気配と買い気配を提示し、他の投資家が取引したいと思った時にその相手方となることで、市場に流動性を供給する役割を担う市場参加者のこと。
- ストップロス注文 (Stop-loss Order) 保有している金融商品の価格が、あらかじめ指定した価格(ストップ価格)まで下落した場合に、自動的に成行注文を出して損失を確定させるための注文方法。
- E-mini S&P 500 先物 米国の代表的な株価指数であるS&P 500種株価指数を対象とした先物取引の一種。取引単位が比較的小さく、流動性が非常に高いため、世界中の投資家に利用されている。
- 市場のミクロ構造 (Market Microstructure) 価格が形成される具体的なプロセスや、取引ルール、市場参加者の行動様式など、市場の微細な構造を研究する金融経済学の一分野。
- バッチオークション (Batch Auction) 一定時間(例:100ミリ秒)ごとに注文を集め、その時間内のすべての注文が単一の価格で同時に約定する取引方式。スピードの優位性をなくす効果が期待される。
- オーダーブック (Order Book) ある金融商品に対する、すべての未約定の買い注文と売り注文を価格順に一覧表示したもの。板情報とも呼ばれる。
参考文献一覧
[1] Kirilenko, A., Kyle, A. S., Samadi, M., & Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market. The Journal of Finance, 72(3), 967-1005.https://www.jstor.org/stable/26652722
[2] Menkveld, A. J., & Yueshen, B. Z. (2019). The Flash Crash: A New Deconstruction. The Review of Financial Studies, 32(6), 2147-2186.https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2721922
[3] Johnson, N., Zhao, G., Hunsader, E., Qi, H., Johnson, J., Meng, J., & Tivnan, B. (2013). Abrupt rise of new machine ecology beyond human response time. Scientific Reports, 3, 2627.https://doi.org/10.1038/srep02627
[4] Budish, E., Cramton, P., & Shim, J. (2015). The High-Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Response. The Quarterly Journal of Economics, 130(4), 1547-1621.https://doi.org/10.1093/qje/qjv027
[5] Easley, D., López de Prado, M. M., & O’Hara, M. (2012). The microstructure of the “flash crash”: Flow Toxicity, Liquidity Crashes, and the Probability of Informed Trading. The Journal of Portfolio Management, 38(2), 118-128.https://doi.org/10.3905/jpm.2011.37.2.118
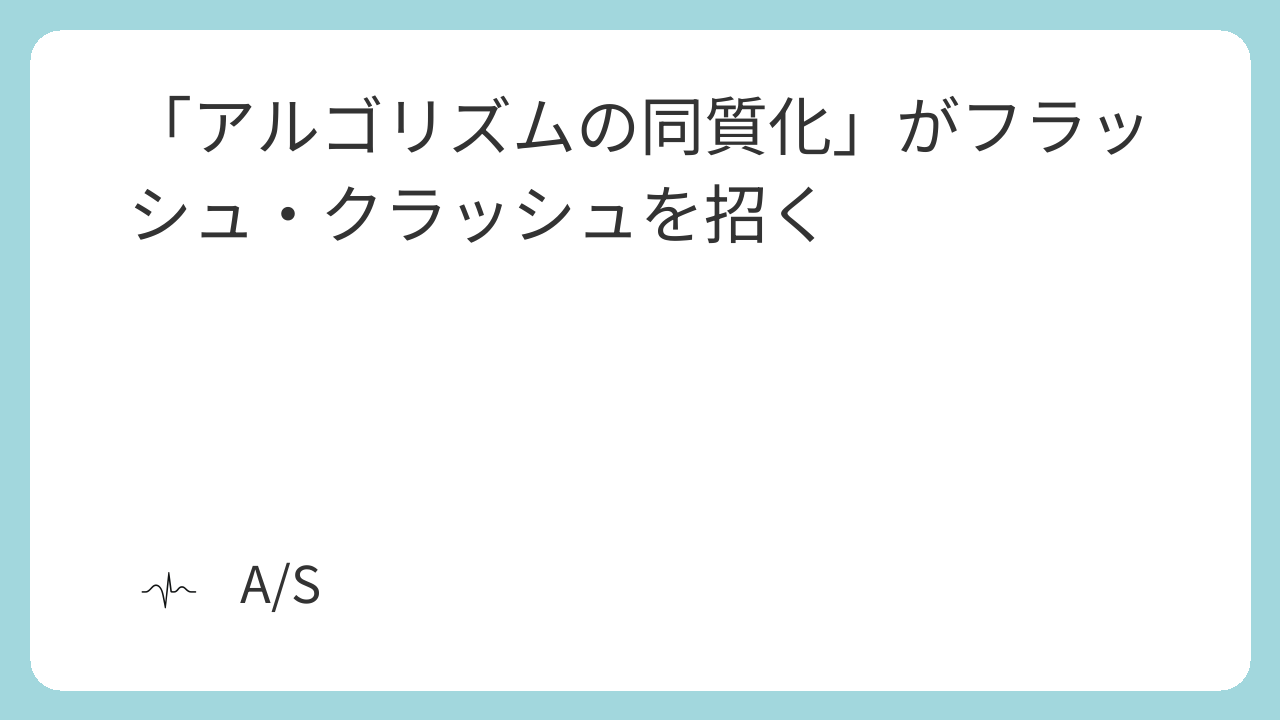
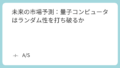
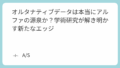
コメント