勝ち続ける投資家の思考を探る
金融市場において、長期的に利益を上げ続ける一握りの参加者が存在します。彼らと、その他大多数の市場参加者を隔てるものは一体何なんでしょうか。運や勘といった曖昧なものではなく、よりシステマティックで、再現性のある優位性、すなわち「エッジ」の存在がその核心にあると、私たちは考えています。
本稿から始まる連載では、この「エッジ」の正体を、学術研究の最前線から解き明かしていきます。勝ち続ける投資家たちはどのような論理に基づいて、95%以上のトレーダーがまだ知らないであろう、どのような収益機会を捉えているのか?そのパターンをご紹介します。
伝統的金融理論への挑戦
トレーディングにおける「エッジ」とは、市場平均を上回り、かつ統計的に有意で持続性のあるリスク調整後超過リターン、すなわち「アルファ」(α)を生み出す能力を指します。
このアルファの存在そのものが、「市場は常に効率的であり出し抜くことはできない」とする効率的市場仮説(Efficient Market Hypothesis, EMH)への根源的な挑戦となります¹。もし市場が完全に効率的ならば、勝者と敗者を分けるのは純粋な運だけのはずです。しかし、SNSの怪しいうわさ話ならまだしも、複数の専門家が重ねて検証している学術研究の世界でさえ、EMHの想定に反するアノマリー(市場の規則性)が多数報告されています。それは一部の参加者が「何か」を捉えて市場を上回っている可能性を示しています。
「ファクター動物園」から宝を見つけ出す
近年、金融経済学の研究は数百にも及ぶ市場アノマリーを発見し、これは「ファクター動物園(Factor Zoo)」と揶揄されるほどの混沌とした状況を生み出しています²。
この混沌の中から、ノイズやデータマイニングの産物ではない「本物のエッジ」を嗅ぎ分け、現実の取引コストを乗り越えて利益を上げるーこれこそが、勝ち続ける投資家たちが行っている知的作業の核心です。本記事では、彼らが駆使してきたエッジの源泉を、学術的根拠に基づいて体系的に解き明かしていきます。
勝者のエッジはどこから生まれるか:アルファの3大源泉
では、持続的なアルファ、すなわち勝者のエッジはどこから生まれてくるのでしょうか。Asymmetry Signalが分析したところ、学術研究で特定されたエッジを主に三つのカテゴリーに分類することが可能でした。これは、トップトレーダーやクオンツファンドがどのような領域で優位性を築いているのかを知るための手がかりになります。
1. 高度な数理モデルとAIの活用:勝者の技術的優位性
現代の市場における勝者たちは、単純な線形モデルを超え、複雑で非線形な資産価格の関係性を捉える技術的優位性を有しています。機械学習(AI)やディープラーニングといった最先端技術の活用は、その象徴です。
- セクショナル・ファクター(Sectional Factors): 市場全体の力学や需給関係そのものからシステマティックなリターンを捉える、より高度なファクターモデルです³ ⁴。
- 機械学習と「ファクターのファクター(FoF)」: 複数の基本ファクターをAIで再帰的に組み合わせ、単一モデルでは見逃される微細なシグナルを増幅させる手法です⁴。
- ディープラーニングによるトレンド識別: CNNやLSTMといった深層学習モデルを用い、人間や従来の指標では不可能なレベルで高精度にトレンドを識別します⁴。
2. 市場の”歪み”の利用:勝者の構造的視点
優れたトレーダーは、個別銘柄の値動きだけでなく、市場全体の「構造」や制度的な「摩擦」に目を向け、そこに生じる非効率性(歪み)をエッジの源泉とします。市場のインフラに根差したこれらのエッジは、比較的持続性が高いと考えられています。
- ショーティング・プレミアム(貸株料プレミアム): 貸株市場という特殊な領域に存在する価格の歪み(貸株料の差)を利用し、専門家のみが引き受けられるリスクの対価としてリターンを得る戦略です⁵。
- カバー付き金利平価(CIP)の乖離: 為替市場において、金融機関の事情などから生じる一時的な価格のズレを捉え、それが修正される過程で利益を得る裁定取引です⁶。
3. “群衆の心理”の逆用:勝者の行動洞察力
市場は、時に非合理な人間の集合体です。勝者たちは、その他大勢の参加者が示す体系的な判断の誤り(認知バイアス)や、特定のニュースに対する過剰/過小反応のパターンを冷静に分析し、それを逆手に取ります。
- 「宝くじ」効果(MAXアノマリー): 大衆が「一発逆転」を夢見て高値掴みしがちな銘柄の特性を見抜き、その後の価格下落から利益を得る戦略です⁷。
- 異常出来高の予測能力: 価格が動く前に出来高が急増する現象を「情報の兆候」と捉え、群衆が気づく前にポジションを構築します⁸。
- 情報イベントと機械学習: 決算書やIPO目論見書のテキスト情報など、人間では処理しきれない膨大な情報をAIで解析し、市場の集合知の一歩先を行きます。
勝者の「思考地図」を手に入れる
今回は、勝ち続ける投資家たちが拠り所とする「エッジ」の源泉が、「①高度な技術」「②市場構造の理解」「③群衆心理の洞察」という3つの大きなカテゴリーに分類できることをお伝えししました。
限られた勝ちトレーダーがどのような「思考地図」を頼りに複雑な市場を勝ち抜いているのか。今回はその輪郭を明らかにしました。自らが得意とする、あるいは探求したいエッジがどの領域に属するのかを意識すると、これからの探求の質を上げられるかもしれません。
次回は、一流の研究者が論文で報告した高利回り戦略の具体例をご紹介します。
巻末用語集
今回は詳しめの説明の記事だったので、初心者の方には難しかったかもしれません。理解の助けになるように、用語をもう少し丁寧に解説します。
アルファ(α)
投資の世界で「市場平均よりどれだけ上回ったか」を示す数値。
例えば市場全体が1年間で+5%成長したとき、あなたのポートフォリオが+8%なら、超過リターンは+3%。これがアルファです。
ただし、単純な差ではなく、「リスク調整後」で比較します。リスク調整とは、より危険な(値動きの大きな)投資で稼いだリターンは割り引いて評価する、という考え方です。安全に近い形で市場を上回ることが「本物のアルファ」とされます。
効率的市場仮説(Efficient Market Hypothesis, EMH)
1960年代に経済学者ユージン・ファーマが提唱した理論で、「金融市場の価格は、すでに利用可能な全ての情報を織り込んでいる」という考え方。
この仮説が正しければ、株価や為替を長期的に予測して市場平均を上回るのは困難であり、勝敗はほぼ運任せになります。
本記事では、この仮説を揺るがす存在を「エッジ」や「市場アノマリー」と説明しています。
ファクター(Factor)
株式や資産のリターンを説明するための「性質」や「特徴」のこと。
有名なファクターには以下があります:
- バリュー(Value)
割安な株(利益や資産に比べて株価が低い)を買い、割高な株を避ける戦略。割安株は長期的に平均より高いリターンを出す傾向がある。 - モメンタム(Momentum)
最近上昇している銘柄はしばらく上がり続け、下落している銘柄はしばらく下がり続ける傾向を利用する戦略。 - サイズ(Size)
時価総額が小さい企業(小型株)は、長期的に大型株よりリターンが高い傾向がある。
ファクター投資とは、こうした特徴を組み合わせて平均を上回るリターンを狙う手法です。
ファクター動物園(Factor Zoo)
学術研究によって提案されたファクターの数があまりに多く(数百種類以上)、本当に有効なものと偶然見つかっただけのものが混在している状況を揶揄した表現。
本記事では、この「動物園」から本物のエッジを見極めることが勝ちトレーダーの仕事だと説明しています。
ショーティング・プレミアム(Shorting Premium)
株式を空売りする際、株を借りるために貸株料を支払う必要があります。貸し手は貸株料を受け取り、この差額(プレミアム)が一部の投資家の利益源になります。
例えば、空売り需要が高い株は貸株料も高く、その貸株を提供できる投資家はリスクの対価として高い利回りを得られます。
裁定取引(Arbitrage)/裁定機会(Arbitrage Opportunity)
異なる市場や商品の間で、同じ価値を持つはずの資産の価格にズレ(不一致)が生じているとき、その差を利用してリスクなしで利益を得る取引のこと。
「裁定取引」は実際にそれを行う行為、「裁定機会」はその価格差が存在する状態を指します。
簡単な例
- 東京市場で金1グラムが7,000円
- ロンドン市場で金1グラム相当が為替換算で7,050円
この場合、東京で買ってロンドンで売れば、手数料を差し引いても利益が残る可能性があります。これが裁定機会です。
特徴
- 理論上はリスクゼロ:ただし実務では、取引コストや時間差で損益が変動することがあります。
- 瞬間的に消える:市場参加者が一斉に取引するため、価格差はすぐに解消されます。
- 種類:
- 空間的裁定:異なる市場間での価格差を利用
- 時間的裁定:同じ資産でも時間差で価格がずれるのを利用
- 統計的裁定:完全な価格一致はなくても、確率的に収束する傾向を利用
記事との関連
今回の記事で紹介した「カバー付き金利平価(CIP)の乖離」は、典型的な裁定機会の一つです。為替と金利の関係が理論値から外れたとき、そのズレを利用するのが裁定取引です。
とりわけクリプト(暗号資産)市場において裁定取引は頻繁に出現します(とはいえ、最近では全盛期に比べれば無に等しいですが)。クリプトの裁定取引は本サイト管理者の筆者A/Sが得意としている手法でもあります。
カバー付き金利平価(Covered Interest Parity, CIP)
異なる国の通貨間で、金利差を為替スワップで調整した場合、裁定(ノーリスク利益)が発生しないように価格が決まるという理論。
しかし現実の市場では、金融機関の資金需要や規制などでこの平価が崩れる瞬間があり、そのズレを利用する取引が可能になります。
MAXアノマリー(宝くじ効果)
過去に「1日の最大上昇率」が極端に高かった銘柄は、その後の平均的なリターンが低くなる傾向があるという現象。
理由の一つは、人々が「宝くじのように大きく跳ねる株」を好むため、高値掴みをしてしまい、その後値下がりするケースが多いからです。
異常出来高効果
出来高(売買の成立件数)が急に増えた銘柄は、その後価格が大きく動く傾向があるという観察結果。
これは、出来高増加が「新しい情報が市場に入り始めたサイン」であることが多く、大口投資家の先回りを可能にします。
リスク調整後リターン
単純な利益率ではなく、「どれだけのリスクを取ってそのリターンを得たのか」を考慮した指標。
例えば、低リスクで+8%の利益を出した投資と、高リスクで+8%の利益を出した投資では、前者の方が評価されます。代表的な評価方法にシャープレシオがあります。
引用文献
- Malkiel, B. G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. Journal of economic perspectives, 17(1), 59-82.
- Kolari, J. W., Huang, J. Z., Liu, W., & Liao, H. (2025). A Quantum Leap in Asset Pricing: Explaining Anomalous Returns. Journal of Risk and Financial Management, 18(7), 362.
- Davis, C., Fabozzi, F. A., & Gandhi, A. (2023). From Style to Sectional Factors: A New Framework for Systematic Investing. The Journal of Portfolio Management, 49(8), 1-22.
- Fabozzi, F. A., et al. (2023). (As described in) The Journal of Financial Data Science, Spring 2023. Portfolio Management Research.
- Drechsler, I., & Drechsler, P. (2014). The shorting premium and the pricing of positive skewness. The Journal of Finance, 69(4), 1475-1512. (NBER Working Paper w20282)
- Du, W., Tepper, A., & Verdelhan, A. (2018). Deviations from covered interest rate parity. The Journal of Finance, 73(3), 915-957. (NBER Working Paper w26009)
- Bali, T. G., Cakici, N., & Whitelaw, R. F. (2011). Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. Journal of Financial Economics, 99(2), 427-446.
- Gervais, S., Kaniel, R., & Mingelgrin, D. H. (2001). The high-volume return premium. The Journal of Finance, 56(3), 877-919.

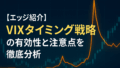
コメント