もしあなたの銀行預金の金利が年2%だとしたら、あなたの資産は本当に増えているのでしょうか。多くの人は「はい」と答えるかもしれません。しかし、もし同じ年に物価が3%上昇していたとしたらどうでしょう。数字の上では2%増えたように見えても、そのお金で買えるモノの量は、実質的に1%減ってしまっています。この、額面上の価値と、実質的な購買力との違いを捉えるのが「名目」と「実質」という概念です。
一般的に「名目(Nominal)」とは、インフレーション(物価上昇)の影響を調整していない、私たちが日常的に目にする価格や金利の数値を指します。一方で「実質(Real)」とは、名目の数値からインフレの影響を取り除き、そのお金が持つ本当の購買力を示したものです。賢明な投資家が最終的に関心を持つべきは、名目上のリターンではなく、この実質的なリターン、すなわち資産の購買力がどれだけ増えたか、です。
この名目金利、実質金利、そして期待インフレ率の関係性を初めて体系的に示したのが、経済学者のアーヴィング・フィッシャーです [1]。彼が提唱した「フィッシャー方程式」は、以下の式で表されます。
名目金利 ≒ 実質金利 + 期待インフレ率
この単純な関係式は、金融と投資の世界における最も基本的な原則の一つです。この記事では、インフレという静かなる資産の侵食者から自分たちの富を守るために不可欠な「実質」と「名目」の考え方を、学術的な知見を交えながら徹底的に解説します。
「実質」と「名目」の混同が引き起こす投資の罠
この二つの概念を区別できない、あるいは意識しないことは、投資家が陥りやすい深刻な罠の入り口です。気づかぬうちに資産価値を損ない、誤った投資判断を下す原因となります。
インフレを知らないことのリスク:名目リターンの幻影
投資家が陥る最も一般的な過ちは、名目リターンに満足してしまう「貨幣錯覚」です。例えば、ある投資信託が年間5%のリターンを達成したとします。この数字だけを見れば、良好な成果のように思えるかもしれません。しかし、同年のインフレ率が6%だった場合、この投資家は実質的には1%の損失を被っており、資産の購買力は減少しています。名目上の利益という幻影を追いかけることで、インフレによって資産が静かに目減りしていくという現実から目を背けてしまうのです。
利益例:実質リターンを意識した資産選択
インフレが高進している時期に、実質と名目の違いを理解している投資家は、その知識を利益に変えることができます。彼らは、固定金利の債券のような、リターンが名目値で固定されている資産の価値がインフレによって大きく損なわれることを知っています。そのため、彼らは資産の一部を、物価の上昇と共に価値が上がりやすいとされる実物資産(例えば不動産)や、インフレ連動国債(TIPS)といった、インフレに強い資産へと戦略的に移します。これにより、インフレ下でも資産の「実質」的な価値を守り、成長させることが可能になります。
損失例:デフレ下での名目金利の罠
インフレとは逆に、物価が持続的に下落するデフレーションの環境下でも、この概念を知らないと損失を被ることがあります。例えば、デフレ率が年2%の状況で、銀行預金の金利が年1%だったとします。名目金利1%は非常に低く、魅力がないように見えます。しかし、実質金利は「1% – (-2%) = 3%」となり、非常に高いリターンです。この状況を理解できない投資家は、わずか1%の名目金利を嫌い、より高い名目リターンを求めて不必要なリスクを取ってしまうかもしれません。デフレ下では、安全なはずの現預金が、実質的には有力な投資対象となるのです。
フィッシャー効果は本当に現実の市場で機能するのか
フィッシャーが提唱した「名目金利は実質金利と期待インフレ率の和で決まる」という考え方は、フィッシャー効果と呼ばれ、現代金融理論の基礎となっています。しかし、この理論は現実の市場で常に完璧に機能するのでしょうか。
理論の検証と現実
フィッシャー効果が正しければ、名目金利の動きは、将来のインフレ率を予測する上で有効な手がかりとなるはずです。1970年代、ユージン・ファーマによる影響力のある研究は、米国の短期金利が将来のインフレ率に関する情報を実際に含んでおり、市場はある程度、フィッシャー効果に沿って動いていることを示しました [2]。これは、市場参加者がインフレを予測し、それを名目金利に織り込んでいるという考えを支持するものでした。
しかし、その後の多くの研究は、この関係が常に安定しているわけではないことも明らかにしています。例えば、フレデリック・ミシュキンによる再検証では、短期的な視点で見ると、金利とインフレの間の関係はそれほど強くなく、他の要因によって大きく変動することが示されています [3]。つまり、フィッシャー効果は長期的な傾向を捉える上では強力な枠組みですが、短期的な市場の動きを完全に説明する万能の法則ではない、と理解することが重要です。
実質・名目間に潜む非対称性と摩擦
当メディアの分析の核である「非対称性」と「摩擦」の観点からこの問題を捉えると、なぜ理論通りに市場が動かないのか、そしてそこにどのような投資機会が生まれるのかが見えてきます。
ポジティブファクター:非対称性(Asymmetry)
市場における最大の収益機会(非対称性)は、多くの市場参加者が「実質」と「名目」を混同してしまうという、体系的な誤りから生まれます。この現象は「インフレ錯覚(貨幣錯覚)」として知られています。フランコ・モディリアーニとリチャード・コーンによる著名な論文では、1970年代の米国株式市場が歴史的に見て極めて割安に放置されていた原因が、このインフレ錯覚にあると論じられました [5]。
彼らによれば、投資家は二つの大きな間違いを犯していました。第一に、企業の将来の利益(キャッシュフロー)を評価する際に、インフレを反映した高い「名目」金利で割り引いてしまったこと。第二に、インフレが企業の負債の実質的な価値を減らす(=株主にとってはプラス)という効果を、企業価値の評価に正しく織り込まなかったことです。市場の大多数がこの認知バイアスに囚われている中で、インフレの影響を正しく計算し、「実質」の価値を見抜くことができた投資家は、不当に安くなった優良企業の株式を仕込む絶好の機会を得たのです。このように、市場参加者の間に存在する「実質思考」と「名目思考」の格差こそが、非対称なリターンの源泉となります。
ネガティブファクター:摩擦(Friction)
一方で、市場がフィッシャー効果の示す通りにスムーズに調整されるのを妨げる、様々な「摩擦」が存在します。
第一の摩擦は、前述の「インフレ錯覚」という認知的な摩擦です [5]。人間は本能的に、目の前の名目的な数値で物事を判断するようにできており、インフレによる購買力の変化を直感的に理解することは困難です。この根深いバイアスが、市場全体の非合理的な価格形成につながります。
第二に、制度的な摩擦です。私たちの経済社会は、多くの部分が名目値ベースで設計されています。例えば、税制は通常、インフレを考慮しない名目上のキャピタルゲインに対して課税します。インフレ率が高い時期には、実質的には利益が出ていないにもかかわらず、名目上の利益に対して多額の税金を支払わなければならないケースさえ起こり得ます。このような制度が、資産価格の合理的な調整を妨げる摩擦として機能します。
さらに、資産の種類によってインフレへの反応が異なることも摩擦の一因です。例えば、ある研究では、米国の住宅不動産はインフレに対する良好なヘッジ手段として機能した一方で、株式のリターンはインフレと負の相関関係にあったことが示されています [4]。このように、資産ごとにインフレとの関係性が違うという複雑さが、ポートフォリオ全体での最適な調整を困難にするのです。
実質リターン思考を投資に活かすための具体的なアクション
「実質」と「名目」の違いを理解したら、次はその知識を具体的な投資行動に結びつけることが重要です。
すぐできること
まず、あらゆる投資リターンや金利を見るときに、現在のインフレ率(例えば、消費者物価指数CPIの前年比上昇率)を必ず確認する習慣をつけましょう。そして、「名目リターン – インフレ率」という簡単な計算で、その投資がもたらすおおよその実質リターンを頭の中で見積もるのです。これにより、表面的な数字に惑わされることなく、投資案件の本質的な価値を評価する癖がつきます。
長期的に取り組むこと
長期的には、インフレ環境の変化に対応できる強靭なポートフォリオを構築することを目指すべきです。そのためには、様々な資産クラスがインフレに対してどのように振る舞うかを理解することが不可欠です。過去の研究によれば、株式は短期的にはインフレに弱い反応を示すことがある一方で、不動産や物価連動国債などはインフレヘッジとして有効な場合があるとされています [4]。これらの知見を参考に、インフレに強い資産と弱い資産を組み合わせ、どのような経済環境でも資産の実質価値が大きく損なわれないような、バランスの取れた資産配分を心がけましょう。特に、ポートフォリオの債券部分には、インフレ率に連動して元本が増えるインフレ連動国債(TIPS)などを組み入れることを検討する価値は高いでしょう。
総括
この記事では、インフレ時代の投資家にとって必須の知識である「実質」と「名目」の概念について解説しました。
- 名目値はインフレを考慮しない額面上の数値、実質値はインフレを考慮した真の購買力を示します。
- フィッシャー効果によれば、「名目金利 ≒ 実質金利 + 期待インフレ率」という関係が成り立ちます。
- 多くの投資家が名目値で物事を考えてしまう「インフレ錯覚」は、市場に非効率な価格形成をもたらします。
- この市場の体系的な誤りを理解し、常に「実質」ベースで思考できる投資家は、非対称な収益機会を捉えることができます。
- 認知バイアスや、名目値ベースの税制・契約などの制度が、市場の合理的な調整を妨げる「摩擦」として機能します。
- 投資家は、インフレ率を常に意識し、様々な資産クラスのインフレ耐性を考慮したポートフォリオを構築することが求められます。
用語集
- 名目金利: インフレ率を考慮しない、預金や債券の額面に表示された金利。
- 実質金利: 名目金利から期待インフレ率を差し引いた、資産の実質的な購買力の成長率を示す金利。
- インフレーション: 物価が全般的に継続して上昇する経済現象。通貨の購買力が低下すること。
- フィッシャー効果: 名目金利が、市場参加者の期待インフレ率を反映して変動するという理論。
- 購買力: 一定額の通貨で購入できる財やサービスの量。インフレが上がると購買力は下がる。
- 貨幣錯覚: 人々が、貨幣の額面価値(名目値)と実質価値(購買力)を混同してしまう傾向のこと。インフレ錯覚とも呼ばれる。
参考文献一覧
[1] Fisher, I. (1896) Appreciation and Interest.※書籍です。
[2] Fama, E. (1975) “Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation,” The American Economic Review.https://www.jstor.org/stable/1804833
[3] Mishkin, F. (1992) “Is the Fisher Effect for Real? A Reexamination of the Relationship between Inflation and Interest Rates,” Journal of Monetary Economics.https://doi.org/10.1016/0304-3932(92)90060-F
[4] Fama, E. & Schwert, G. (1977) “Asset Returns and Inflation,” Journal of Financial Economics.https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90014-9
[5] Modigliani, F. & Cohn, R. (1979) “Inflation, Rational Valuation and the Market,” Financial Analysts Journal.https://www.jstor.org/stable/4478223
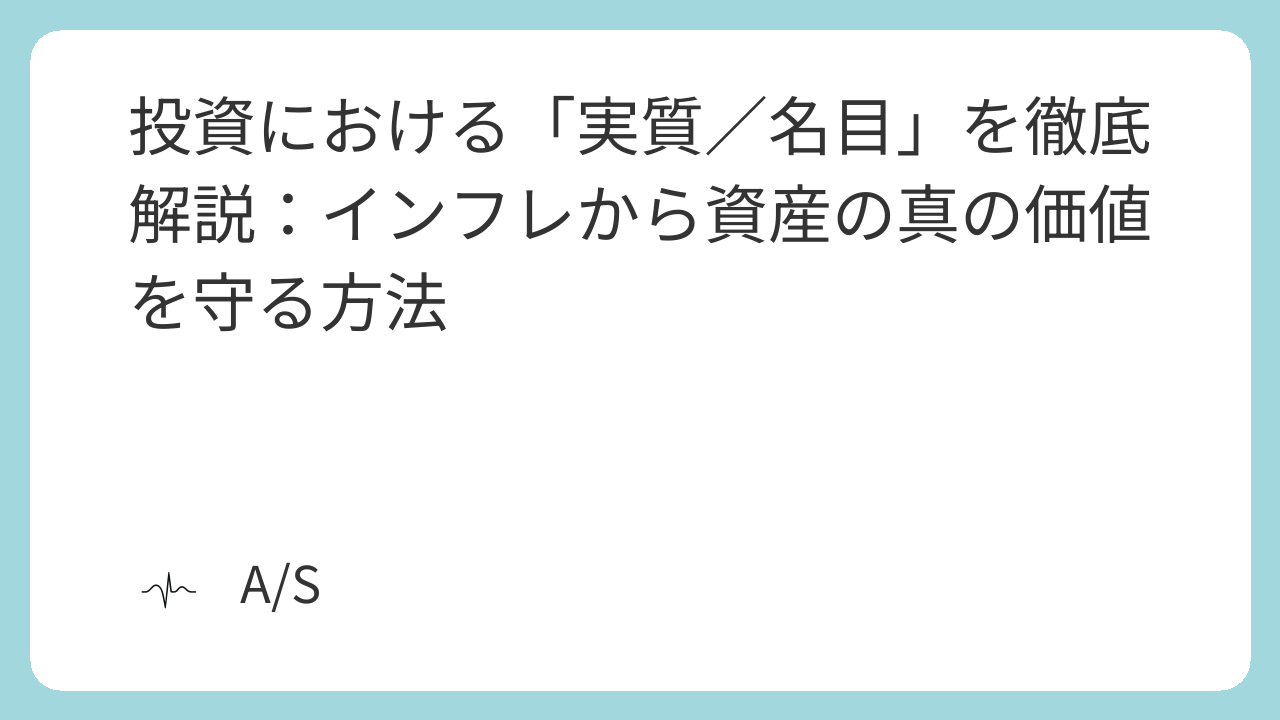
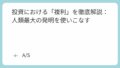
コメント